楠町の生い立ちを町史から拾ってみると・・・
楠村の誕生
楠が地上に出現した時代は明言できないが、地名、万葉集の歌から考察すると、河原田、河尻、塩浜、羽津、富田をつらねる線は海岸であった。自然楠も万葉の時代、五世紀から七世紀の頃まで、海中か海浜であった。次第に、海の後退と鈴鹿川の土砂堆積により陸地化していった。初め本郷、南川から北一色、小倉、五味塚とでき、デルタ地帯として造成された。五味塚は鈴鹿川の派川ができて、南北に分かれたとも考えられる。
楠の地名の由来にも諸説ありはっきりしないが、
・楠山城初代城主諏訪十郎が、北畠国司被官として、正平24(1369)年に信州諏訪から本郷の城に城主として任ぜられて楠十郎と改めたと伝説にはある。
・吉田東湖「大日本地名辞典」に、楠郷とは郷名に非ず、古昔「楠氏」居住に拠って名づくる処なるべし、とあるが、これは俗称であろう。城のあった本郷は、古昔中島と称せられたところであって、明治22(1889)年に7ヶ村が合併して、楠村となり、昭和15年2月11日町制が施行せられて楠町となり現在に至っている。
以上、述べてきたが、いずれにせよ文治元(1185)年に、加藤景廉が北勢5郡の守護になったころの史料に三重郡内の郷として、葦田、河後、柴田、刑部、釆女、吉田、六名、楠、知積の九郷を数えているものもあり、楠の名称は古くからあったものと考えられる。
楠の各町(旧大字)の由来
(1)北五味塚
五味塚の名称は、久美塚の転化で、豊かな土壌の堆積したところの意から生じたとも、一説には
塩汲場で、その塩味の美味なところから五味塚と言ったとのことで、現在小字に「塩役」「汐入り」「塩後り」
という名称があるところから塩取場であったと思われる。
神社の棟札の中に天正16年(1588)のものがあり、楠郷五味塚とある。
富田忠左ェ門、堀七郎右ェ門の二家は、古くからの村の名門として、明治維新に及んだ。
(2)五味塚新田
五味塚から分かれて、東に新田ができたのはいつであるか明瞭ではないが、元禄13年(1700)の
文書に北五味塚新家 氏子中肝入 杉野平兵衛とあることから、杉野平兵衛が開発者であろう。
(3)南五味塚
楠最大の部落で、昭和の初め頃まで漁業も盛んだった。秀吉は文禄の役にあたって、長島、大島、
桑名、四日市、長太、若松、楠、別保、栗真、白子、白塚、津、松崎の13浦に船の動員を命じていて
相当の港であったことがわかる。(以下、筆者注:当時、大きな港があったのは、北楠だったのではないか)
元禄2年(1689)棟札に江戸鉄砲須本港町、伊勢屋六兵衛の名とともに、庄屋伝右衛門、
同9年庄屋林善右衛門の名が見える。
(4) 南川
応永8年(1401)の創建になる天台宗末寺南川聖洞寺は、寛政6年(1465)真宗高田派に転じた古刹
であるが、山号を瓜生山と称した。南川の地名は鈴鹿川の南にあるのでこの名がでたのであろう。
(5)本郷
本郷は往昔中島と称したが、名草と書かれた記録も存在する。これは、この村が海に接し名草浜と
称したことによるものであろう。
楠の中で早く開けたところで、中世中島4郷と称したが、暫次人口が増加し、後楠7郷の中に数えられた
とみられる。楠城のあったところから、本郷の名がつけられたのであろう。本郷には楠村神社、八幡社、
山祇社、菅原社の外、城主の菩提寺正覚寺、来教寺、今は廃寺となった華台寺、泰応寺等があった。
河原田村貝塚は本郷より移住せる人々によって起れる村なりともあり。
(6)小倉
文禄5年(1596)三重郡楠小倉之郷の棟札があり、この棟札に「地下舟乗衆より(中略)きしん」の文字があり、
この地に舟乗があったと見ることができ、また、西対岸近くの川尻と通船していたことが口碑に残されている。
(7)丑ノ新田
万治4年(1660)の棟札に、「万治4年、泰建立神明御社、丑4月吉日 願主 立木茂十郎、
立木七郎右衛門、高橋又兵衛、字氏子中 小倉村新田」とあって、丑ノ年万治4年これらの人たちによって
新田を開発し、同時にお宮を建立し神明社を祀った。それで丑ノ新田と名づけたものであって、
その子孫が代々庄屋、年寄として村治にあずかった。
(8)北一色
北一色は地勢上小倉、本郷、南川とともに最も古くから開けたところと考えられる。
(9)吉崎
往昔は五味塚の属邑であった。吉崎新田の名称は天保5年の地図にでている。
明治9年度会県廃止、三重県に併合の際に独立の大字となった。
吉崎の防潮壁に絵を描きました。(1998.8.1)
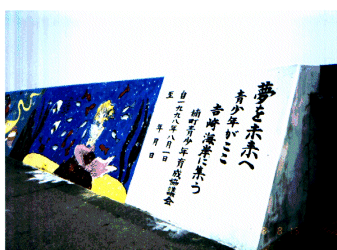

今年も吉崎の防潮壁に絵を描きました。(1999.7.25)


防潮壁の絵も3年目です。少しは進歩したかな。(2000.7.22)

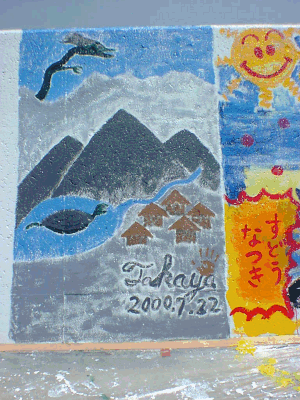
今年もありました。参加できませんでしたが・・・(2001.7.21)


今年で5年目になります。関係者のみなさんご苦労さまです。(2002.7.20)


6年をかけた事業(イベント)が完成しました。お疲れ様でした。(2003.7.20)


6年間の事業報告が、楠青少協のホームページに掲載されています。
こちらをクリック
☆ 楠町一口コラム ☆
夢の跡 〜 吉崎の養魚池 〜

吉崎海岸地区は湿潤の土地が多かったが、安政元年六月十五日の大地震で池となったところもあった。周囲の田も浸水しがちであったので、土を掘り上げ、高い場所へ作付し、低地は悪水路、あるいは水溜となった水面を利用し、魚の繁殖を計ったりしていた。これを溜池と言った。
明治四十二年に人工投飼養魚池が始められたのは、四日市市の磯津から移住してきた石田甚吉が最初であった。池は水面より三尺ほど掘り下げ、その土で周囲に堤防を築いて池を作り、木曽川流域、桑名、弥富、津島方面から購入した鰻、鯉、鮒、いななどの稚魚を放養した。飼料は生蛹、乾蛹、蜆、田螺、蝦、鰛など細かく粉砕した物を、時間を定めて与えていた。
養魚池は、大正八年の最盛期の頃には、経営者一三戸、広さ十六町歩に及びました。(以上「楠町史」より)
養魚池は、現在でも若干の活用はあるようですが、安全面を含め、跡地の再開発が課題といえましょう。
 楠総合支所のホームページへ
楠総合支所のホームページへ  楠地区青少年育成推進指導員協議会のホームページへ
楠地区青少年育成推進指導員協議会のホームページへ(吉崎海岸防潮堤壁画作成の主催者です)