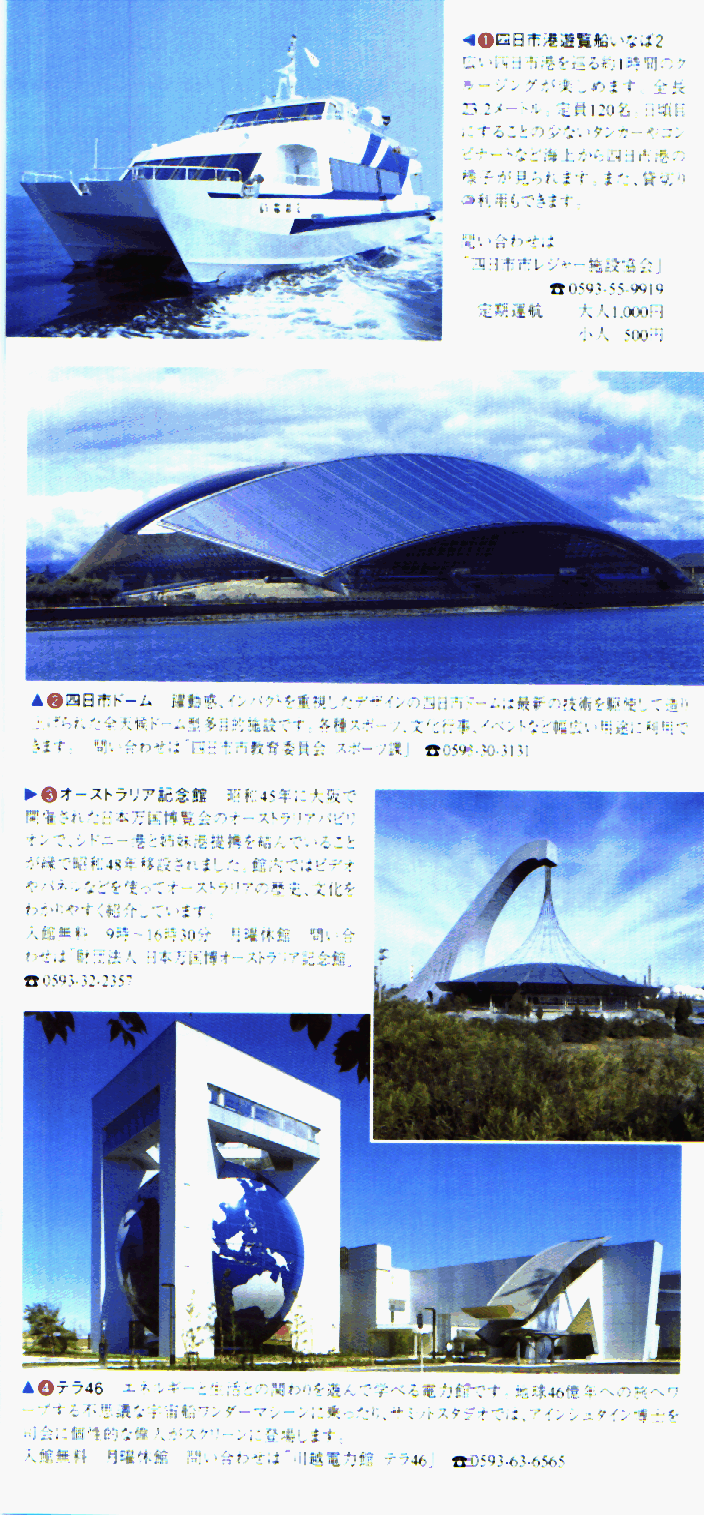
 四日市港周辺の見所
四日市港周辺の見所
港とともに発展する都市「四日市」
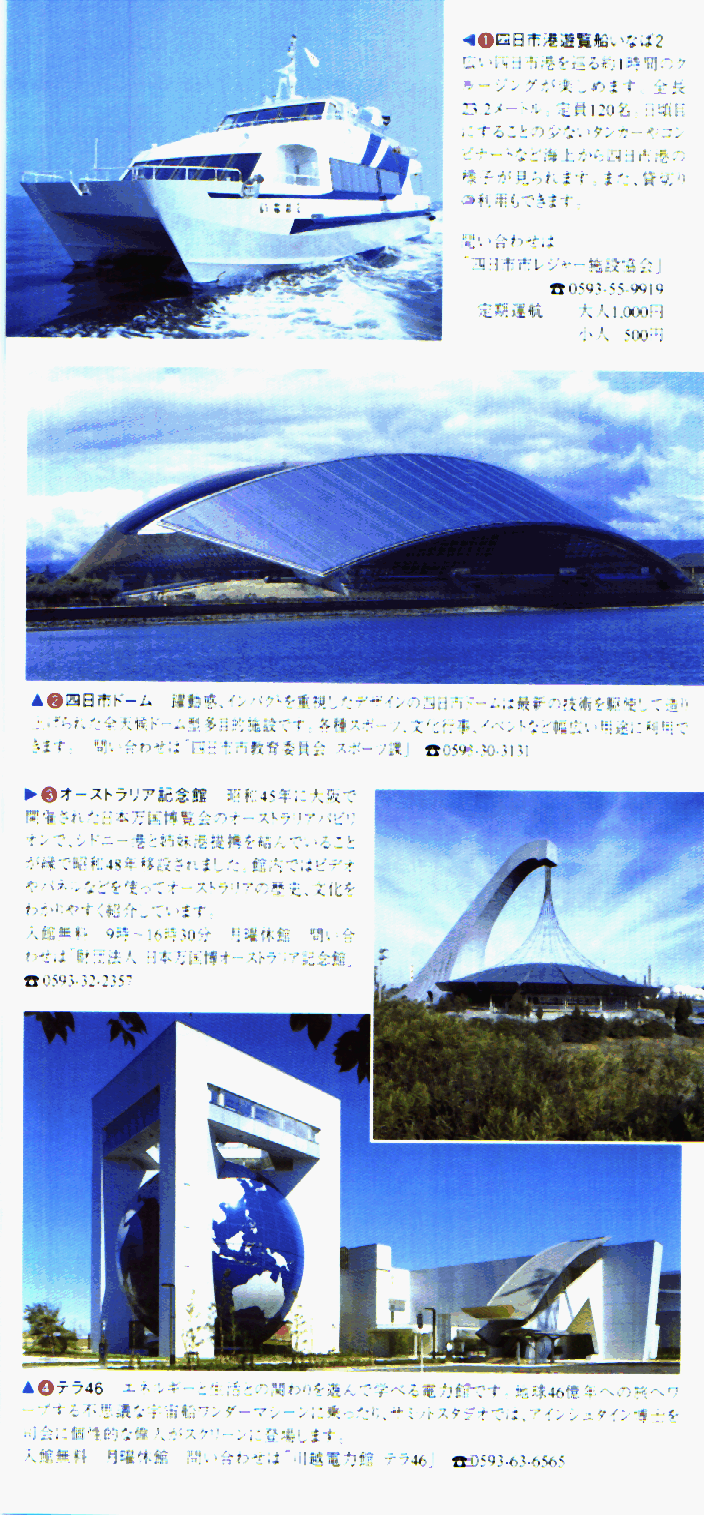
 四日市港周辺の見所
四日市港周辺の見所
四日市港は江戸時代の終わりごろから、伊勢湾のなかで最も大きい港として栄え、船の出入りも盛んでした。しかし、嘉永7(1854)年に2回も起こった地震やその後数回の高潮などで大きな被害を受けました。また、川の氾濫などによって堤防が壊れたため、砂が流れ込んで、港の入り口がしだいに浅くなり、船の出入りにも不便をきたすようになりました。
当時、今の四日市市中納屋町で回船問屋を営んでいた稲葉三右衛門は、この様子をみてたいへん悲しみ、自分の財産をなげうって四日市港を改修する工事を始めました。
(略年表)
明治5年11月13日 三重県庁(当時は四日市町に置かれていた)に「四日市港波止場
建築灯明台再興之御願」提出。
明治6年1月12日 三重県は大蔵省に「四日市港波止場建築伺い」を進達。
明治6年7月18日 県は大蔵省からの回答を両名(出願人である、稲葉三右衛門及び
田中武右衛門)に下達。
明治6年8月 田中武右衛門が資金不足を理由に協力を辞退を申し出る。
明治6年12月 波止場・灯明台の建設と浚渫を除いて、埋立はほぼ完成する。
その後、資金調達の行き詰まりと請負契約先の倒産などの不幸に
より事業が中断される。
明治8年1月 県では延引放置するに忍びず、個人の努力の限界と判断して、県
営にて事業を続行する案を固める。
ようやく完成した埋立地は、同年5月14日、創始者並びにその夫人「たか」にちなみ、県によって稲葉・高砂町と命名されましたが、それまでに私財5万円を投入して造成された埋立地の所有権帰属も、工事の全工程未完了のため処分保留とされて、続行経費の融資を受けようにも担保物件もなく、三右衛門は万策尽きた状態になりました。
その後、人家も50戸ほどが立ち並び、稲葉町には汽船会社の支店も設けられ、汽船の出入りも次第に増えて、波止場の築造はいよいよ急務となりました。三重県が三右衛門の事業を継承しましたが、三右衛門はなんとしても自分の手で初志を貫徹させたいと、同8年8月、自分の出生地である岐阜県高須町に実兄、吉田耕平をたずねて、身元引受人の援助を乞い、資金を調達して再び波止場工事の継続を出願しました。ところが県はこの出願を退け、その上両埋立地の地券および借地料なども全工程が竣工し、精算が終わるまで県庁に保管されることになりました。
三右衛門は悶々の日を送り、生計を立てるにも事欠くようになりました。それでも、再三工事出願を出しましたが入れられず、ついには県を相手取って法廷で争う覚悟を決め、同9年3月、大阪上等裁判所に訴えました。この間も工事は県営で継続されましたが、同12月伊勢暴動が起こり、稲葉、高砂の人家も焼き討ちにあって新開地は焦土と化し、県の工事も中止されてしまいました。裁判所での争いも結局は三右衛門の敗訴となりましたが、それでも彼の意志はくじけず、いよいよ最後の手段として単身上京し、内務大臣に直談判におよびました。内務省も彼の熱意と信念に打たれ、ついに三右衛門による港修築を許可、県もそれまでの出資を放棄し、工事完成後は波止場を公有にするという条件で工事継続を認めました。時に明治14年3月、訴訟提起以来5年、工事中断以来実に7年という受難の時代を経てようやく再起工となったのです。再起工後も資金調達に東奔西走の日々が続きましたが、工事は比較的順調に進み、同17年5月、ついに港修築を完成させ、15年ぶりに宿願を果たしました。ちなみに、この工事に要した費用は当時の金で20万円、三右衛門は私財のことごとくを使い果たし、莫大な負債を残しましたが着工に際して豪語した「いまこの港に10万金を投ずるは、他日四日市に100万金をもたらさんがためだ」の信念どおり、後の四日市に大きな財産を残しました。
三右衛門によって修築された四日市港は、四日市〜東京間の定期航路も多くなり、すでに明治15年には汽船の入港724隻、出港740隻にのぼり、同22年には特別輸出港、同30年には開港外貿易港に指定され、31年4月には指定後初の直輸出船伊勢丸がセメントを積んで仁川(韓国)へ出港、同5月には牛壮(旧満州)からの直輸入船住吉丸が大豆、豆粕を積んで入港(最初の外国貿易)するなど、外国貿易も活発化し、32年8月正式に開港場に指定されました。こうして四日市港は、満韓諸港やアメリカ航路など外航船の出入が相次ぎ、同41年には162隻にのぼりました。
このような港勢の進展にともない、三右衛門が築造した旧港だけでは船舶の入港に応じきれず、かねてから新港開さくの計画がしばしば取り上げられたが、多額の経費を要するため容易に実現しなかった。すなわち明治17年には岩村県令が沖野技師の案により170万円の計画をたて、19年には石井知事が内務省雇水理工師デ・レーケの案により310万円の計画、同33年には小倉知事が内務省原技師案による680万円の計画を策定しましたが、いずれも財政難で着工できませんでした。
こうした情勢の中、四日市市は、明治39年、四日市の将来のため緊急に実現すべき事業として、(1)諏訪前道路改修、(2)阿瀬知川開さく、(3)堀川しゅんせつ、(4)海面しゅんせつと埋立を四大事業として取り上げ、新港建設の足掛かりとして、43年3月、現在の尾上町に当たる地域の海面や原野の埋立を完成しました。
また、また、この埋立事業と並行して、地元の有志らによって港湾改良会が結成されたり、市会の中に港湾発展調査会が設けられたりして、新港問題と本格的に取り組み、国庫補助による新港建設を国・県に強く働きかけた結果、43年ようやく国庫補助港に指定され、同年7月17日、待望の第1期修築工事起工式が尾上町の埋立地で晴れやかに行われました。
それからも、三重県などが港の整備を進め、今では、国内の船はもちろん、外国の多くの船が利用することのできる国際貿易港になっています。
(いにしえの四日市港データファイル)
明治5年3月28日 三重県庁が津から四日市旧陣屋に移る。
明治6年12月10日 三重県庁、四日市から津に移る。
明治8年11月 郵便汽船三菱会社山中伝四郎支店稲葉町に設立され、東京・
四日市定期航路を開始。
明治17年3月1日 第一国立銀行四日市支店、浜町に創設。
明治22年4月1日 四日市、町制を実施。
明治22年11月10日 四日市大阪税関出張所を高砂町3493番屋敷に設置。
明治28年6月3日 四日市倉庫(株)、北納屋町131番屋敷に設立。
明治42年10月8日 米国領事館代理事務所を設置。
大正7年11月30日 米国領事館代理事務所、東海・北陸7県を管区とする領事館に
昇格。
大正8年4月30日 米国領事館、名古屋へ移転により、四日市事務所閉鎖。
ちなみに、当時の、四日市港と名古屋港の対立関係を「築港視察報告」(東京市政調査会市政専門図書館蔵)に見てみます。これは、大正12年4月、横浜港と同一湾内にある東京港の整備計画調査のため、類似する大阪湾における神戸・大阪港および伊勢湾における四日市・名古屋港を視察した東京市会議員一行の報告書です。
名古屋及四日市港の対立関係
伊勢湾に於ける表記の両港は、東京湾における東京港横浜港の対立関係に頗る類似するを以て、此点に関し特に調査す。名古屋港は、伊勢湾の東北詰めに位置し、木曽川、蟹江川等多数河川其附近に於て湾内に流入するを以て湾頭に於ける土砂の埋没甚だしく、遠浅なることまた東京港附近の比にあらず、故に名古屋市は四日市市に比し、遙かに多数の人口を有し、従って其消費、生産の物貨甚だ大なるに拘らず、外国貨物は勿論大船輸送を要する貨物は凡て四日市港の中継に依らざるべからざるが故、伊勢湾に於て港湾としての四日市港は、前者に比し、一頭地を抜き凡ての点に於て到底名古屋港の競争し能わざるが如き観ありしを以て、〜(略)。
(この後、愛知県等が巨費を名古屋港に投じ、整備を行っていく様子が書かれています。現在の港勢は皆さんがご存じのとおりですが、四日市港が名古屋港を凌駕していた時代があったことは以外と知られていませんので、あえてここに書かせていただきました。)
なお、四日市港について、詳しくは四日市港管理組合のホームページをご覧ください。
