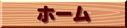現在の四日市市は、四日市市に三重郡と朝明郡(明治29年に三重郡に合併)の町村が
合併をして成立しました。ここでは、その町村(現在の地区)の名前の由来を考えてみます。
(なお、地区の概要は、四日市市制100周年記念誌「大樹育つ百年」から転載させていただ
きました。なお、各地区の面積、人口、世帯数は平成9年3月末日現在です。)
※楠地区は追加していません。お手数ですが別項をご覧ください。
(1) 四日市(よっかいち)
古くは浜村、洲浜ともいう。また、別に、南町、建福寺、北町、竪町の4か所の井戸から良質
の水が湧くことにちなみ泗水の里と呼ぶこともあった。市街西部は東海道沿いに市場町、宿
場町として発展。東部は伊勢湾に面し、三滝川河口に開かれた港を持ち、州浜(四ケ市場)
と呼ばれ、廻船や漁船の集まる港町をなしていた。
地名の由来は、この地方の交通、物資集積の中心であったことから、定期的に市が開かれ
るようになり、毎月4日を市の初日としたところから名付けられたものであろう。
○ 地区の概要(中部地区)
古くから東海道五十三次の宿場町として栄えてきました。現在でも四日市の中核をなして
います。交通網、商業施設、企業オフィスなども集積し、三重県内でも有数の繁華街を形
成しています。
鎌倉時代末期、赤堀氏の一族が浜田に築城し、西方にあった東海道往還を城の東に移
しました。ここに北市場・南市場を開いたことから、次第に発展していきました。江戸時代に
なると、一時、大和郡山藩に属していた時期もありましたが、長く幕府直轄領として治められ
ました。
明治維新以降は、めまぐるしく管轄が変わり、1872(明治5)年から翌年まで三重県庁が
四日市の旧陣屋(現在の中部西小学校)に置かれ、1889(明治22)年に市町村制が実施
されると同時に、浜一色村、赤堀村・末永村の一部とともに浜田村が編入して新しい四日
市町が誕生しました。
●面積/6.54㎡ ●人口/24,525人 ●世帯数/10,573世帯
(2) 富洲原(とみすはら)
明治22年に富田一色、天ケ須賀、松原の3か村が合併して成立。地名の由来は、旧村名
から一字ずつとったもの。すなわち、富田一色の「富」、天ケ須賀の「洲(須)」、松原の「原」。
ちなみに、富洲原小学校の校門は3カ所あり、それぞれ旧村に向いている。
また、校章は3つの錨を組み合わせたものであり、同窓会の名称は三錨会という。
○ 地区の概要
けんか祭りや石取祭りなどの有名な伝統行事が行われる富洲原地区は、江戸時代にな
ると戸数も増え、天カ須賀村約180戸、富田一色村約430戸、松原村約30戸であったとい
う記録が残っています。また、人々は漁業のほか廻船業に従事する人が多かったと伝えら
れています。1825年ごろには物資輸送の五十集(いさば)船が、主に伊勢湾内の交易に
活躍していました。三ツの村が合併したのは、1889(明治22)年で、それぞれの村の名前
から1字ずつとって、富須原から富洲原村となり、その後、1923(大正12)年に富洲原町と
なりました。さらに1941(昭和16)年四日市市と合併し、現在に至っています。
●面積/2.04㎡ ●人口/9,344人 ●世帯数/3,174世帯
(3) 富田(とみだ)
地名の由来は、米が多くとれる美田という意味から起こったとも、鳥出(とりで)神社の由緒
から「とんだ」となり「とみだ」に転訛したともいわれる。
○ 地区の概要
漁業を中心とした浜地区、商業を中心とした高地区、農業を中心とした茂福地区。富田
はそれぞれに特色ある表情を持つ三つの地区から成り立っています。その昔には桑名と
四日市の間に位置していることから、「立場(たてば)」あるいは「間の宿(あいのしゅく)」と
呼ばれ、東海道沿いには旅籠、茶店が軒を並べ、茶店では松かさで焼いた焼蛤を売る光
景が見られました。今も勇壮な鯨船神事やどんど祭りなどの伝統行事が脈々と受け継がれ、
桜が咲き乱れる春の十四川沿いは、憩いの場所となっています。1889(明治22)年に東富
田村と茂福村が合併して富田村となりました。その後、1912(大正元)年に富田町となり、
1941(昭和16)年に四日市市と合併し、現在に至っています。
●面積/4.41㎡ ●人口/11.610人 ●世帯数/4,196世帯
(4) 羽津(はづ)
地名の由来は杖部から羽津に転訛したとも、地の先端、はずれから生じたともいう。古来か
ら交通の要衝として栄えた地で史跡も多い。
○ 地区の概要
四日市で唯一の前方後円墳がある羽津地区の歴史は古く、弥生時代、現在の地区の辺
りは、数十戸の小集落が点在していました。その後、今からおよそ500年前の室町時代に
羽津城の城下町として栄えました。江戸時代後期には桑名藩領と忍藩領に分かれていまし
たが、1889(明治22)年に羽津、吉沢・八幡(現在の八田)、別名、鵤(いかるが)の五つの
村が合併し、羽津村となりました。その後、1941(昭和16)年に四日市市と合併しました。
地区内には霞ヶ浦緑地や競輪場、第3コンビナートなどがあります。特に、美しく整備され
た霞ヶ浦緑地や昔懐かしい羽津山緑地(垂坂山)は、地区住民の生活にかけがえのない文
化的遺産であり、潤いあふれる憩いの場となっています。
補足:本文には「近代的港湾施設がある」旨の表記がありますが、ポートビル、コンテナター
ミナルのある四日市港霞ヶ浦南埠頭、現在整備中の北埠頭は富田地区に入ります。
●面積/8.80㎡ ●人口/15,019人 ●世帯数/5,308世帯
(5) 大矢知(おおやち)
地名の由来は、朝明川の流域で最初の大きな谷地を形成することによるという。
○ 地区の概要
大海人皇子(おおあまのみこ、後の天武天皇)にまつわる史跡が見られる大矢知地区は、
豊かな自然や昔ながらの農村風景を多く残した地域です。農業のほかにも、朝明川の伏流
水を利用した酒造りが行われ、明治初期に生産が始められた手延素麺は、「三重の糸」と称
されるほど、地場産業として欠かせないものとなっています。また、大矢知町にある垂坂山観
音寺は、平安時代の高僧である最澄が聖徳太子自作の薬師如来を安置して、堂宇を建立し
たのが始まりであると伝えられています。江戸幕府の成立とともに桑名藩領になり、その後忍
藩領になると、東海道の要地である大矢知村に代官所が置かれました。1889(明治22)年に
大矢知、下之宮、川北、松寺、蒔田、西富田、垂坂の七つの村が合併して大矢知村となり、
1954(昭和29)年四日市市と合併して現在に至っています。
●面積/6.89㎡ ●人口/15,589人 ●世帯数/5,252世帯
(6) 八郷(やさと)
明治22年に、平津村、広永村、山村、伊坂村、千代田村、中村、菅生村、広永新田(大
矢知村のうち山添を含む、後に山分と改称)の8村が合併して成立。地名の由来は、8か村
が合併したことによる。
○ 地区の概要
のどかな田園の風景が広がり、自然に恵まれた八郷。室町時代、萱生城に春日部氏、広永
城に横瀬氏が居城し、この地を支配していましたが、織田信長軍の北伊勢侵攻の際、兵糧攻め
に遭い、降伏落城しています。1889(明治22)年に、萱生、中村、平津、千代田、伊坂、山村、
広永、広永新田(現在の山分町)の八つの村が合併して八郷村となり、1954(昭和29)年に四
日市市と合併しました。
1970(昭和45)年に、住宅団地の造成が始まり、あかつき台ができ、1995(平成7)年には、伊
坂台が誕生しています。地区内には、伊坂ダムと山村ダムの恵まれた自然を生かしたサイクリン
グコースや四日市大学などがあります。
●面積/10.21㎡ ●人口/12,831人 ●世帯数/3,975世帯
(7) 下野(しもの)
朝明郡のうち中世の霜野郷を継承したと考えられる地名の総称。地名の由来は霜野が転
訛したものと考えられる。なお、明治22年に旧6村が合併した際に、大地主であった下田某
と野呂某から一字づつとり下野村としたという説もあるが・・・・・。
○ 地区の概要
条里制が全国的に行われた奈良時代、朝明川流域に敷かれた条里の西端に当たっていた
ようで、大鐘町の南に「五の坪」という地名が残っています。平安時代、下野荘(西大鐘・北山・
中里/現在の朝明町・山城)と東大鐘(現在の大鐘町)、八郷地区の萱生・平津・中村を合わ
せて大金郷と呼ばれていましたが、金づくりに関係があったとの説があります。
1889(明治22)年に、山城、中里、北山、西大鐘、東大鐘、札場新田(現在の札場町)が合
併して下野村となり、1954(昭和29)年に四日市市と合併しました。大正時代には、特産物と
して有名なナシの生産が始まり、昭和30年代後半から40年代前半にかけて、南部の丘陵地
帯にあさけが丘と八千代台の住宅団地が造成されました。
●面積/7.57㎡ ●人口/8,300人 ●世帯数/2,739世帯
(8) 保々(ほぼ)
地名の由来は、平安期以降に成立した国衙内の行政単位である保から出たものと考えら
れる。
○ 地区の概要
保々地区には、縄文時代後期から鎌倉時代に至る複合遺跡である丸岡遺跡があり、古くか
ら人々の生活が営まれていたと思います。その後、弥生・古墳時代に移るにつれて、次第に
集落の形成が進み、西村、市場、中野、小牧の四つの村が生まれました。江戸時代、中野に
住む「天春家」が、朝明・三重から員弁郡にわたる地域の大庄屋として君臨し、天春家で所蔵
されてきた土地、貢租、宗門改などの古文書は、当時を知る貴重な資料として市の文化財と
なっています。1889(明治22)年に四つの村は合併して保々村となり、1957(昭和32)年に四
日市市と合併。さらに、1982(昭和57)年の住宅団地の造成により、新しい町、高見台が生まれ、
現在に至っています。保々工業団地に工場が進出する一方で、菰野町と大安町にまたがる広
大な地域に、県営の北勢中央公園の整備が進められており、完成したテニスコート、芝生広場
などにはたくさんの人が訪れています。
●面積/10.86㎡ ●人口/7,039人 ●世帯数/2,180世帯
(9) 三重(みえ)
地名の由来は、「古事記」に倭建命がこの地に至った時に足が三重に曲がるほど疲れてい
たことにちなむと伝える。
○ 地区の概要
中央に海蔵川が流れ、肥沃な土壌と豊富な水に恵まれた田園地帯として発展してきました。
三重地区には倭建命(やまとたけるのみこと)が足を洗ったといわれる足洗池のほか、数々の
貴重な言い伝えや史跡が残されています。壬申の乱では、大海人皇子(おおあまのみこ/後
の天武天皇)がこの地を通り、兵を休めて一夜を明かしたことから、「御館/みたち」の名が起こ
ったとも伝えられています。また、三重団地内の城山公園は、三日平氏の乱によって落城した
平氏の居城の一部だといわれています。1889(明治22)年に、西坂部、東坂部、山之一色、小
杉、生桑の村が三重村となり、さらに1954(昭和29)年四日市市に合併。その後、坂部団地、
三重団地、大谷台団地など住宅地帯としての開発が進み、大型スーパーや飲食店などが相次
いで進出しています。1993(平成5)年には、山之一色町にハイテク工業団地が操業を開始し、
古い歴史を持つ農村地帯も今や市内屈指の大ベッドタウンとなっています。
●面積/11.83㎡ ●人口/22,661人 ●世帯数/7,764世帯
(10) 県(あがた)
明治22年に合併した際に、当初三重村とする予定であったが、同村名が先に県庁に届け
られていたため、三重県の県をとって名付けたといわれている。
○ 地区の概要
1889(明治22)年に、平尾、江村、赤水、上海老原、下海老原、北野、黒田の七つの村が
合併して県村となり、1954(昭和29)年に四日市市と合併し、現在に至っています。「県村」
という村名は、三重村とする予定でしたが、すでに隣村がその村名を届出済であったことから、
三重県の「県」を村名に用いたと語り伝えられています。北部では、あがたが丘が誕生するなど
住宅団地の造成が進んでいますが、県村のころから土地改良事業などに積極的に取り組み、
稲作はもとよりナシに代表される果樹栽培、施設園芸、養豚など、先進的かつ効率的な農業
経営が行われ、市内の中でも有数の農業産地となっています。
●面積/11.25㎡ ●人口/7,634人 ●世帯数/2,179世帯
(11) 海蔵(かいぞう)
地名の由来は、村内を海蔵川が流れることにちなむ。
○ 地区の概要
海蔵地区にある海蔵川堤の桜は、市内の桜の名所の一つで、桜まつりには、毎春多くの
花見客でにぎわいます。はるか昔、野田、末永、三ツ谷一帯は海または沼地であったと考え
られ、沿岸の住民は海草や魚を捕って暮らしていたと思われます。これら海産物を蓄える横
穴の蔵を「海蔵(あくら)」と呼び、それが今の地名になったといわれています。萬古焼が、四
日市を代表する地場産業となったのは、1853年に末永の大地主、山中忠左衛門がこの地に
窯を開いたのがその始まりです。1889(明治22)年に、東阿倉川、西阿倉川、三ツ谷、野田、
末永の五つの村が合併して海蔵村となり、1930(昭和5)年に四日市市と合併し、現在に至っ
ています。
●面積/3.65㎡ ●人口/11,349人 ●世帯数/3,954世帯
(12) 橋北(きょうほく)
三滝川の北に位置することにちなむ。なお、橋北地区は当初より四日市町(四日市市)
の内。従って、旧村名ではない。
○ 地区の概要
橋北は、天文年間(1532~1554)に末永村の出郷(でごう)として、三滝川と海蔵川とに挟ま
れた海岸部が開発されたことに始まります。浜一色辺りは葦の生える一面の湿地帯だったとい
われていますが、江戸時代に入ると東海道の整備とともに街道筋には人家が建ち並び四日市
宿の助郷として、人馬の提供もこの地域で行われるようになりました。
1889年(明治22)に市町村制が実施されると、四日市が町制を施行、その際に、隣村の浜
田村と赤堀村・末永村の一部とともに、浜一色村が編入され、新しい四日市町が誕生しました。
現在では、四日市を代表する地場産業「萬古焼」の生産地となり、かって海水浴場としてにぎ
わった海岸部は、石油化学コンビナートへと変貌を遂げています。
●面積/2.62㎡ ●人口/7,048人 ●世帯数/2,712世帯
(13) 常磐(ときわ)
地名の由来は、松本山(建正山)にそびえる松の木にちなみ、これが弥栄の瑞祥を示
すとして常磐と名付けられたという。
○ 地区の概要
常磐地区は、四日市の基礎をつくった赤堀氏が最初に城を築いた所であるといわれていま
す。江戸時代になると、津藩、久居藩、長島藩などに分かれていましたが、中には東海道の
43番目の宿場町である四日市宿の助郷に指定された村もありました。
1889年(明治22)に、赤堀、中川原、芝田、伊倉、久保田、大井手、松本の七つの村が合併
し、常盤村となりました。その後、1941年(昭和16)に四日市市と合併。市中心部と隣接している
ことから、東部が市街化され、また、西部では、松本を中心に次々に団地が造成され、青葉町、
ときわといった新しい町を生み出し大ベッドタウン化しています。
●面積/4.89㎡ ●人口/23,420人 ●世帯数/9,186世帯
(14) 川島(かわしま)
地名の由来は、源義経の家来であった当地の伊勢三郎義盛の子孫に河島五郎義晴・
河島宮内大夫永時がおり、その名前にちなむという。
○ 地区の概要
平安時代は伊勢神宮領であったと伝えられています。源平合戦で活躍した伊勢三郎義盛が
居を構えていたといわれ、その死後、家来が祀ったと伝わる三郎塚と、後につくられた墓が現在
も残されています。
江戸時代の川島は亀山藩・長島藩、小生は津藩領となり、その後、川島の長島藩は幕府の
直轄領と忍藩領に、小生は久居藩領へと変わりました。
1889年(明治22)に川島村と小生村が合併して川島村となりました。その後、1954年(昭和
29)四日市市と合併し、現在に至っています。タケノコの生産と茶の栽培が盛んに行われてきまし
たが、昭和40年代の終わりごろから大規模な住宅団地が開発され、三滝台、かわしま園などが
でき、都市化が進んでいます。
●面積/7.89㎡ ●人口/10,391人 ●世帯数/3,193世帯
(15) 神前(かんざき)
地名の由来は式内社神前神社の名にちなむという。
○ 地区の概要
尾平町で永井遺跡、上畑遺跡が発掘され、この調査によると、神前では弥生時代ごろから
稲作が行われ、以後断続的に集落が形成されていたようです。
大化の改新(645年)のころにななると三重郡柴田郷の一部となり、西野(現在の菅原町)、
寺方、高角、曽井、尾平の五つの村がありました。この五つの村が合併して、神前村になったのが
1889年(明治22)。水に恵まれ、米・麦を中心とした農業のほか、副業として、養蚕・畜産を営む
農村でした。1954年(昭和29)に四日市市と合併しました。
1964年(昭和39)、尾平町の丘陵地に宅地が造成され上名ヶ丘が誕生。さらに1977年(昭和52)
には三重団地に隣接して美里ヶ丘団地が開発されましたが、今なお多くの緑を残しています。
●面積/7.40㎡ ●人口/7,445人 ●世帯数/2,300世帯
(16) 桜(さくら)
明治22年に桜村、智積村の2村が合併して成立。桜の地名は南北朝期にはすでに見
られ、室町期には智積御厨のうちに「桜郷」があらわれる。
○ 地区の概要
大化の改新(645年)以降、佐倉、桜一色、智積の三つの村は、三重郡韋田卿に属していたと
いわれています。桜地区には、奈良時代前記に創建されたと伝えられる智積廃寺が発見されて
います。この寺は四日市最古の寺とされ、奈良飛鳥寺のものにつながる様式をもった瓦が出土して
います。
1875年(明治8)に佐倉村と桜一色村が合併して桜村となりました。さらに1889年(明治22)に
桜村と智積村とが合併して桜村に統一、1954年(昭和29)に四日市市と合併しました。豊かな
水に恵まれ、古くから米や麦の生産、そして酒造りが盛んに行われていました。現在では東南部
丘陵の大規模な住宅団地の造成で桜台、桜花台、桜新町が誕生。西南部の丘陵には、四日市
スポーツランドのほか、研究開発機能の拠点として、鈴鹿山麓リサーチパークがあります。また、
地区内を流れる智積養水は1985年(昭和60)に環境庁選定の名水百選に選ばれるほどの
きれいな水をたたえています。
●面積/12.02㎡ ●人口/16,763人 ●世帯数/5,020世帯
(17) 水沢(すいざわ)
かっては「杉沢の荘」のちに「川上杉村」と呼ばれており、地名の由来は、この「すぎさ
わ」が転訛したものとも、住民の水に対する願望の現れとも考えられる。なお、一説に
は、古来この地方で水銀が産出し、その「すいぎんざわ」が転訛したものともいわれる。
○ 地区の概要
鎌ヶ岳、雲母(きらら)峰のふもと、内部川上流の扇状地に広がる水沢は、古来「杉沢の荘」
「川上杉村」と呼ばれてきましたが、室町時代になると「水沢村」と呼ばれるようになりました。
この地域は古くから茶の栽培が盛んでしたが、その起こりは平安時代、地元の僧侶が唐伝来
の茶の木を植えて栽培したのが始まりとされています。
1889年(明治22)の市町村制で水沢村となり、1957年(昭和32)に四日市市と合併、同時に
従来から深い関係にあった野田地区が鈴鹿郡三鈴村から分かれて水沢に編入し、現在に至って
います。鈴鹿の峰からの清流が美しい宮妻峡、紅葉で名高いもみじ谷など多くの観光客に
親しまれています。
●面積/19.63㎡ ●人口/3,781人 ●世帯数/1,021世帯
(18) 日永(ひなが)
古くは平安期の民有年解案(承徳4年)に良田郷内4条13里の里名として、日長里の
名がみられる。また、保延元年の寛御厨検田馬上帳にもみられる。なお、日永の名は
鎌倉期からみられる。
○ 地区の概要
江戸時代に、東海道と伊勢神宮へ通じる参宮街道の分岐点として、また四日市宿と石薬師の
「間の宿(あいのしゅく)」として、追分は大名行列や参宮客でにぎわいました。この追分には、
今も伊勢神宮の二の鳥居である「追分の鳥居」があります。
1891年(明治24)に、日永、泊、六呂見の三つの村が合併し日永村となりました。その後、
1941年(昭和16)に四日市市と合併、東に隣接する塩浜地区とともに、わが国屈指の石油化学
コンビナートが形成されています。また、国道1号、国道23号、そして近鉄線、JR線といった
主要交通網が整い、急速に都市化が進みました。その一方で、中央緑地や泊山丘陵地帯に
南部丘陵公園があり、つんつく踊り、輪くぐり神事といった伝統行事も今なお続けられています。
●面積/7.23㎡ ●人口/16,275人 ●世帯数/6,339世帯
(19) 四郷(よごう)
明治22年に、東日野、西日野、室山、八王子の4か村が合併して成立したことにちなむ。
○ 地区の概要
東日野、西日野、室山、八王子の四つの村は、四郷谷あるいは日野谷と呼ばれていたと
いわれています。南北朝時代には北畠氏が領主となり、長くこの地を統治していました。
1889年(明治22)の市町村制の実施と同時に、四郷村が誕生し、明治から大正にかけて紡績、
製茶、醸造などが盛んに行われました。また、三重鉄道が四日市-八王子間に鉄道を敷設する
など、四日市の近代化の先駆けとなった地区でもあります。
1943年(昭和18)に四日市市と合併し、高花平、笹川といった大規模な住宅団地の開発により、
現在では市最大の人口を抱える地区となっています。明治期からの急激な産業の発展は、
今も当時の面影をわずかに見ることができ、美しい緑とともに調和のとれた町並みが残っています。
●面積/8.40㎡ ●人口/25,740人 ●世帯数/9,165世帯
(20) 塩浜(しおはま)
地名の由来は、古くから製塩が行われていたことにちなむ。製塩は近世初期まで栄え
ていたようである。
○ 地区の概要
塩浜地区では平安時代のころから伊勢神宮の「御薗」として塩づくりが行われていたという
記録があります。
室町時代から戦国時代にかけて、ここ塩浜も戦乱の舞台となりました。中でも工藤氏が浜田
攻略を企てた「塩浜の合戦」(1559年)があったことが伝えられています。
江戸時代になると荒れ地を開いて人が住むようになり、後に参宮下街道と呼ばれる道沿い
には村ができました。
1889年(明治22)に、塩浜、馳出、旭の三つの村が合併して塩浜村となり、1930年(昭和5)
に四日市市と合併。昭和の始めごろまでは農漁業を営む村落でした。昭和30年代、急速に工業化への
道をたどり、わが国屈指の石油化学コンビナートを形成するに至りました。昭和40年代の公害問題も
現在ではかなり改善され、新しい住宅地の造成も行われています。
●面積/7.44㎡ ●人口/7,897人 ●世帯数/3,026世帯
(21) 内部(うつべ)
地名は内部川に由来する。
○ 地区の概要
内部川下流の台地に5世紀ごろの八幡塚古墳が発見されており、この地域は古くから村落が
あったものと思われます。中世、采女・波木・貝塚・北小松は後藤氏、小古曽は北畠氏の所領で、
小山田地区辺りまで勢力が及んでいたといわれています。江戸時代にかけては細かく分かれて
統治されてきました。
1889年(明治22)に、采女、小古曽、貝塚、波木、北小松の五つの村が合併して内部村となり、
1943年(昭和18)四日市市と合併しました。1957年(昭和32)、鈴鹿郡三鈴村であった南小松村
が分村して編入され、現在の姿となりました。采女町には有名な杖衝坂があり、貝塚町は四日市を
代表するトマトや野菜の生産地として知られています。田園が広がる地域ですが、交通網が整って
いることから、四日市南部のベッドタウンとして発展しています。1994年(平成6)には采女町の
丘陵地で区画整理が行われ、新しく采女が丘が誕生しました。
●面積/12.31㎡ ●人口/15,331人 ●世帯数/5,120世帯
(22) 小山田(おやまだ)
地名は、旧村の小山の「小」と山田を合わせたものといわれる。
○ 地区の概要
堂ヶ山町の樹齢800余年の大樟、縄文時代早期の一色山遺跡、足見川と鎌谷川に挟まれた
台地で確認された7世紀ころの円墳3基など、小山田地区には長い歴史を物語る貴重なものが
残っています。
江戸時代の記録を見ると、山田では油かすや干鰯を肥料に用い、粟、稗、小豆、大根、春麦、
小麦、茶などを栽培していたようです。また、内部川の川床より土地が低い六名には、水害に
見舞われた記録が残っています。1889年(明治22)に、山田、小山、六名、堂ヶ山が合併して、
小山田村となりました。その後、1954年(昭和29)に四日市市と合併し、1957年(昭和32)に
鈴鹿郡三鈴村に属していた鹿間、和無田が分村して編入され、現在の姿となりました。
内部川、鎌谷川、足見川、天白川がながれる起伏に富んだ丘陵地には、田畑が広がり、
その地形を生かした茶の栽培が盛んです。
●面積/18.35㎡ ●人口/5,738人 ●世帯数/1,931世帯
(23) 河原田(かわらだ)
地名の由来は、内部川沿岸に田が広がることにちなむといわれる。
○ 地区の概要
河原田地区は、平安時代には伊勢神宮領となっていました。南北朝時代には有田氏が
河後(川尻)城を築き、織田信長の北伊勢進攻まで、長くこの地を統治していました。
江戸時代から明治に至るまで、大治田村、内堀村、南川尻村は幕府直轄領に、
今宿村(現在の南河原田)、貝塚村は津藩、川原田村は久居藩、北川尻村は桑名藩の管轄と
なりました。古来から内部川、鈴鹿川の水害に苦しめられていたようで、1659年の大洪水では、
川尻、川原田、貝塚、内堀の各村が大きな被害を受け、村のあった場所を移したと伝えられています。
明治維新後、五つとなっていた村は1889年(明治22)に合併し河原田村となりました。その後、
1954年(昭和29)に四日市市と合併し、現在に至っています。
河原田山丘陵地の斜面は、明治の末ごろからミカンの栽培が行われ、特産物の一つになっています。
地域には南北に走る国道23号などがあり、こうした交通の便から1979年(昭和54)には北勢公設
地方卸売市場が開設されました。食品卸団地の形成や関連する流通施設も立地しています。
●面積/5.12㎡ ●人口/4,438人 ●世帯数/1,438世帯
四日市市の最新の統計(人口等)はこちらです。(四日市市ホームページ)
ところで皆さん、「三重県」という名前は四日市(正確にいうと三重郡なのですが)に由来し
てるって知ってました?県名は、県庁所在地の地名に由来することが多いのですが、三重県
の県庁は津市にあるのに、なぜ?それは、三重県の県庁が一時期四日市にあったからなの
です。その頃の県の変遷を年表でみますと、
明治4年7月 廃藩置県が行われる。三重県では、旧藩を中心に12の県が置
かれる。
明治4年11月22日 三重県では、北勢、中勢北部、伊賀地方が安濃津県となり、中勢
南部、南勢、東紀州が度会県となる。県庁は、安濃津県が安濃郡の
津に、度会県は度会郡の山田に置かれる。
明治5年3月17日 安濃津県の県庁が三重郡の四日市に移転し、県名も三重郡の地
名をとって三重県に変更される。
明治6年12月 県庁を再び安濃郡の津に戻す。(県名は三重県のまま。)
理由は、県庁として利用していた旧四日市代官所の建物が狭い、四日市では
位置が北に偏りすぎているなどいろいろといわれていますが、実際には、維新後
も影響力を持っていた旧藤堂藩の影響力を弱めるために、丹羽参事(今の都道府
県知事)が四日市に移したのが正解でしょう。翌年、津に戻ったのは旧藤堂藩士
の政治力がまだまだ強かったことの証でしょうか。
話がそれましたが、もし丹羽参事がいなかったら、県庁は津のまま。従って、県
名は今でも「安濃津県」だった可能性が高いのですが、この名前皆さんはどう思
われます?私は・・・ちょっと・・・。 安濃津県四日市市??
明治9年4月18日 三重県と度会県が合併、今の三重県が誕生する。