過去の過ち
住民の戦い
1960年(昭和35) 塩浜地区連合自治会「工場地帯からの騒音とガスで、夜もおちおち寝ておられない」と、市に陳情。
1961年(昭和36) 地区住民を対象に実施したアンケート調査の結果を発表。結論として、 1.工場誘致は、必ずしも市の発展にならない。2.公害防止策の早急な制定を。 3.公害による人体影響は老人と子どもに特に著しい
1963年(昭和38)
自治会費で塩浜病院の無料検診をはじめる。県・市はこの状態を捨て置くことができず、地区全般の一斉検診をもってその結果を重視し、処置をとることの話し合いが実現。
1964年(昭和39) 記者会見で、「ぜんそく患者の治療費自己負担分は市費で支払う認定制度を発足させる。」と発表。
1965年(昭和40) 「四日市市公害関係医療審査会」が正式に設立。会長には、推進役だった二宮医師会長が選出。
1965年(昭和40) 第1回の審査会が5月に開かれ、申請のあった18人全員が認定された。 18人のうち12人は磯津の人で、すでに塩浜病院へ入院している人たちであった。病名は、肺気腫10人、気管支ぜんそく5人、慢性気管支炎3人で、入院を要するとされるのは14人であった。うち子供は2人。
市独自のこの認定制度は5年後の1970年(昭和45)2月から国が施行することになった『公害に係る健康被害の救済に関する特別処置法』の制度に引き継がれていった。
引き継がれるまでの5年間の間に認定された患者数は717人にのぼっていた。
「四日市公害訴訟」 野呂 汎(名古屋弁護士会)
四日市公害裁判の流れ
四日市再生「公害市民塾」のご協力をいただきました。
四日市ぜんそく公害
コンビナート(企業集団)というロシヤ語が、四日市市民の日常語として使われるようになった1965〜6年ころから、磯津で水揚げされる魚は【くさい魚】として買い手もつかないありさまに加え、人間も変な咳をしたり、ぜいぜい発作が起こるなどの病気に見舞われる人の数が増え始めた。
磯津の開業医、中山医師は、「ぜんそくではないぜんそく様疾患」に「塩浜ぜんそく」と名づけ、発作止めの注射を打つなどにおわれるようになった。
百万ドルの夜景と謳いあげる石油化学コンビナートの繁栄の影で、なにも悪いことをしていない住民たちが、コンビナートと言う外来語の次に、「公害」というこれまた新たな言葉で表現される苦しみにあわされていった。
風評被害
エビ、カニ、スズキなど、うまい魚、高級魚がとれることで知られる伊勢湾。その伊勢湾で、油くさい魚がとれはじめ、犬や鶏さえも見向きもしないといわれるほどになった。四日市港を中心にした海域での魚は、とってきても放棄したり、値引きされたり、あるいは出漁を見合すなど、三重県の漁民がうけた年間被害は、1960年(昭和35)以降、8千万円にのぼると県は推定している。
三重県の対応
三重県が策定した「四日市地域にかかる公害防止計画」(1970年〔昭和45〕11月)のなかで、漁業について次のように記している。
当地域の沿岸漁業は、カタクチイワシ、イカナゴなどを対象とした機船、船びき網漁業と、エビ、カレイ、貝類を対象とした小型機船、底びき網漁業が主要なものである。が、この海域は、1953年(昭和28)頃から、工場廃水に起因すると思われる異臭魚が出現し始め、1959年(昭和34)頃からさらに顕著となり、沖合い北東11キロメートル、沖合い東南7キロメートル、沿岸南方15キロメートルの範囲に分布しているものとみられる。
漁業価値の低下が進行するとともに、港湾施設の拡張、臨海工業用地の造成がこれに拍車をかける形となり、漁業者数、漁獲量とともに減少しつつある。 ・・・・・・・・・・・このまま漁場環境の悪化が進行するかぎり、漁業者の生活維持が困難となる恐れがあるので、水質の改善が当面の急務となっている。
くさい魚についての詳細はここでは触れないが、少しだけ付け加えておきたい。工場の排水を何とかしてほしいと再三、企業に頼んでも聞き入れない。こうなれば、停めるしかないと、磯津の漁師は、土のうと廃船を用意、1963年(昭和38)6月、三重火力発電所の排水口を実力封鎖するという≪漁民一揆≫をおこした。 そうした騒ぎがあってはじめて知事が現地へきて、くさい魚の試食会をやったが、結局、排水口はそのまま、僅かな見舞い金で片付けられてしまった。
工場のどぶ溜め
1968年(昭和43)、四日市海上保安部に、田尻宗昭警備救難課長という、『海の男』が着任した。「こんなのは海ではない。工場のどぶ溜めだ。」と、たれ流しの摘発を行った。それで、企業も行政も、排水対策に努めるようになり、以前よりはきれいになった。とはいえ、海底は死んだままの状態であり、漁業は衰退をたどっている。
誤った考え
漁業などの一次産業は滅びるもの、工業こそが栄えるもの、富をもたらすものという考え方や政策が、偽政者の中に根強くあることも否定できない以上、漁師にとっての明日は暗い。
磯津は、四日市でも、ここだけは陸続きではなく、鈴鹿川で切り離され、四日市の南東に位置している。1キロ四方にも満たない狭い地域に、680世帯、2700人が、家々の軒をつらね、体を寄せ合うようにして生活している。先祖代代、漁業を中心に生計を営む漁師町(組合人450人)である。
『磯津』という地名は戸籍にはなく、四日市市大字塩浜何番地が正式な地番であるが、四日市公害は、海も空も、ここから発した激甚地であり、四日市公害の原点である。
磯津は、第一コンビナートと鈴鹿川を挟んで隣接している。当初は、中部電力三重火力発電所の煙突でさえ、70メートルもない低いものであった。また、昭和四日市石油なども低い煙突であり、プラントから吐き出されるガスも、特に冬季は、コンビナートの風下になるという季節風でもろに流れ込んでいた。そして、亜硫酸ガス濃度はしばしば1ppm以上に達し、2.5ppmになったことさえある。許容量0.1ppm(日本公衆衛生協会)からいえば、殺人的ともいえる高濃度汚染である。
その磯津で、1960年(昭和35)以降、急速にぜんそく患者が出始めた。1964年(昭和39)までに約3%、40歳以上で約7%、50歳以上で10%という高い発生率となった。通常のいわゆる古典的ぜんそく患者の発生率は1%以下であると言われていることからいくと、まさに異常な状態である。
磯津の人たちは、亜硫酸ガスもppmも知らないが、同時刻頃に、ぜんそくもちでない家の人たちが、ゼイゼイ、ヒューヒュー、のどがおかしい、発作が止まらんと訴えることから、これは工場のせいとしか考えられんと体で知った。
亜硫酸ガスは、重油に含まれる硫黄が燃えて発生する有毒なガスである。1965年(昭和40)頃、四日市市で排出される量は、1日430トン、年間13万トンと推定された。これは、約2000個の浅間山の噴煙中にふくまれている亜硫酸ガスの量に匹敵する。しかも、南北約6キロ、東西約5キロメートルの狭い地域に排出源が集中し、排出されたガスも、その狭い地域に到達する以上、被害をこおむるのは明らかなことである。 さらに、ここで使われる原油をスマトラやソ連産の0.1から0.5%のものに切り替えれば、10分の1程度に減少することはわかっていても、アメリカ資本と技術提携していることや、硫黄分の多い中近東産のほうが安価ということで、経済優先がまかり通ってきている。
現在の状況
四日市の公害認定患者は多いときで1140名を数え、現在でも600名ほど居り、認定制度がなくなったとはいえ、同じ症状のぜんそく患者の発生もあり、公害「克服」「終結」などと言ってすます状況にはなっていない。

住宅地に隣接するコンビナート地帯

家屋から眺めた煙突からのスモック

死亡した公害患者の追悼市民集会

原原告患者側の記者会見
公害患者が増える一方なのに、患者救済や公害発生源対策が進まず、おまけに、新たな公害発生源となる第3コンビナート誘致のため、霞ヶ浦の埋め立てを市議会が決めるなど、開発優先の政策が推し進められた。
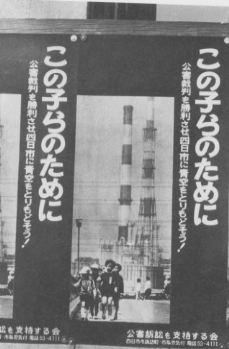
憲法第25条の「生存権」が脅かされる状況の中、1967年(昭和42)9月、磯津地区に住み、県立塩浜病院に入院中の公害患者9名が、隣接する第1コンビナート6社を相手どっての公害訴訟(裁判)を提起、津地方裁判所四日市支部で審理が行われ、5年目の1972年(昭和47)7月、患者側「勝訴判決」が下されました。

"勝訴”日本公害訴訟の先駆け