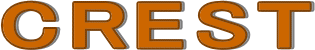
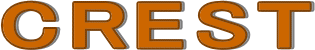
日本の家紋には、千年の歴史があり、基本的なもので200種類もあり、その変形を含めると10,000種類以上にものぼります。
平安時代、公卿(貴族)の間で牛車や衣服に好みの文様を用い自家を誇示した。後鳥羽上皇は、菊紋を用い、後にこれが皇室のしるしとなりました。
武士は、戦場でそれぞれの旗やのぼり、陣幕、馬印などに紋章を付け、敵、味方を明確にしました。
江戸時代後期に急速に普及し、大衆化された家紋は、「紋どころ」と呼ばれ親しまれ、その模様はさまざまに変化し、現代へと受け継がれています。
| 家紋の由来 | 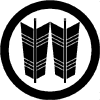 |
| 矢紋 | 並び矢 |
| 弓矢の歴史は古く、狩猟や戦場の武器として利用されてきた。「弓取り」は武士を意味し、神事の破魔矢・流鏑馬などに弓矢が使用されている。 弓紋は弓削(ゆげ)氏や平岩氏のほか、そう多くはない。矢紋のほうは、矢羽といって羽の部分だけを表した、紋と矢尻といって矢の先の部分を表した紋と、矢筈(やはず)といって矢の弦につがえる部分だけを描いた紋とがある。この中で、矢尻紋は比 較的少ない。 この矢紋を広めたのは服部である。服部は伊賀国阿拝郡服部郷が名字の発祥地である。服部の文字からもわかるようにもともとは服を織る工人の職業集団であった。六条天皇のとき、弓の大会で天皇の命により矢一千本を奉納したとあり、服部の矢紋はこれを記念したものと伝えられる。 |
|
| 服 部 | |
| 古代、職業部の機織部門を担った機織部の服部(hatoribe)に由来する姓氏。「ハタオリ」「ハトリベ」から「ハトリ」そして「ハットリ」と呼ぶようになった。 | |