
茨川エピソード
赤ひげ先生奮戦記
現北勢町中山に開業していた民上俊平医師(明治23年生まれ)はたびたび茨川へ往診に行っていた。林道の開通するはるか以前の話である。小児は村の人がセタ(背負子)に背負って連れて来たが、動かせない患者は民上先生が往診に出向いた。病気としては結核、関節炎、栄養不良などが多かった由。
新町口まで自転車で行き、あとは当然徒歩である。川を渡渉し、マムシやヒルに悩まされながらの山越えである。日没後に暗くて川で転倒したこともあるという大変な仕事だ。冬季は1mを越える積雪の山道をかんじきを履いての往診だった。一度深夜の難産に村から迎えが来て、月明かりに輝く樹氷に見とれながらの往診もあったと言う。また、川向こうの家へ渡るときに転倒して怪我をしたこともあった。
この先生は驚くなかれ、さらにノタノ坂を越え君ヶ畑までも往診に出向いた。往診のお礼は茨川で50円、君ヶ畑で100円であったという。当時の物価は安かったとはいえ、やはり尊い奉仕の精神がなければ出来ないことである。以上は「員弁郡医師会百年史」から拾った話である。この本から民上先生の登場する項目を辿っていくと、人力車で時山へ往診に行く話など興味は尽きない。
久保田孝夫氏の訪問
昭和28-35年頃、愛知厚顔こと久保田氏が茨川を訪問されたそうです。そのときの思い出として「 区長さんの家には奇麗な娘さんがいて、岳友が淡い想いを抱いたのですが…。」ということだったので興味を持った私がその区長さんのお名前を尋ねました。
「筒井さんということしか覚えていません。彼女も間もなく家を出て都会へ就職したようで、顔も忘れましたが、佐々木先生の調査に娘さんが一人トランジスタラジオを聞いて針仕事していた、の家のような気がするのですが、それも先生の調査は昭和37年ごろで、私たちの行った年代はそれより前なので、同じ娘さんかよくわかりません。」
当時区長は輪番制だったようで、どのお家のことか不明。
筒井しんさんの墓標
熊谷栄三郎の著書で紹介された、筒井しんさんの墓標が茨川の共同墓地にひっそりと立っていた。
「筒井しん 行年八十三歳 昭和五十二年七月二十七日亡」
注目されるのは茨川が廃村になって12年もたってから、この地に葬られたことである。しんさんは蛭谷生まれで、正吉さんの兄弟である円次郎さんに嫁いできた。ところが円次郎さんは42歳で亡くなられて、その後しんさんは女手一つで3人の子供さんを育てられたということである。
利明さんによれば、「炭焼きでも、薪作りでも男並にやられた。暗いうちに山に出て、働いているうちに夜が明けたという人です。たいへんな女性です。だからこそ、離村してからも茨川が恋しくて仕方が無かったのでしょう」
しんさん一家は廃村2年前に離村して息子さんと桑名へ住んだが、茨川が恋しくて「ちょっと行ってくる」と言っては何日も廃村に寝泊りされたということである。心底山暮らしが好きな女性であった。
桑名で亡くなったしんさんの遺骨は、望みどおり円次郎さんの眠る茨川に埋められた。遺骨は息子さん達に、墓標や蓮の花と共に抱かれて長い治田峠道を越えたのであった。
狛犬(こまいぬ)
茨川にある天照神社の狛犬は大正13年筒井円次郎さんと小椋安次郎さんが寄進したものである三重県で作ったものを筒井利明さんが治田越えで背負ってきたと熊谷氏の本に書かれている。重量は60貫というから、230KG程である。とても人間業とは思えない。台座は別として狛犬の背は60cm位で、60貫もあるとは思えない。多分一対の重量であって、115KGのものを二回運んだのかもしれない。利明さんが17歳のときである。
新田次郎の小説に白馬岳に石で出来た方向表示板を担ぎ上げる話がある。誰も持てないので富士山一の強力に白羽の矢が立った。1956年直木賞を受賞した「強力伝」である。その大きい方の石は50貫近くとある。60貫というのが途方も無いものであることが分かるだろう。利明さんが嘘をつく人だとは思えないので、多分115KG×2ということだろう。それでも並外れた力持ちである。この神社は天保13年(1842)に移設されたと言う。
蓮華寺
蛇谷銀山が盛況であった頃、出合の下流に蓮華寺と言う立派なお寺があったと言う話がある。屋根の上には燦然と輝く金の鶏があり、このあたりにも集落があり上茶屋と呼ばれた。鉱山が衰退して寺が無くなった後も、元旦の暁に鶏の鳴き声が聞こえたという。何処まで本当の話かは不明だが、今に残る伝承である。
運動会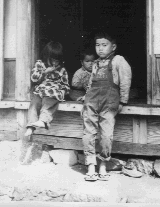
筒井正さんの通った茨川分校は生徒も少なく広い校庭も無いので、13kmの山道を歩いて政所本校の運動会に参加したということである。その夜は蛭谷の親戚に泊めてもらい、翌朝また長い山道を歩いて帰った。賞品に鉛筆をもらった。正さんは一泊二日の運動会が今でも、脳裏にやきついていると書かれている。
ちなみに正さんと私は同い年で、自分の子供時代を思い出して、茨川ではそういうことが行われていたのかと思うと感慨深いものがある。
イワナ釣り
正さんはイワナ釣りが趣味だと書かれている。私も渓流釣りから素石を知り、茨川を知ることになったのだが、結果的に素石が紹介したことで茶屋川は釣り荒れた。それは素石自身分かっており、著書の中で釣りのガイドを書くことのジレンマに触れている。
それはともかく人の住んでいたころの茨川のイワナは型、数ともに豊富だったらしい。林道がついてからは型が小さくなってしまった。釣り荒れもあるが、山の木を切り過ぎたことも一因である。川床が埋まれば渓魚も生きていけない。山に住む人は釣りのような効率の悪いことはあまりやらない。短時間で沢山捕る方法がある(毒流しのような卑劣なものではない)。ただし食べる分しか捕らない。その方法は私も知っているが、魚族保護のためここでは触れない。
林道
茶屋川沿いに林道が完成したのは昭和29年となっている。これは役場の台帳の話で、その2年位前から通ることができたらしい。延長10.5km、幅員3.6mの立派な道路だ。
林道が出来て便利になったことが皮肉にも村人の離村を早めてしまった。車が入ることにより機械化の波が押し寄せ、原木のまま積み出すことにより現場の仕事が無くなった。輸送力が桁違いにアップして、木炭より割木で出荷した方が早くお金になるので木を切りまくった。ついに山は丸裸で売るものが無くなった。
人が背負って出荷しているのが茨川の生活サイクルに合っていたのだ。都会のスピードが茨川の財産をあっという間に持ち去ってしまった。木が再生する前に食いつぶしてしまったのである。
この後林道は用事が無くなって荒れていき、橋は朽ち落ちた。再び整備されたのは廃村後である。各橋の竣工年月を見ると、入り口八風橋S53年3月、中間銚子橋S56年12月、終点小風谷橋S63年12月となっている。10年前のTV放送では再び大雨の崖崩れで通れなくなっていた。現在は未舗装ながら、四駆でなくても通ることが出来る。
紀行、エッセイ
茨川について書かれた文はいろいろある。そのなかで今回の研究のきっかけとなった中西光三氏「一匹のさまよい」の中にある「望郷の石門--茨川」は謎に満ちている。調べるほどに内容に矛盾が出てくる。読んでない人が殆どと思うので具体例は一々出さないが、一つだけ指摘しておく。
タイトルとなった石門とは青川のトンネルであるが、「茨川の廃屋がすべて朽ち果てても住民の執念が残したレリーフとして、この石門は永久に残るだろう」という意味の事を書いておられる。残念ながらそうではなく、前述のようにこのトンネルは鉱石を運ぶために五代財閥が掘らせたものである。私は本に書いてあった住所に問い合わせの手紙を出したが、宛先不明で帰ってきた。やっぱり謎の人である。まあ、しかし脚色承知なら非常に面白い本ではある。
筒井みつえさんにコピーをお見せしたところ「作家の人は話を面白おかしく書きます」と言われた。動物との交流についてもそんなことはあり得ないと。ある雑誌には言いもしないのに、筒井順慶十七代当主と紹介されたそうだ。
三筋会
筒井みつえさんに「今でも茨川出身者の親睦会のようなものがあるのでしょうか」とお尋ねした。
お話によれば、ご当家と、筒井勉さん、筒井実さん、石井正之さん(一正先生の子息)らで、茶屋川上流にある三筋の滝にちなんで「三筋会」というものを作っているということ。3年程前神社の新しい鳥居を寄進された由。元住民の方々は離れ離れになっているので、皆さん集まることは難しいというお話だった。
焼野のツチノコ
山本素石の本に面白い話がある。茨川林道の中ほどに杠葉尾の池田四郎という人が小屋がけをしていた。植林に携わりながら、イワナの放流にも熱心だった人である。ツチノコの話は池田さんが語ったものである。
昭和36年の秋、焼野の萱場にある炭焼窯のあるじが窯を開けると黒光りをする変な生き物がいた。目が暗闇に慣れて、よく見るとグロテスクな蛇のような怪物が金色の目でこちらを睨んでいた。驚いた窯主は暫く足の震えが止まらなかったそうだ。慌てて蓋を閉めて閉じ込めておいて、山道を駆け下り、里人に急報した。
池田さんは近所の人と共に自転車で駆けつけた。怖いもの見たさで集まった人々だが、誰も手出しは出来なかった。協議のあげく近江八幡から本職の蛇捕りを呼び、見事生け捕りと相成った。太さは太ももほどあったと言う。名古屋方面から、高額で買い取りたいと言う人が現れ、引き取られていった。ところが、ツチノコは野生の誇り高く、人間が与えた餌を食わず餓死したと言うことである。
素石は窯主だった員弁郡大安町の藤原さんを訪ねたが、家族ぐるみで引っ越した後だった。引越し先は誰も分からない。買った人も名古屋の誰かは分からない。関係者はすべて故人となり、事の真偽は定かではない。