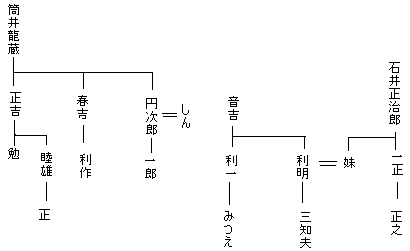
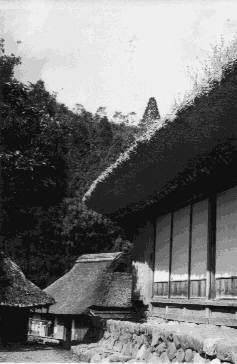
人物紹介
☆系図
聞き取り調査の結果、今回関係のある人の系図を描いて見る。
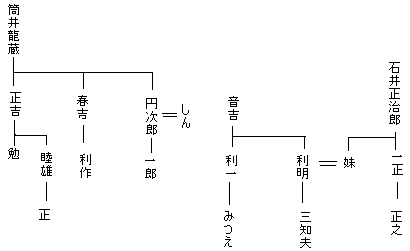
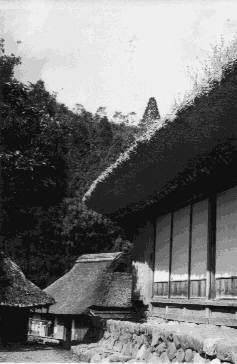
代々筒井龍蔵を名乗ってきた茨川草分けの本家は一番左のラインである。さいごの龍蔵さんは天保13年生まれ、正吉さんは明治28年、正さんは昭和31年生まれである。
石井正治郎さん(政次郎と書かれたものもあり。明治14年生まれ)は明治38年、三重県の石榑から入植された。子息の一正さんは分校の先生を昭和4年から36年間務められた。他から来た先生では、隔絶された山村の生活に耐えられなかったからである。一正さんは4年くらい前に 亡くなられたそうだ。
今回お話を伺ったのは、筒井正さん(愛知県の高校の先生)、みつえさん(昭和9年生まれ)、三知夫さんである。みつえさんと正さんも、同じ筒井の父祖の代の親戚であるし、それぞれの方の兄弟ももっとあるが、複雑になるので簡略化した。
三知夫さん一家は昭和28年頃離村されたので5歳位まで、正さんは昭和40年離村で9歳まで、みつえさんは昭和28年頃離村ではたち位まで茨川で暮らされた。
山本素石の「廃村茨川紀行」に登場する雄策さんは利作さんをモデルにしたと思われる。最初みつえさんが、雄策などという人は知らないとおっしゃるので、驚いた。利明さんや三知夫さんは実名で登場するのに、なぜ仮名となったかは、素石が故人となった今は謎である。
円次郎さんの奥さんだった しんさんの墓はレッツドンキホーテや熊谷氏の本に紹介されたが、この話はエピソード編で述べる。
☆茨川を訪れた人々
惟喬親王(844-897) 文徳天皇第一皇子
惟仁親王(後の清和天皇)との皇位継承争いに敗れ各地を流浪。話が古すぎて本当に茨川を訪れたかは不明。しかし永源寺町によれば小椋谷に幽棲し、ろくろを使って膳・盆・椀などを作る仕事を広めた事になっている。 「貞観元年(859年)に小椋庄に入山され、貞観7年(865年)蛭谷に筒井八幡宮を建立されるなどされたため、工人たちは親王を業祖と崇めるようになりました」ということ。
御池岳の犬返し谷、三筋の滝は親王の連れた犬が登れなかったという話から、鈴鹿山中をかなり歩いたようであるが、作り話の可能性も否定できない。
親王の別荘が交野が原(現大阪府枚方市)にあって、渚の院といった。ここで従者の在原業平が「世の中に 絶えて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし」という有名な歌を詠んだ。これは単に桜を称えた歌ではなく、(皇位継承の)争いがなければ・・・という親王の心境を詠み込んだといわれている。
今西錦司(1902−1992) 文化人類学者 第12代日本山岳会会長 京大卒
「わしは好きなことしかせえへん」。京都西陣織元に生まれ、生涯ガキ大将だった超大物。探検家と学者という二つの顔を持つ。マナスル調査隊長、中国の大興安嶺探検などで知られる一方、ダーウィンの「進化論」に対する「棲み分け理論」を発表。研究の対象はアフリカの部族、ゴリラ、野生の馬、日本ザル、渓流魚、カゲロウなどなど幅広い。
山本素石の渓流釣り集団「ノータリンクラブ」顧問だった。期日ははっきりしないが、人が住んでいた頃の茨川の調査をしている。研究のため員弁川源流で釣りをしたこともある。
山本素石(1919−1988) 日本釣り振興会理事 作家、エッセイスト
滋賀県甲南町生まれ。生涯渓流釣りを愛し、川を愛し、山村を愛した名エッセイスト。最初釣り雑誌に投稿していたが、あまりに文が達者なのでレギュラーとなり、後に本にまとめられた。1964年ツチノコ探査、及び渓流釣り集団「ノータリンクラブ」を旗揚げし、日本中にツチノコブームを巻き起こす。
釣りやツチノコより、山村奇譚、風俗を描いたものは天下一品。ことに茨川を愛し、廃屋に泊まったり、元住民と交流したりしていた。69歳でガンに倒れ、病床で「ここから川が見えるか。川が見たいんや」と言って亡くなった。文明嫌いで、目に余る河川行政に対して国会に意見書を提出したことがある。
筒井三知夫氏は素石と交流があり、今西博士も知っているとのこと。
熊谷栄三郎(1940- ) 京都新聞記者 エッセイスト 京大卒
昭和57年頃茨川を取材し、京都新聞に連載して好評を博す。民俗ものを得意とする。三知夫氏の父君、利明さん(故人)に取材している。この人も渓流釣りが好きで「山釣りのロンド」という著書がある。素石の曾孫弟子を自称する。
佐々木一(1924- ) 菰野町郷土資料館長 郷土史家
菰野町史編集主任として尽力された方。久保田孝夫氏の師匠でもある。我が家も母、私、娘の親子三代でお世話になっている。何処の史跡へ行っても資料も見ずに、立て板に水で話されるパフォーマンスは人々を驚愕させる。頭にCD-ROMが入っているのではないかと思われる。
昭和37年9月30日茨川調査をされた(未発表)ことが、筒井正氏の著書に書かれている。今回かたじけなくも、そのノートを届けて頂いた。茨川調査の他、昭和30年頃からの鈴鹿登山記も書かれている。しかし、茨川調査は日帰りの時間不足のため充分に出来なかったようである。 中島氏の鉱山の本にも協力されている。
菅沼晃次郎 滋賀民俗学会会長
この方については良く知らないが、昭和39年10月茨川の調査をし、「鈴鹿山中に消えた村の民俗」を発表されている(未見)。写真は半分この方が撮られたものである。