
生活と産業
茨川の主産業は炭焼きと林業(杉、檜)であった。それぞれの持ち山で焼いた炭を背負って、三重県側の新町へ出荷した。私の父が昭和23年頃茨川へ行って、一泊させてもらっている。そのときの話によれば村の人は男は四俵、女は三俵の炭を背負ったそうである。鈴鹿HP仲間の北勢町中村さんのご両親は、終戦直後茨川へ炭の買出しに行かれたことがあるそうで、それぞれ、三俵と二俵を担いで運ばれたという話である。
炭一俵は四貫(およそ15KG)であるから、現在の登山者のザックの重さと比べたら雲泥の差である。人一人を背負っているようなものである。炭焼き自体が大変な重労働であるうえに、この重荷を背負って治田峠を越えたと言うことは利明氏の語った「山奥は、弱い人が住める所ではないんです」という言葉が実感できる。
炭焼きの景気が良かった頃は三重県側から人を雇って盛大にやり、運搬専門の人(強力)は茨川--新町間を二往復した。搬出した炭は新町の薪炭問屋「水谷信一商店」に運び込まれた。ここでは、米や生活物資、郵便物の取次ぎまで便宜を図っていたそうである。ご主人は気の良い人で、茨川の人達に盆暮れの決済で赤字が出ても「次の炭で返してくれたらいいから」と言っていたそうである。ある本で郵便配達が峠を越えて運んだと書かれているのは間違いで、茨川へ帰る人達が水谷さんのところで受け取ったと言うのが真相だ。
その他、父は茶畑があったと言っていたが、みつえさんはお茶は収入を上げる程では無かったと語った。それよりも多くの家では養蚕が行われていたそうである。野菜は自家用程度であるが、寒冷地ゆえ病害虫の心配はあまり無かった。米は後藤佐治郎さん(高柳から移住)が焼尾谷付近で作っていたそうだが、石高は芳しくなかった。何せ平地が少なく標高は560mあって気温も水も冷たく、谷間で日当たりが悪いときているから米作りには向かない土地である。
これらの仕事の比重は時代と共に変遷しているはずだが、古い話は証言者もいず分からない。
茨川の婚姻はすべてと言っていいほど蛭谷の小椋一族との間で行われている。経済的に密接な関係を持った伊勢側には嫁に行くことはあっても、来ることは無かった。伊勢平野で育った娘には山間の厳しい暮らしに耐えられないと言うことか。長男以外は他村へ養子に行ったり、町へ出たりで村内に分家することは困難であった。
それにしても、地理的に近い君ヶ畑を素通りして蛭谷とばかり縁を結ぶと言うのには訳がありそうだ。君ヶ畑と蛭谷は木地師の元締めを争ってライバル関係にあったが、そのことと関係があるのかを筒井正氏に伺ってみた。
これは、よく分かりませんが、苗字を調べると、蛭谷にはほとんど小椋姓であるのに対して、君が畑の苗字は、小椋姓もありますが様々です。これは、その村の成立に原因があると私は考えています。 かつて、茨川は鉱山とし知られており、各地より鉱山で働く山師が入り込んで働いていました。その山師は君が畑の人を寄り親(身元保証人)にして働いています。茨川に元からいた住人は、ほとんどが筒井姓、小椋姓で、筒井峠や蛭谷などに居住していた人が移り住んだものと思われます。 古い時代に合っては、結婚は家柄をきわめて重視する風潮があり、蛭谷と茨川とは、相互に密接な婚姻関係によって結ばれていました。蛭谷と、君が畑とは、全国に散在する木地師の支配をめぐって近世以降激しく対立しており、刃傷沙汰まであったと聞いています。質問の答えになったかどうか分かりませんが、これ以上のお答えは私にはできかねます。
ということです。と言って茨川と君ヶ畑は仲が悪い訳でもない。茨川は皆君ヶ畑金龍寺の檀家であり、葬式にはそこから坊さんが来た。ついでに言っておけば、ある本には一人の方が神職、僧職、医者を兼ねたスーパーマンのように書かれているが、そうではなく、村の大人は誰もが祝詞(のりと)やお経を読むこと位はできたということである。神主は交代制であったし、雪深い時に葬儀が出来れば金龍寺の住職は来られなかったのである。火葬の習慣はなく、遺体は共同墓地に北向きに埋葬された。
 大正3年 政所小学校茨川分教場設置。筒井春吉さんの倉庫を仮校舎とし、大正6年に現在も残る(八幡工業山岳部小屋)校舎が完成した。開校当時の児童数は7名(男子4、女子3)だった。中学校は政所にあり、通学は無理であり蛭谷の親戚に寄宿したと言うことである。昭和4年に村出身の石井一正先生が赴任し、廃村までの長きにわたって教鞭をとられた。
大正3年 政所小学校茨川分教場設置。筒井春吉さんの倉庫を仮校舎とし、大正6年に現在も残る(八幡工業山岳部小屋)校舎が完成した。開校当時の児童数は7名(男子4、女子3)だった。中学校は政所にあり、通学は無理であり蛭谷の親戚に寄宿したと言うことである。昭和4年に村出身の石井一正先生が赴任し、廃村までの長きにわたって教鞭をとられた。
村には登山者、釣り師、猟師、行商人などが訪れ、食事は出さないが無料で泊めてあげたそうだ。正さんは来客があると都会の話など聞けて嬉しかったということである。
生活物資は前述のようにすべて治田峠を越えた三重県の新町で調達、ときに阿下喜まで足を伸ばすこともあった。しかし茶屋川の林道が開通してからは、薪炭運搬のトラックに便乗して八日市へ行くことも出来たし、頼んでおけば車が運んできた。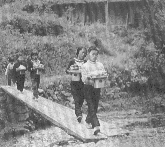
茨川は少ない戸数にしては立派な神社(天照神社)があり、佐々木一氏調査ノートには祭礼は10月16日で、前後一日(計三日)は山仕事を休んだと書かれている。盆正月は下界と変わることは無く、都会へ出て行った人が帰省した。