���t����
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���t��ʌ���
���t�d��������
���t�����w���� |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
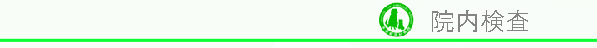
���t����
���t��ʌ���
�@�������A���t�������F���t�̒��̌��������ɂ��Č���������̂ł��B�����p���������v���@��
�v��������A���t���X���C�h�K���X�ɔ����h��̂��Đ��F�����W�{(�h���W�{)���������Ŋώ@�����肵�܂��B�@
�v�a�b(������) �@�̓��i�������ۂ�E�C���X�Ȃǂٕ̈����זE���Ɏ�荞��A�Ɖu�R�̂�����ĎE�����肷�铭�������Ă��܂��B�������ɂ́A�D�����E�D�_���E�D����E�P���E�����p���Ȃǂ̎�ނ�����A�h���W�{���������Ŋώ@���邱�Ƃŕ��ނł��܂��B��ʂɁA�ۂɊ�������Ɣ����������������܂��B
���������͎��������v���@�ŁA���������ނ͓h���W�{�̌������ώ@�Ō������܂��B
�q�a�b(�Ԍ���) �@�x���炩�炾�Ɏ_�f���^�� �A�s�v�ɂȂ����Y�_�K�X��x�Ŕp�������ڂ����܂��B�Ԍ���������������ƕn���ɂȂ�A��������Ƒ����ƂȂ�܂��B�Ԍ�������Ԍ����̑傫���͎��������v���@�ŁA�Ԍ����̌`(����Ȃ��̂͐^���Ԃ�������p���̂悤�Ȍ`)�͓h���W�{���������ώ@���Č������܂��B
�g����(�w���O���r��) �@�Ԍ����Ɋ܂܂�Ă���F�f�ŁA�Ԍ����̂͂��炫�̂Ȃ��ł��ł���Ȏ_�f�̉^����S���Ă��܂��B���������v���@�Ōv�����܂��B
���t���̌����̗e�ς̊����i���j�������܂��B���������v���@�Ōv�����܂��B
�Ԍ����P��
�l�b�u�i���ϐԌ����e��)
�l�b�g(���ϐԌ������F�f��)
�l�b�g�b(���ϐԌ������F�f�Z�x)�@�Ԍ����P���́A�Ԍ������ƃw���O���r���l�ƃw�}�g�N���b�g�l����v�Z����܂�(���������v���@���Z�o���܂�)�B
�l�b�u�́A�Ԍ����̑傫���������܂��B�������傫����Α�^�̐Ԍ����A��������Ώ��^�̐Ԍ����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�l�b�g�́A�Ԍ����Ƀw���O���r�����ǂ̂��炢�܂܂�Ă��邩������킵�܂��B
�l�b�g�b�́A�Ԍ����̑̐ς�����̃w���O���r���̗ʂ�\�킵�܂��B
������g�ݍ��킹�Ă݂邱�ƂŁA�n���̃^�C�v���������܂��B
�o�k�s(������) �@�������S���������錌�������ł��B���ǂ������ďo�����N����ƁA���̑������������̌��Ǖǂɂ������ďo�����Ƃ߂铭�������܂��B����������������i�R���^��l�ȉ��j�Əo�����₷���Ȃ�܂��B�����Ƃ��Ăт܂��B���������v���@�Ōv�����܂��B
�ԏ�Ԍ��� �@�����n�ȐԌ����ŁA���n�Ԍ����ɂȂ钼�O�̂��̂ł��B����ȐF�f�Ő��F����Ɠ����ɖԖڏ�̖͗l���݂��邱�Ƃ��炱�����t�����Ă���A�����@�\�̒��x���݂�ڈ��ƂȂ�܂��B������F�����h���W�{�̌������ώ@�Ō������܂��B
�@�@
�@���t�ÌŌn�A���n�n�����F���t�ÌŌn�Ƃ́A���t���ł܂点�ďo�����~�߂�(�~��)���߂̈�A��
�����̂��Ƃł��B
�h(1)����w�h�h�h(13)�܂ł̈��q���֗^���邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B���t���Ìł��J�n����̂ɂ́A���Ǔ��i�����n�j
�ƌ��NJO�i�O���n�j�Ìň��q����͂��܂�2�̃��[�g�ƁA���̌�ɂȂ��鋤�ʌn������܂��B���̂悤�ɂ���
�Ìł������t�ɂ���ď����̏o���͂Ƃ܂�܂��B
�@���n�n�Ƃ́A�Ìł������t�̂����܂��n���������������܂��B�ÌŌ������܂ł������ɑ��݂�������ƌ��t
�̗����j�Q���邱�ƂɂȂ�A���x�͑̂ɂƂ��ėL�Q�ɂȂ��Ă��܂����߁A��ڂ��ʂ������ÌŌ��͐��n�n�ɂ����
���������K�v������̂ł��B
���̂ł́A�ÌŌn�Ɛ��n�n���o�����X�ǂ��������Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B
�o�s(�v���g�����r������) �@�v���g�����r���́A���t�Ìő�U���q�ł��B�v���g�����r�����Ԃ́A�O���n�̋Ìő�u�h�h���q�Ƌ��ʌn���q�ُ̈�ׂ邽�߂ɂ����Ȃ������ł��B���t���Ìł��ɂ����Ȃ�ƁA���̎��Ԃ������Ȃ�܂��B�b�n�`�f�Q�u�Ō������܂��B
�`�o�s�s
(�����������g�����{�v���X�`������)�@�g�����{�v���X�`���́A���t�Ìő�V���q�ł��B�����������g�����{�v���X�`�����Ԃ́A�����n�̋Ìő�u�h�h�h�A��h�w���q�Ƌ��ʌn���q�ُ̈�ׂ邽�߂ɂ����Ȃ������ł��B���t���Ìł��ɂ����Ȃ�ƁA���̎��Ԃ������Ȃ�܂��B�b�n�`�f�Q�u�Ō������܂��B
�e����(�t�B�u���m�[�Q��) �@�t�B�u���m�Q���́A���t�Ìő�h���q�ł��B�̎����זE�ŎY������āA��80%�����t���ɑ��݂��܂��B���t�Ìł̍ŏI�i�K�ŁA�g�����r���ɂ���ăt�B�u�����ɕω����Č��t���ł܂点��Ƃ������������Ă��܂��B�܂��A�����̋ÏW������n�������ɂ��֗^���Ă��܂��B�܂��A���ǂ�����Ƃ��ɂ͑������܂��B�b�n�`�f�Q�u�Ō������܂��B
���t�d��������
�@�J���E���A�i�g���E���A�N���[���A�J���V�E���A�����Ȃǂ̌��t���̓d�����͏�Ɉ��̒l��ۂ��Ă��܂��B
�����ԘA�����Ă̓_�H�A�t���ɂ́A�J��Ԃ��Ẵ`�F�b�N���K�v�ƂȂ�܂��B
�J���E��
�@�J���E���́A�ق�ǂ��זE�̒��ɑ��݂��܂��B���t���̃J���E���Z�x�́A�������t���̉e�����܂��B�q�f�A�����ȂǂŒႭ�Ȃ�A�t���@�\���ቺ���Đt�s�S�ɂȂ�ƍ��l�ɂȂ�܂��B
�i�g���E�� �@�啔�����זE�O�t�ɑ��݂��邱�Ƃ���A���t���̔Z�x�́A�����o�����X�̎w�W�ƂȂ�܂��B �E���A��`�����ǁA�ێ�ߏ�A�����厾���Ȃǂō��l�ƂȂ�A�����펾��(�q�f�A����)�A�A�ǐ��A�V�h�[�V�X�A�A�W�\���a�A�l�t���[�[�ȂǂŒ�l�ƂȂ�܂��B
�N���[�� �@�啔�����זE�O�t�ɑ��݂��܂��B���t���̔Z�x�́A �E���A��`�����ǁA�A�ǐ��A�V�h�[�V�X�Ȃǂō��l�������A�����펾��(�q�f�A����)�A���A�ܓ��^�A�}���t�s�S�ȂǂŒ�l�ƂȂ�܂��B
�J���V�E�� �@�J���V�E���́A�قƂ�ǂ����̒��ɑ��݂��܂��B���t���̃J���V�E���Z�x���߂ɂ͑����̃z����������������Ă��܂��B�����p��A���������b��B�@�\���i�ǁA������������A������ᇍ��]�ځA�b��B�@�\���i�ǁA�r�^�~���c���łȂǂňُ퍂�l�ƂȂ�A�r�^�~��D���R�A���b��B�@�\�ቺ�A�����t�s�S�Ȃǂłُ͈��l�ƂȂ�܂��B
���@���� �����́A����ӂ�G�l���M�[��ӂɕK�v�ȓd�����ł��B�t�s�S�A�b��B�@�\�ቺ�ǁA���b��B�@�\���i�ǁA�r�^�~��D�ߏ�ێ�A���[���Ȃǂňُ퍂�l�ƂȂ�A�r�^�~��D���R�A���������b��B�@�\���i�ǁA����a�Ȃǂňُ��l�ƂȂ�܂��B
���t�����w����
�@���t�����S�������ē�����t�̕���(�����܂��͌���)���w�I�ɕ��͂��錟���ł��B
�h���C�^�C�v�̐����w�����������u���g�p���܂��B
���̌����ɂ��A���ɓ����n�̊̑���t���ُ̈���`�F�b�N���邱�Ƃ��ł��܂��B