
茨川絵図面
筒井みつ江さん宅に伝わっている古い絵図により、茨川周辺の細かい地名が判明した。これは当時の様子を窺う大変貴重な資料である。

全体図

部分拡大図
作者、製作年代とも記入されておらず不明。しかし境界に西藤原村と言う記入がある。明治22年に町村制が実施され、東藤原村・西藤原村・立田村・白瀬村・中里村が誕生しているのでそれ以後である事は確か。
これで具体的な場所が分かると思いきや、現在の地形図と見比べると川筋、部分部分の縮尺が全く違う。これには以下の理由が考えられる。
個人的には単に3番目の理由によると思う。
参考として現在の川筋、及び上記の絵図を見やすく単純化したものを作ったので比較されたい。
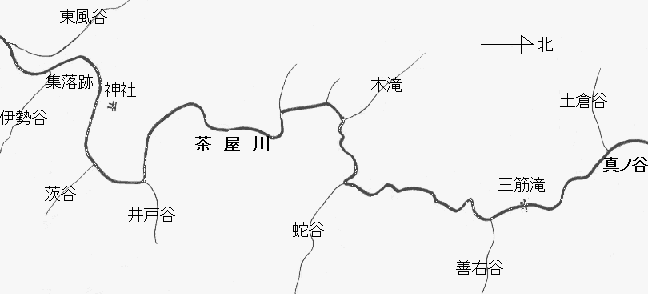
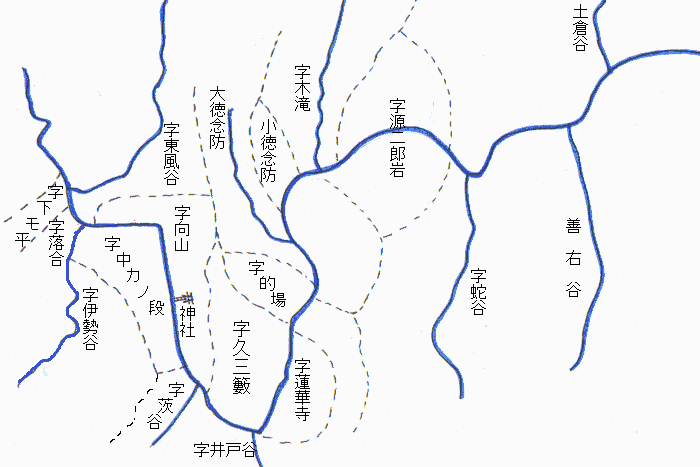
(上)現在の地形(二万五千図・竜ヶ岳を使用) (下) 絵図字名
上の図と比較すると茶屋川と書いた水平部分が欠落しているのに気付かれるであろう。川がUターンした後いきなり木滝が現れる。実際の地形図と比べると蛇谷・善右谷・土倉谷の間の距離が極端に短い。そして中心部が大きく描かれていること等が分かる。
字名解説 字中ノ段とある場所が集落跡である。神社東にも三軒家があった。字蓮華寺には銀山があった頃、その名の通り蓮華寺という立派な寺があったと言い伝えられている。ここにも昔集落があり、上茶屋と言われていた。対して現在の集落跡を茨茶屋と呼んだ。最初の支流の位置がおかしいので字的場の位置が確定できないが、殿様(彦根藩か?)が弓矢の稽古をする場所であったと言う。何故このような辺鄙な場所で行う必要があったのか分からない。狩場だったのだろうか。源二郎岩は河原から30mもある岩が天に聳えているとある。徳念防は谷名らしい。確かに大徳念防と木滝の間に小さな谷がある。これを小徳念防と言うのだろう。どちらの徳念防か知らないが音吉さんと安次郎さんが共同で5年間炭を焼いていた。善右衛門谷や蛇谷では立ち木の権利を買って、伊勢側の坂本や石榑の人も炭を焼いていたようである。