大河愛知川最初の一滴 05.10.16
古(いにしえ)の念仏ハゲ横断ルートを辿る
愛知川を大河と称すると多少気がひける。日本を代表する信濃川、利根川、石狩川などに比べればごく小さな河川である。またアマゾン、長江、ナイルと比べたら、カエルのションベンみたいなものである。大陸の河川など持ち出すほうがおかしいのであるが、愛する鈴鹿に限ればやはり堂々たる大河である。当サイトは鈴鹿専門なので、愛知川を大河と呼んでも差し支えなかろう。
その愛知川を遡ると御池川、茶屋川、神崎川という同規模の三大支流に分かれている。ではいったいどれが本流なのだろう。御池川は残念ながら最初に分岐するので本流とは言えない。北の茶屋川と南の神崎川の対決になる。本流と支流の判断は川床の低さや集水面積、水量で判断される。
茶屋川は御池、藤原、竜の水を集め、神崎川は御在所、雨乞、釈迦の水を集める。何れもそうそうたる鈴鹿の名山で、その点では優劣つけがたい。しかし川の西側に目を向けると、神崎川にはイブネ、銚子ヶ口が連なるのに対し、茶屋川はヒキノの尾根という点が弱い。やはり神崎川を本流と見たい。神崎川はそのまま愛知川と呼ばれることもあるので、以前から本流と見られていたのかもしれない。
では神崎川の最源流、即ち愛知川最初の一滴は何処で生まれるのであろう。ポイントはコクイ谷分岐である。規模から見て、どちらが本流とも言い難い。しかし右の杉峠方向の谷には地図に名前がない。知る人ぞ知る御池谷という名があるのだが、殆ど流布していない。つまり支流としての一般名がないことが、本流と認められている証左である。この本流を地図でたどると、鉱山跡付近から左に折れて雨乞岳山頂に行き着くことが分かる。寡聞にしてこの谷を詰めて雨乞岳に登った話を知らない。入り口の大滝が気にかかるが、やはり大河愛知川最初の一滴は自分の目で確かめてくるしかない。
間近に見る雨乞岳の念仏ハゲ 郡界尾根から見る秋の鎌ヶ岳
![]()
御池谷は「鈴鹿の山と谷」第4巻にも、登頂ルートとしての可能性すら載っていない。御池谷の項を見ても簡易な紹介しかなく、西尾氏自身入ったことがないことが分かる。登り口にある崩壊と滝マークが曲者だ。様子が全く不明なので20mロープと簡易ハーネスとしてテープスリング、エイトカン、ヘルメットを持っていくことにした。高巻きからの沢身下降に備えたものだ。 出発は朝明か武平峠か迷うところだが、念仏ハゲの古道も確認したいので武平峠からとする。
このルートに時間的な読みは不可能なので早朝に自宅を出る。7時5分ごろトンネル東の駐車場を出発。7時では早朝といえないらしく、御在所岳の登山口はすでにたくさんの車が停まっていた。武平峠にも車が数台いて驚く。しかも他県ナンバーばかりだ。武平峠から七人山のコルまでは一般登山道なので省略するが、久々に歩いた印象としては随分長く感じた。特にクラ谷源流は7年ぶりで記憶が殆どなく、初めて歩くような気がして新鮮だった。デジカメの時刻を見ると8時50分ごろコルに着いたようだ。御池岳ならもう山頂に着いている時刻だ。仕事にかかる前に10分ほど休息して行動食と水を摂取する。
コンパスを定めてコルの向こう側へ入っていく。別段ヤブもなくそんなに苦労はない。適当に歩いていたら杣道が現れた。昔、杉峠−御池鉱山−念仏ハゲ−七人山コルを結ぶルートがあったことは話にも聞くし、「鈴鹿の山と谷」にも概念図がある。たぶん鉱山のための道であろう。上下に分かれたり交錯したりで明瞭ではないが確かに道跡である。急斜面に切られた道は自然に還りかけ、どうしても体が谷側に引かれるので靴の中が痛い。あまり高度を落とさないように1000m前後を保ってトラバースしている。やがて猫の額ほどの平坦地を見つけて一息つく。GPSのメモリーボタンを押しておく。マップポインターを使って現在地確認をすることはあまりない。何処をどう歩いたかは、帰宅後パソコンにダウンロードしてのお楽しみである。
山腹を横切る鉱山の古道 小さなコバで一息 自然に還りつつある例のブツ
小コバから前方に樹間を通して白いものがチラチラ見える。念仏ハゲのようだ。意外と簡単に到達することができた。さすがに遠目にも目立つだけに、ハゲの淵に立つとその規模に圧倒される。巨大な採石場のようだ。「鈴鹿の山と谷」の地図は総てデフォルメされているので正確なルートは不明だが、念仏ハゲの真ん中を横断しているように読める。しかし現実は不可能である。岩ならともかく、対岸は土砂の絶壁である。いかな名人をもってしても登れないだろう。最上部までは見通せないが、どこか渡れる場所があるのだろうか。
とりあえずフチ沿いに下降するしか手はない。崩壊の末端近くから普通の谷状になってきて、見下ろすとチョロチョロ水が流れ出している。愛知厚顔さんの温泉の話を思い出して谷底へ下りてみた。手ですくってみるとただの清水のように思える。飲んでみたが味も香りもない。温泉(冷泉)は何処にあるのか、それとももう湧いていないのか不明である。
あまり高度を下げると効率が悪いので、ここで苦労して砂ザレを這い上がって対岸に登りついた。
すぐにまた杣道を発見した。選択したルートは間違っていなかったようだ。テープもヒモもない快適な場所だ。太い木はないが雰囲気の良い二次林である。念仏ハゲで末端まで下降したため高度は下がり、900mラインをトラバースしている。右下にあるはずの愛知川源流御池谷のせせらぎが徐々に大きくなってくる。ほどなく谷が雨乞岳に向かって屈曲する地点に着いた。分かりやすく言えば杉峠道下の鉱山跡対岸である。紅葉しているのはハゼとシラキだけだが、それだけでも秋の雰囲気がする。ボタ山の高台に腰かけ、イブネや高昌山を眺めながら行動食をとる。山は治外法権なので、禁煙しているタバコも吸う。
ここから念のためヘルメットをかぶる。この先は初めてなので用心するにこしたことはない。最初はただの河原で難なく進む。右側に鉱山施設が点在する。やがて左手(右岸)が切り立った岩盤になり、多段の滝が現れてくる。その岩盤の中ほどに四角い坑口があり、かなりの水量を吐き出している。これは見物せずにはおられない。かがんで中に入るとノミ跡も荒々しい手掘りの洞窟で、奥は暗くて見えない。鉱夫の怨念がこもっているような気がして、凄い圧迫感を感じた。フラッシュを焚いて写真だけ撮り、早々に逃げ帰った。
採石場のような念仏ハゲ 御池谷多段の滝 水を噴出する坑口
次々と岩盤の滝が現れる。登山靴なので直登はできないが、右手左岸が樹林帯なので難なく巻くことができる。連瀑を過ぎると穏やかな地形になり、杣道がある。こんなところでも登る人がいるのかと思ったが、これはどうやら先ほどの念仏ハゲ鉱山ルートの続きで、高度を上げてから杉峠へトラバースするものと思われる。
快適に高度を上げていく。柔らかいカンスゲの絨毯の中を箱庭のような苔むす渓流が流れ、両岸の斜面はブナなどの広葉樹の森となっている。振り返れば谷のはざ間にイブネが姿を現し、山上台地に霧が流れていく。ああ、いい場所だ。早く登るにはもったいないのでゆっくり休憩する。七人山のコルから掘割の登山道を登るより百倍良いルートだ。もはや無用の長物と化したヘルメットを脱ぐと、涼やかな風が心地よい。
明るく歩きやすい谷になる 振り返るとイブネの山頂が見え隠れする 滝は小規模になり庭園の趣
詰めが近づくと水量が細り、付近がヤブっぽくなってきた。源流の一滴を確認しなければならないので谷芯を外せない。ササを掻き分けて細流を追うが、分岐するたびに本流を見分けなければならない。最後は水音はすれども姿は見えずという場所に到達。よく見ると小さな空洞から水が出てくる。左の細流はまだ上へ続くが、この穴の水量のほうがずっと多いので、これを水源と決める。横穴に水筒を突っ込んで汲もうと思ったが、浅くて濁ってしまうのであきらめた。ともかく場所を確定できて安堵する。無数にある愛知川の水源のひとつにすぎないが、これが本家本元の嫡流とすれば感慨もひとしおである。
さて山頂は近いはずだが、見渡す限りヤブである。地図を見て東峰との鞍部を目指すか、あるいは本峰直登か迷う。登る人がいるのか獣道なのか分からないが、右手のササヤブが割れていたので本峰直登と決す。ヤブといっても腰までくらいなのでそこそこ登れる。振り返ると対岸の斜面の上に東峰が頭を出し、素晴らしい風景になってきた。東峰山頂に人がいるのが見えるが、ガスの流れが速く、あっという間に隠れてしまう。
快調なのはつかの間、割れ目も消えてしまい、やはり獣道だったのだろう。密生するササはやがて胸まで来るようになった。こうなると登りの抵抗力は相当なものがある。イブネのジグネも何のその、雨乞のそれは元気すぎて困ってしまうほど頑健でバネが強い。やがてササは背丈を没する長さになり、傾斜も強まって殆ど前進できなくなった。以前のイブネのようにササは長くとも平地なら何とかなるが、急斜面ではお手上げである。山頂目前でササの海に溺死するのかと、冗談抜きで困り果てた。やはり鞍部に向かったほうが良かったかもしれないが、それより問題は現在の状況を打破することだ。
愛知川水源の空洞 背後を振り返る 遠景釈迦ヶ岳 ササの海に捕まる
どうせ視界がないので逆にしゃがんで潜ってみる。こうして芝目ならぬササ目を読んで平泳ぎしていく。ときに点在する潅木にすがり、ときに馬力に訴えて強引に踏み上がる。筆舌に尽くしがたい困難を乗り越えて、池(大峠の沢)のすぐ北に飛び出した。池の畔にあったカマツカの実を食べながら三角点を踏むと、たむろしていた登山者に 「何処から登ってこられたのですか」 と聞かれた。びしょ濡れでゴミだらけの風体が異様だったのだろう。やはり御池谷の名は通用するはずもなく、御池岳から縦走してきたと勘違いされた。まさかねえ。帰路はどのコースが良いか色々聞かれる。そのまま引き返すより鉱山跡コースを進言する。
雨乞岳から東雨乞岳 東雨乞岳でくつろぐ登山者 リンドウ
ここから見る東雨乞岳が好きなのでお昼ご飯とする。凄い速さでガスが流れ、カメラを構えるともう景色が変わっている。こういう風景は肉眼で見るには快晴より味がある。しかしカメラではコントラストがない弱々しい映像になってしまう。
東峰にもたくさん人がいるようだ。向こうから次々と人がやって、こちらも賑わいを見せる。やはり高度を稼げる武平峠からの人が殆どのようだ。食後は東雨乞岳で展望を楽しんだ後、旧郡界尾根から下山した。三人山付近も紅葉には程遠い。10月も半ばを過ぎたのに、こう生温い天気が続いては木もボケてしまうだろう。
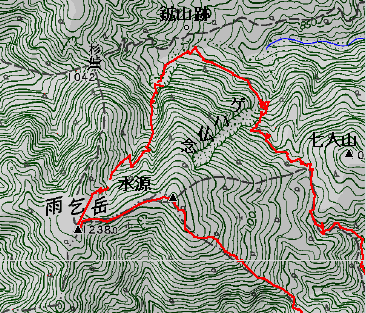
核心部のGPSトラック
谷の中で乱れているのは電波状況のため。
実際は谷芯をトレースしている。