 十 尾張にたまと云ふ人あり。困難な行程を好めり。此の人、異形のいでたちにして一目でそれと分かれり。足繁く山に通ひしが、とうとう細君より自粛命令が下れり。あまたの猫と同居せり。
十 尾張にたまと云ふ人あり。困難な行程を好めり。此の人、異形のいでたちにして一目でそれと分かれり。足繁く山に通ひしが、とうとう細君より自粛命令が下れり。あまたの猫と同居せり。同じく尾張にいわなっちと云ふ人あり。深き山中で天幕を用ひず寝袋一つで泊まれり。ゆえにみのむしと云ふ名を拝するなり。此の人、脚の筋肉非常に発達せしこと競輪選手の如し。巨大なる背嚢を担ぎ撮影機材の歩荷をなせり。
藤 原 物 語 2040年3月 記
序 文
此の話はすべて菰野の老人、葉里麻呂翁より聞きたり。今を去ること三十八年前、平成十四年三月頃に行はれた花見山行を中心に、夜分老人を訪ねてその話を聞き取りて筆記せしなり。此の老人少々ぼけており他の山行話も交じりしが写真は保存して居れり。一字一句をも加減せず当時、当日のままを書きたり。願はくは之を語りて平地人を戦慄せしめよ。
一 藤原岳は勢州員弁郡と江州神崎郡の境にある山なり。此の山あまたの草花を産し、花の百名山に数へられる秀峰なり。古くは富士見山、袴ヶ腰とも云へり。藤原の名は、朝廷の勘気に触れ野尻山に蟄居した藤原仲成に因むと云ふ説あり。
二 藤原岳の麓に坂本郷あり。百数十戸の家ありて古くは勢州員弁郡坂本村と云へり。児玉、近藤の姓多く、大半は敬善寺の門徒なり。
三 藤原岳山麓にうり坊と云ふ人あり。幼な子ありて子煩悩なり。此の人鈴鹿徘徊倶楽部の会長にして鈴鹿の木や石や、すべて其の形状と在所とを知れリ。或る日在郷の民家の娘数名、山に入りたるまま帰り来たらず。家の者は天狗に攫われたるならん、神隠しならんと思ひしが、翌日喜々として帰り来たれリ。家の者何事たらんと問へば、うり坊なる人たちと御池岳に泊まれリと云ふ。巴菜と名乗る雪女も居れりと云ふ。何ゆえ雪女と分かりしかと問へば、其の人姿かたちは常人にあれど山を降りるに足を用ひず雪の中を滑ったり転がったりして降りる様は常人に非ず、雪女ならんと云へり。
四 そのとき夫人同伴の隊長と名乗る人や、髪につららを垂らした御池杣人と名乗る人も姿あらわせりと云ふ。
五 熱田に御池杣人と云ふ人あり。御池岳ばかり登る奇人なり。故に藤原岳の花見山行には参加せず。此の人御池岳の書を大量に著はし、評判となれり。あまり大量に著はしたゆえ残りを山羊に喰わせんとせしも其の山羊腹を壊し大いに病めり。以後この書毒を山羊附子(やぎぶし)と云へり。この毒、笛太鼓で踊れば解毒と成す。類似したる毒は葉里麻呂の戯れ歌にもあり。之を黒田附子(くろだぶし)と云ふ。
六 御池岳は真ノ谷を隔てて藤原岳の西一里余に在れり。鈴鹿一の高峰なり。濃き薮の中に二十有余の池を隠せり。大半は永源寺に属せども、最も近き村は多賀の大君ヶ畑なり。
七 鈴鹿に隊長と云ふ人あり。恐妻家なり。此の人、身の丈六尺を超へる大男なれど可憐なる野の花に通じたり。其の地の放送局隊長に頼み藤原岳の番組を作らんとするなり。
八 隊長山好きの人々に声を掛け、やまぼうし、なっきい、さこた、へべれけ・りん、巴菜、有里、うり坊、藤原、へべれけ・とおる、たろぼう、まんてま、たま、やまちゃん、いわなっち、まうんとごあ、高森一家・・などと名乗る人々あまた集まれリ。
九 三月二十四日早暁、西藤原駅に全員集結せり。撮像機の前で自己紹介をするなり。電脳網で名前をよく知るも、葉里麻呂は本日初対面の人多し。いわなっち、たま、やまちゃん、まうんとごあ、なっきいと云ふ人達のことなり。かような人々の尊顔を拝せるは隊長の企画と人徳のお蔭なり。
 十 尾張にたまと云ふ人あり。困難な行程を好めり。此の人、異形のいでたちにして一目でそれと分かれり。足繁く山に通ひしが、とうとう細君より自粛命令が下れり。あまたの猫と同居せり。
十 尾張にたまと云ふ人あり。困難な行程を好めり。此の人、異形のいでたちにして一目でそれと分かれり。足繁く山に通ひしが、とうとう細君より自粛命令が下れり。あまたの猫と同居せり。
同じく尾張にいわなっちと云ふ人あり。深き山中で天幕を用ひず寝袋一つで泊まれり。ゆえにみのむしと云ふ名を拝するなり。此の人、脚の筋肉非常に発達せしこと競輪選手の如し。巨大なる背嚢を担ぎ撮影機材の歩荷をなせり。
十一 うり坊、駅の蒸気機関車や登山届の解説せり。聖宝寺の境内をぞろぞろと連なり登山道に取り付けり。聖宝寺は臨済宗妙心寺派の古刹なり。鈴鹿にやまぼうしと云ふ人あり。物腰柔らかで笑みを絶やさず人を癒せり。此の人、能く花を知ると評判の人なり。そのやまぼうし長名水で水を汲むところ撮影せり。此の人御池岳撮影の折も長命水で水を汲めり。二百年は生きると思へり。
りんも水を汲めり。此の人へべれけ・とおるの奥方にして酒呑みなり。
十二 春の藤原岳は人気ありて人出の多きこと驚異的なり。老若男女雲集して登山道に数珠の如く連なれり。山頂で火事ありとて麓から手桶の水を手渡しして消す事も可能なり。
此の時期大貝戸、聖宝寺から登りたること軍事作戦に例へれば玉砕覚悟の正面突破と云へり。敵の背後に回り込むのが上策なれど混成部隊なれば致し方なし。
十三 途中で女人集まりて行動食(おやつ)の講義あり。頂きものにありつけり。うり坊冬道の講釈などせし。ここまで福寿草、節分草、州浜草、芹葉黄蓮などの花あり。

十四 八合目より泥壁をこねたる如き道になり、靴の汚れること甚だし。夥しい数の人々が此の道をこねてこねてこねまくり、やがて泥流となれり。
十五 避難小屋周辺の混雑極まれり。昼飯によき場所を求めて彷徨し、小屋西の平坦地に落ち着けり。福寿草咲き展望丘を望む良き場所なり。各々思い思いの場所に腰を下ろし昼飯をなしながら談笑するなり。巴菜の料理教室を撮影せり。
十六 葉里麻呂、御池撮影行の折、牡丹淵展望でしどろもどろになれり。故に今回は出番無しと安心しておれども地形図の講釈せよとの下命ありて再び醜態をさらすことになれり。
昼飯後地形図と磁石について述べたり。展望丘で山座同定の筈が山の見えざる小屋付近になりて四苦八苦するなり。やがて風雪模様となりて寒きこと甚だし。いい加減な所で切り上げるなり。



十七 再び避難小屋に戻りて、うり坊小屋の解説をなせり。寒気に打ち震へ誰も展望丘に行きたしと云ふ者あらず。即刻下山となれり。


十八 風雪強まりて辺りはたちまち白き世界となれり。花を覆ふなごり雪は風情あり。
下山路の泥田状況ますます悪化し歩行しづらき事甚だし。たろぼう、りん等長靴組の勝利なり。此の泥道で巴菜は期待に応へて見事転倒し、御池岳の尻滑りに続き泥滑りをなせり。自分の出番を良く心得たる様は賞賛に値すると云へり。
十九 京にまんてまと云ふ人あり。博識なり。此の人本日出会ひし花を二十余種手帳に書き留めており驚けり。たろぼうも手帳にびっしりと書けり。葉里麻呂の如きぼんくらは四つか五つしか気付かず、二つのまなこは只の飾り物と云へり。
二十 八合目分岐より大貝戸道を下れり。植林のつまらぬ道なれど鈴鹿寒葵の葉あり。全員大過なく下山したれども雪は雨となれり。隊長挨拶、各々の感想を撮影したる後解散となれり。
花と雪、泥遊びは思ひ出に残れり。各自電脳のみならず、生身の言葉を交わしたること有意義と云へり。また局の人、高森家の子ら、良く頑張れり。
※ 物語と云ふ性格上、敬称無きこと御賢察頂きたし 原作 柳田国男 「遠野物語」
生存者近影 (2040年)
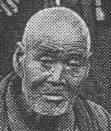 |
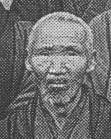 |
 |
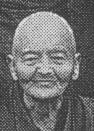 |
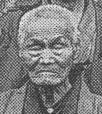 |
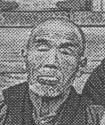 |
| 金麻呂隊長 | へべれけ・とおる | たろぼう | うり坊 | 葉里麻呂 | 御池杣人 |
ご婦人の写真も掲載せんと思へども、葉里麻呂老人が「袋叩きにあうのでやめておけ」と云へり。初対面の人もしかり。老人既知の人に留め置けり。
巻末資料 (一)
葉里麻呂翁の語りし『藤原物語』を読み、遠い日を思ひ出して御池杣人が詠める
本歌 花さそふ あらしの庭の 雪ならで ふり行ものは 我身なりけり (入道前太政大臣)
花さそふ あらしの藤原の 雪女 ズリゆく泥尻は 鑑(かがみ)なりけり (近藤朝臣)
現代語訳 フクジュソウやセツブンソウ、早春の花々がつつましく人々を誘ってやまぬ。その花々に誘われて、早春の嵐の藤原岳に花吟行。そこに登場したる巴菜女は、雪女の気高さも透明なほどの肌の白さ?もなんのその。純白の雪上だけでなく、嵐吹く雪解けの泥道をも得意のズリズリ行きは止まらない。泥にまみれたそのお尻姿は、鈴鹿を愛する人々の鑑(手本、模範)であることだなあ。(もぐもぐ)
後世の注釈者 おそらく葉里麻呂の曾孫氏が、葉里麻呂翁がバナナを食べながら語った昔話を聞き書きをしたであろう『藤原物語』は見事である。心強いことにおたんちんぶりはぼけないものだ。臨場感が伝わってくる。御池杣人翁もすでにかなりのぼけ具合であったが、『藤原物語』を読んで遠い過去が一瞬よみがえったようだ。家人の知らないうちに、何を思ったか急に隠してあったミルキーをなめはじめ、あんぱんも五つ、この歌を作りながら食べてしまったという。
管理人解説(2040年) おお、御池の御老人・・・お懐かしゅうございます。うるうる。御老人は確かもう九十を越えておられるはずですが、歌も食欲も健在で何より。私はもう紙オムツのお世話になっておりますじゃ。それでは昔の調子で解説でもこきますか。
まず本歌の選定が冴える。もうすでに花・あらし・雪というキーワードが組み込まれていて当日の様子を良く現わしている。もう一つ言えば入道前太政大臣とは藤原公経のことであり藤原岳の隠し詞になっている。さらに公経の歌は老いの嘆きを述懐したものであり、皆々老人になってしまった今の心境と重なるのである。見事なり杣人翁。 我が身→鑑(かがみ)の置き換えは秀逸。とことん自然を楽しんでいた巴菜女讃歌となっている。鑑に祭り上げられた巴菜女が鈴鹿に骨を埋めたる後はイワカガミとなって末永く人々の目を楽しませるであろう。 (もがもが)
管理人の曾孫(2070年) 「藤原物語」を曽祖父、葉里麻呂から聞き書きしたのは私ではなく孫、すなわち私の父である。葉里麻呂は私がもの心ついた頃に、自分で剥いたバナナの皮で転倒して亡くなっている。曽祖父の事はよくは覚えていないが、晩年ますますガンコになりボケも併発して家人を困らせていたようである。父もこの話を聞きだすのに相当苦労したと言っていた。
杣人翁もこの歌を詠んだのち、あんぱんを喉に詰まらせて亡くなったと聞く。遺骨は遺言どおりコグルミ谷に埋められ、巻き道分岐の大岩は杣人の墓として御池岳を愛する登山者が手を合わせていく。私も先日、故ウリ坊翁の御子息(と言ってももう七〇を越しているが)と一緒に杣人翁の墓に詣で、翁が生前愛したと言うあんぱんを供えてきた。
藤原岳花見山行は遠い昔のことであり、関係者もことごとくこの世の人ではない。ただ一人、長名水をたらふく飲んだやまぼうし媼が存命であると風の便りに聞いたが定かではない。
巻末資料(二)
藤原讃歌
作詞 金麻呂隊長
漢詩訳 柳澤郎女
恋慕冬御池 冬の御池に恋い焦がれ
空虚夢醒時 はかない夢がさめるとき
脚下雪割草 足下に咲くミスミソウ
予感巡春季 季節はめぐり春の予感
阻行小臭木 行く手を阻むコクサギが
勇敢挑戦我 我に挑む勇ましさ
歓喜被試練 ありがたき試練に喜びて
優如節分草 セツブンソウの優しさや
踏雪孫太尾 残雪踏みしめ孫太尾根
樅木阻我行 行く手を阻む樅(もみ)の木が
歓喜来迎我 我を迎える嬉しさや
御背嚢飲水 ザックを降ろし水を飲む
誇福寿草開 フクジュソウ咲きほこり
慕山藤原岳 山を慕いて藤原の
山男仰峰也 峰を仰ぐ山男
知暁花之情 花の情を知るものぞ
春花開我前 我先に咲く春の花
潔良開花式 いさぎよき咲き方に
山男恋慕也 恋してしまう山男
薄命優美哉 はかない命は美しい