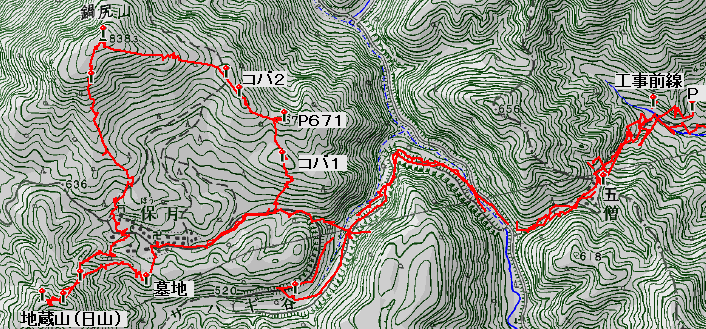五僧峠から鍋尻・地蔵山 05.03.20
![]()
人様もすなる花見といふものを、我もしてみむとて、するなり。それの年の三月の二十日あまり一日の日の、辰のときに門出す。その由、いささかものに書きつく。
紀貫之土佐日記風に全編書くと誰も読んでくれないし、自分も疲れるのでやめておこう。鈴鹿も3月後半ともなれば花見と相場が決まっている。御池岳は残雪多い上にゲートが閉まっている。霊仙山などよかろうが人も多い。いわんや藤原岳においておや。やはり生来の気性として、もそっと寂しい所が良かろうということで久しぶりに鍋尻山へ登ることにする。時山奥の林道が伸びて、五僧を容易に越せるようになったこともある。滋賀へ車を回さなくてもいいのは有難い。
日曜は時山の工事がお休みである。しかし万一ということもあるので、邪魔にならない奥の荒地へ乗り込んで駐車した。せっかくワックス掛けした車が泥まみれだ。谷へ駆け下りるとすぐに登り谷との分岐。そこから標高差130mを登ればもう五僧峠である。実際あっけないのだが、間隔があいたのと、ヒザの不調で朝飯前とはいかなかった。
余談ではあるが近頃ズボンはジャージを愛用している。なぜかといえばウエストがゴムで楽だからである。「そうなったら人間お仕舞いやね」と人に言いながら、自分がそうなった。ベストは64KGであるが、もう70KGに王手が掛かっている。当然スタミナにもヒザにも悪影響が出ているのだ。
一月末にゴッソリあった峠の雪は、廃屋の軒先を残して完全に消えていた。雪さえなければあれほど苦労した保月への行程も楽勝である。天気はどんよりした曇り空。しかし不思議と見通しはきく。通る人もいない西へ下る旧道は荒れている。獣の背骨と頭蓋骨が横たわり、いっそうさびれた雰囲気がした。
林道へ降り立つと落岩橋の上に30cm程積雪があってギョッとする。しかしそれは橋の上だけであった。アサハギ谷林道はもう溶けている。橋から100mほど先で路肩が崩壊している。一月には雪庇が出ていてよく見えなかったが、かなり危ないことになっている。林道には夥しい大小の石が散らばっていた。落石が頻繁なのだろう。小谷との出会いは大きなデブリが道を塞いでいる。そういう場所が数箇所あった。谷の対岸の急斜面でガラガラ音がするので視線をやるとシカが四頭トラバースしている。人間が登れるような斜度ではないが、さすがに野生動物は敏捷なものである。
落石の巣。アサハギ谷林道から霊仙山 谷の斜面にひっそりとフクジュソウ 除雪された保月への道
右手に霊仙山が見えている。曇り空の割にははっきり見える。前方でまた落石の音。しかし不思議なことに自分に当たる気が全くしない。根拠は何もないが、宝くじも全然当たらないことになっている。送電線の下に来た。雪がなくなった斜面を見下ろすが、やはり道らしきものはない。ズルズル滑り下りると、下流数百メートルで不気味な落石の音。全然収まらず対岸北斜面から雨あられと石が降り注いでいる。やはり雪消の時期は怖い。
適当に対岸に取り付いてしばらく登ると、フクジュソウに出くわして驚いた。花見に来たのだから驚かなくてもいいのだが、意外な場所で見るものだ。しかしそこ一箇所だけで、似たような他の場所には全然なかった。写真を撮っていると、背後でゴッという鈍く重い音が響いた。林道の舗装の上にかなり大きな石が落ちたようだ。さすがに少し心配になる。ヘアピンの対岸道路に這い上がると、汚れた雪が壁になっていた。こんな山奥にも除雪車が入ったようだ。
前回足の抜き差しに難儀した道がすっかり乾いている。嬉しくて調子にのって大またで歩いていて、ふと思い出した。保月まで行ってしまったらダメだ。今日は鍋尻山東尾根から登る予定。位置を確認してすぐ林道を離れ、北側の斜面に取り付き、25000図の671標高点を目指す。一面の植林で少しがっかりだ。見上げるような角度ではないが、直登はしんどい。ヨレヨレと仕事道を斜行しながら登る。高度が上がると雑木が交じり、地面にはオニグルミの殻が沢山落ちていた。やがて前方が明るくなり、尾根の一角に這い上がった。
そこには素晴らしいコバが広がっていた。真ん中はやや凹地状で雪が浅く積もっている。地図を見ると ・671ではなく、その南の650mの等高線に囲まれた場所らしい。ちょっと休憩せずにはいられない場所だ。腰を下ろしてお茶と行動食をとる。静かである。先日ネットで買った素焼きのオカリナを持ってきたので、ちょっと吹いてみる。まだ指がなじまない。山では室内のような反射も残響もなく、すべて音が吸い込まれ、直接音だけが聞こえる。ごまかしがきかず、隠れもなきヘタクソさが露見する。イヤになってすぐやめた。
北へいったん下るとまた植林になり、雪が深くなって靴の中に進入した。しょうがないので面倒だがスパッツを着ける。鞍部右手の小高いところがP671だ。落葉期なのでそこそこ霊仙山方面の景色が見えた。杉の木には弓の的のような物体がいくつか取り付けてある。いったいこれは何なのだろう。
671南のコバで休息 謎のマト。矢が刺さった跡はない。何これ? エンジンの給排気バルブに見えませんか
西へ続く尾根は快適そのもの。楽園をシカが走る。徐々にカレンフェルトが現れ、カルストの山らしくなってくる。ヤブがないので日当たりもよく、フクジュソウがありそうな匂いがぷんぷんとする。しかし不思議なことに花の類は何もない。次の700m等高線で囲まれた細長い場所は絶好のテン場となりうる。まばらな雑木の間に御池岳がよく見える。落ち葉とカレンフェルトが醸す雰囲気で心が安らぐ場所だ。
あとで地図を見ると廃道となった河内と保月を結ぶ山道はここを横切っている。その痕跡はあったのかなかったのか。気付かずに通ったので分からない。
ここを下りるとほぼ真西へ山頂を目指す尾根の登りとなる。また植林が現れた。中途半端に潜るのでけっこう厄介だ。今頃持ってくるわけもないが、ワカンがあれば楽だろう。雪の少ない南側を歩くが締りがないので、北側の深くても固い場所のほうがかえって楽かもしれない。やがて潅木のヤブと残雪とカレンフェルトが、三者一体となって進路を妨害するようになった。苦しいがこの雰囲気は山頂が近い証拠だ。最後まで続いたヤブを抜けると、ようやく山頂に着いた。
尾根から見る御池岳 二つ目のコバ 右手前地蔵山。その奥高室山。左ザラノ
誰もいないが比較的新しい単独者の足跡があった。たぶん昨日のものだろう。「人体部分名の山シリーズ」と書かれた大阪の人のプレートがぶら下がっていた。なるほど「尻」がそれに該当するのか。私はこういう登り方をアホらしいと思うが、別段他人に害を及ぼすことではないので当人の勝手である。
霊仙山、男鬼山塊などが見えているが、残念ながら彦根の町や琵琶湖は見えなかった。6年ぶりの山頂は花もなく数十センチの残雪があり、冷たい風が吹いて寒々とした雰囲気だ。風裏を探して昼食にした。
下山は保月方面への登山道をたどる。歩き始めたら小雪が舞ってきた。冬と春のせめぎあいか。南側が開けた場所でパノラマ写真を撮る。急斜面になるとフクジュソウが現れた。そうだ、今日は花見に来たのだった。この時期になるとどこのHPもフクジュソウ写真のオンパレードで、少々食傷気味である。「毎年同じことをして他に芸はないんかい」と思うが、こうして自分もしゃがみこんで写真を撮っているのが笑える。帰ってパソコンで見ればやはりしょうもない写真になっているのだろう。しかしこの精一杯光を捉えている姿、発光するがごとくまばゆい黄色を見れば撮影したくなるのはやむを得ない。
まばゆい黄色の光を放つフクジュソウ 保月の神社 廃村でも萱葺きは珍しい(手前は田の雪)
下山後、保月の神社に参拝する。冬は無人のはずだが道路や寺社の境内はきれいに除雪されている。このまま林道を帰れば楽であるが、せっかくなので1月に断念した地蔵山(日山)へ登ることにした。この山はガイド地図に登山道の線がない。集落南の尾根から登れるだろうと思う。道があったので南へ入るとそこにも人家があった。導水管が敷設された谷があったので堰堤を越して登ってみた。残雪で苦労する。やはり尾根に乗り換えようとタイミングを計るが、容易に上がれる場所がない。仕方ないので急な雪面をキックステップで這い上がった。ぶっ倒れそうに息が切れた。
尾根はヤブっぽいが谷よりはかなりましだ。暑くなってきたので上着を脱いでデポする。マツやアセビ、イワカガミがあって南部の山を思わせる。傾斜が急になるとシャクナゲのヤブにつかまった。北部の山とは思えない。すでに十分疲れているので、このヤブは堪えた。やがて岩とシャクナゲのピークにたどり着いたが、ここは地蔵山東峰というべきピークで山頂ではない。鍋尻山が間近に大きい。西へ向かうとすぐ地蔵山(日山)へ着いた。
ササと樹林の中に「日山763m」と書かれたプレートがあった。25000図では750m以上読み取れないが、何を根拠に標高を書いているのだろう。この冬枯れの時期にして殆ど展望はない。夏は推して知るべし。登頂記念に山には迷惑だろうが、再度オカリナを吹く。鍋尻の左肩に僅かに真っ白な山が覗いている。金糞岳であろう。紫頭巾のヒラヒラ目印が北の尾根を降りているが、往路に上着を置いてきたので追いかけることはできない。東峰へ戻る。ヤブの端へ出ると烏帽子・三国方面の展望がある。
地蔵山から見る烏帽子岳、三国岳、焼尾山 保月集落を見おろす
往路を戻り、上着を回収してそのまま尾根を辿る。チラリと残雪の集落が見おろせる。車が一台道路にいた。元住民だろうか。集落に降りずに尾根を歩いていたら墓地に出くわした。供えられた花がすべて真新しいので驚いた。この連休は彼岸なので、先ほどの車は墓参りだったと思われる。先祖伝来の土地への愛着を思う。当然ここから集落へ下りる道があったので利用させてもらう。
アサハギ谷林道から谷へ降りるショートカットは止めにして、そのまま良い道を帰る。もう悪路を歩く気力がない。ただし、かなり遠回りになる。このヘアピン北側の道は日当たりが良いのでデブリも落石もない。ゆるゆると下っていくとせせらぎの音がしてきた。下流は伏流であったが、この下は水流があるようだ。どんな谷か見たいので半端な場所ではあるが、やはりショートカットする。下りてみるとあまり良い渓相ではなく、渓魚はいそうもない。対岸の登り返しは一転して雪が多い。林道も残雪と落石だらけである。暫らく進むと50cm角くらいの大きな石が落ちていた。行きに聞いた不気味な音はこれだったのかもしれない。当たらないとは思えど、この道を歩くのは落ち着かない。ヘルメットが欲しい。宝くじ、宝くじと唱えながら歩く。
ようやく落岩橋(この名前も怖い)にたどり着いて気が楽になる。最後の登りで五僧を目指す。大した標高差はないが、疲れているのでしんどかった。やがてこの五僧を車で越えることができるのかと思うと嬉しいやら悲しいやら。やはり悲しいほうが大きい。最後に峠で大休止して名残を惜しんだ。