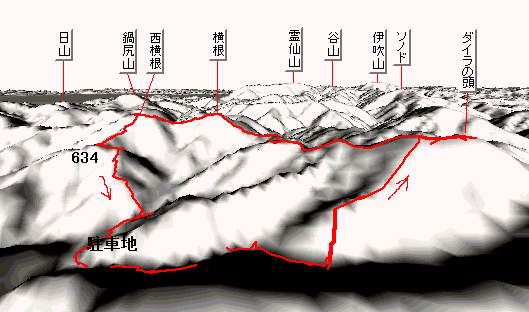ダイラの頭と横根 07.05.13
前夜までどちらに行こうか迷っていた。いや当日さえ迷っていた。例の花の確認に例の山へ登るか。または横根にするか。横根は10年来行こうと思って、未だ行けていない不思議な山。優先順位が低いと、結局いつも後回しになる。しかし思い切らないと生涯未踏になりそうだ。それとダイラの頭にも用があるのでセットで登りたい。でもやはり例の花も見たい。優柔不断で煮え切らないまま出掛ける。
晴れの予報だったが上空は重い曇天だ。結局例の山にする。黄色い絨毯の上で、白装束の踊り子たちのお祭りだ。登山道と無関係の場所を登って例の花の様子を窺う。驚いたことに葉っぱしかない。散ったあとなのか、これからなのか不明だが、そんなに大きく時期は外していないだろう。これは面妖な・・・ 。○花一朝の夢を見ることも叶わず、これから如何に身を処すべきか。他の生育場所をあたるか、あきらめて横根へ転進するか。しばらく思案して、余力のあるうちに下山することにした。途中で高級カメラを提げたI氏とバッタリ。「他のほうで数株咲いてましたよ」 とのこと。やや悔しいが、横根を質に入れてでも見たいというほどの思い入れはない。今日は縁なきものとあきらめる。
場面変わってR306、百々女鬼橋から林道に入る。百々女鬼とはすごい名前だが、この谷には何か謂れがあるのだろうか。女の鬼って、どういうふうなのか見てみたい気もする。林道は乗用車でも通れるが、未舗装なので水溜りが厄介だ。しかも嫌なことに小雨が降ってきた。やがて材木谷の分岐に着いた。林道は更に続くが、下山点をこの付近に予定しているので駐車して仕度をする。ウォームアップは既に済んでいるが、準備運動にしてはちょっと疲れすぎた。
黙々と鳴川谷の林道を歩く。道端には伸びすぎたイタドリがたくさん生えている。誰もいないだろうと思っていたら犬連れの登山者と出会った。犬は正視できないほど片目の周囲の皮が剥げている。怪我か病気か知らないが、物言わぬ動物は余計気の毒に思う。登山者はダイラの頭に登ると言う。私と同じだが、休息しているので先に行く。当初鳴川谷右岸尾根を登ろうかとも思ったが、取り付くタイミングがないまま林道終点まで来てしまった。ところがこの先、谷通しとなる地形図破線の道らしきものがない。登山靴でこのまま進むことはできない。否応なく当初予定していた右岸尾根へ強引に上がることになった。
すごい傾斜でヤブだらけだ。気が付けばいつもの通りの山登りスタイル。稜線漫歩や花園鑑賞もよいけれど、真の鈴鹿登山道(修行の道のほう)の真髄はヤブコギにある。私には花もなければモミジもないゴンタクレ尾根やヘッポコ谷がお似合いだ。
常緑のヤブと足場の悪い急斜面、それに悪天が加わればなお良い。ヒルも出れば申し分ない。本当はそんな場面はあまり好きではないが、向こうから勝手にやってくるから仕方ない。こういうときはありがたや、ありがたやと唱えながら登るのである。
格闘の末、尾根芯に這い上がる。今までよりは歩きやすくなった。相変わらず急傾斜とはいえ、岩の角が立っているので良い。宇賀渓付近の不良尾根と似ている。大きな岩峰を巻くと、その突端に出た。松がある。晴れてはいないが、よい眺望だ。西に高室山と西横根が見えている。まずまずの尾根だと思って登っていたら、突然前方が明るくなってきた。尾根芯だけ木が伐採されて白骨化している。営林署の杭もあった。両側は素晴らしい二次林だが、通路だけがぽっかりと開いている不思議な光景だ。この調子では隣の548の尾根も同様だろう。開けているといっても、裸地を好むアセビやユズリハが茂りつつある。傾斜は緩む気配もなく、もうひとつの山の疲れも重なってよれよれ状態で稜線へ出た。
岩峰より高室山と西横根 天候は良くない 突然尾根に切り開きが
到達点はダイラの頭のすぐ西のピークである。以前ダイラの頭へ来たときは、そのまま真北の尾根へ向かったので、この地点は初めての場所のはず。風情ある林の中にユキザサが群生していた。何と清々しい白の絨毯だろう。花は雪の結晶のようだ。
横根方面は左折だが、用があるので右折してダイラの頭へ登る。あることを確認してからまた戻る。横根へ続く道は登ってきた尾根と同じくすっかり伐採されていて、木の残骸と岩屑が白く延びている。これまた同じくユズリハとアセビが多い。ユズリハは今、名前の由来となっている葉っぱの更新中で、新しい若葉が輪生している。毘沙門谷側の目が覚めるような新緑には心が洗われる思いだ。
清々しいユキザサ 切り開かれた県境尾根と横根 遠景鍋尻山
西へと続く縦走路はアップダウンを繰り返す長い県境稜線である。これから登る横根が見え隠れする。背後は鍋尻山だ。やがてこの標高にしては珍しくブナがあった。すらりと背が高く立派な木だ。柔らかい半透明の若葉を空いっぱいに付け、緑色した木漏れ日を地上に振り撒いている。渋い色のヤマツツジ、オトコヨウゾメの可憐な花、タカノツメの素朴な花など、気をつけて見れば様々なものがある。ウグイスが盛んに鳴くので口笛で返すと、通じたのか警戒しているのか知らないが声が着いてきた。
いきなり横根の突峰が眼前に聳えて見えた。あれを登るのかと思うと気が萎えた。切り開きの道らしきものはほぼ垂直に見える。地図を見れば錯覚であることは明白だが、突撃する元気もないので、ここらで昼としよう。誰も来ないとは思うが、一応道を避けて奥の林に平坦地を探して腰を下ろす。そういえばあの犬連れの人はどうしたのだろう。あとからエアリアマップを見ると、鳴川谷の登山道は途中から三国岳西尾根を通っている。なるほど、地形図しか見ないから知らなんだ。私はめちゃくちゃな所を登ってきたようだ。でもちゃんと目的地にいるからいいだろう。コシアブラの若葉を一枚ちぎってお湯の中を泳がせ、ヒル避けに持ってきた塩を少し付けてかじってみた。特有の味はあるが、もう遅いのでアクが強くてだめだ。
オトコヨウゾメの小さな花 背の高いブナ 天高く聳える横根
食後、息も絶え絶えに急登を登る。鳴川谷右岸尾根と似たようなものだ。この切り開き道のお蔭で背後の景色がドラマチックに変化していくのが分かる。猫の耳のような三国岳とダイラの頭が徐々にせり上がってくる。東横根のピークに上がるとイワカガミが咲き乱れていた。しかしどれも痛んでいる。時期は遅くないと思うが、木曜、金曜と吹きまくった狂乱風に揉まれてしまったのだろう。風ウラには元気なものもある。特段の感慨もない山頂だが、少し西へ進んだところになかなかのブナ林があった。メジャーを出すほどではないが、胴囲5〜6尺クラスのブナが林立している。これだけは是非とも伐採しないでいただきたい。不思議に印象に残る場所だった。
見ごろのイワカガミ 心地よいブナの林
ここからいったん鞍部へ下り、横根三角点(西横根)へ登り返すことになる。なかなか枝振りのいいカエデが一本。西横根東面は植林が崩壊したのか、裸の荒地になっている。お蔭で烏帽子・三国・御池方面の展望は最高である。天気もようやく良くなってきた。子どもに山の絵を描けと言えば、鎌ヶ岳のような姿を描くだろう。その点御池岳は聳えているというより、寝そべっているような山体の面妖な山である。その図体の大きさのまま三角錐であったら、1500mを超える山になっただろうか。ただ、そうなればテーブルランドも池もないわけだが。
三角点に近づくとシャクナゲが現れ、散り残った花が付いているものもある。そういえばたろぼうさんのサイトに横根はシャクナゲが見事だと書いてあった。しかし残念ながら時期を外している。GW頃が見ごろなのだろう。三角点はあまり展望もない素朴なピークである。例の山の疲れか、体力が衰えたのか、更に最高点往復の気力はない。険しい地形と聞くこの先は冬の楽しみに残すとして、今日は下山しよう。それに左の膝関節が痛み出している。
東横根を振り返る 一木だけ残っていたシャクナゲ
地形図には三角点から南に尾根が延び、634標高点で左右に分かれている。言わばミニT字尾根である。これを左折して駐車地に帰ろうという計算である。最初はすごい傾斜のカモシカ落としだ。木につかまりながらズルズルと落ちていく。イワカガミが多い。我慢すれば、すぐに尾根らしくなるだろうと思っていたら、ついに絶壁で行き止まりになった。どうやら外したようで、左に見えるのが本物らしい。登り返してから乗り換えるのが安全だが、骨が折れる。懸垂用具もないので、細引きにつかまって恐々谷に下り、そこから苦労して南尾根に攀じ登った。とんだヘマをして残り少ない体力を使ってしまった。
かなり前にこの尾根も伐採が入ったようだが、もうアセビが伸びすぎて歩きにくい。途中で展望のよいところがあった。眼前の634、その東のピークの背後に三国岳が見えている。いったん鞍部に下り、634T字交点に登りつめ、さっきまで居た横根を仰ぎながら一休み。暑くも寒くもなく心地よい季節だ。
東へ進み、ピークを巻くように右折するとヤブだらけになってきた。それにしてもこの山域はユズリハが多い。シャクナゲも出てきた。枝は引っ掛かるし、ひざは痛むし、高度はまだまだ高い。ありがたや、ありがたや。地形図で見るとそんなに距離はないが、下山するまで随分長く感じた。山本勘助のようにビッコを引きながらバタバタと不恰好に下る。下部は間伐材が放置してある植林帯で、痛む膝で乗り越えるのに難儀した。最後は川べりの高い土手に出てしまって下りられない。ありがたや、ありがたや。頭も手足も総動員して河原に下り、カキドオシやウマノアシガタが咲く対岸の林道に這い上がった。
手前中央はミニT字尾根東ピーク
遠景中央三国岳
左端ダイラの頭 その右斜面が登った尾根
(西横根南尾根から撮影)
さて例の花を捨ててまで転進した甲斐はあったのか。これはあった。鈴鹿のなかで自分の未踏の頂上にも立ったし、懸案の確認事項も済ませたし、想定外のブナ林もあった。そして何より有難いルートも体験させてもらった。あとから「鈴鹿の山と谷」を見れば、鳴川谷通しの破線道は崩壊していると20年も前に書かれていたのだ。犬連れの人が休んでいた場所が西尾根登山道の取り付きだったのだろう。スタコラと林道を直進する私を見て 「あいつ、何処へ行くんだろう」 と笑われていたのかも知れない。
人遠く、水草清き所にさまよひありきたるばかり、心慰むことはあらじ
(人里遠い、水や草木の美しい所をさまよい歩くぐらい、心慰む事はない)