冬のクラシ北尾根 09.02.22
国破山河在。日本の経済が奈落の底に落ちようとも、故里の山の佇まいに変わりはなかろう・・・と思ったが今年は雪まで不景気なようだ。8日に登った釈迦ヶ岳は稜線にしか雪がなかった。その後若干ではあるが雪の補給があった。頼りない淡雪ではあったが、一応山は白く見える。長期予報を見る限り、今日を逃しては鈴鹿の雪山はない。
以前から雪の付いたクラシ北尾根はどんなものか興味があった。北尾根は取り付きが山深く、稜線はスリル満点。その上に雪があれば歩き甲斐があるというものだ。今日はそれにしよう。ただ冬に登ったというには積雪が物足りない。不足分は自分の未踏のルートを加えることで穴埋めしようと思う。
昨夜は晴れて冷え込み、今朝は下界でも氷が張っている。良いコンディションだが、日中は気温が上がって雪が腐りそうだ。しかも晴れのち雨の予報。こういうときは早発ちに限る。しかし往々にして思考と行動は一致しない。予定より30分遅れて朝明に着く。大駐車場は蟻一匹いない(ルーペで確認した訳ではないが)。橋を越えると3cmほどの積雪と薄い氷でクルマがよく滑る。帰路も考えて砂防学習堰堤に駐車する。
歩き出しから雪があるというのは冬らしくて気分がよい。しかしサラサラの数センチの雪で、実質は何の抵抗もない。先日張り替えた新品のソールが心地よい。曙滝の付近は例の豪雨で様相が変わっていて、ちょっと戸惑う。伏木谷も荒れたなあと思いながら歩いていると、周囲の風景に見覚えがない。またやってしまった。私は白一色の世界では登山道を外すことがしばしばだ。かまわず歩いていくと二進も三進もいかなくなった。
仕方なく急な雪の土手を登って尾根に逃げた。こんな所で早くもピッケルのお世話になるとは想定外だ。シカの足跡を辿ってトラバースしていくと、ようやく登山道に出た。ヘロヘロになって中峠へ着く。後で軌跡を見ると中峠東のガレマーク帯に入り込んだようだ。こんなところで消耗している場合ではないのだが、まったく恥ずかしくもお粗末な話だ。
 中峠から西は若干雪が増えるが、下りのことゆえさしたることはない。この通いなれた道さえ、白一色の中では記憶が曖昧になることがある。大トロ橋に着くと、聞いていた通り、巻き道の案内板ができていた。しかし目と鼻の先にある地点へ行くのに、わざわざ下りて渡渉するなどバカらしい。安全より安楽である。深夜の泥棒のように、抜き足差し足忍び足で渡る。右に傾いているのがスリルである。大トロ橋を渡るのはこれで最後にしようと毎回思う。今日も同じことを思った。 (写真:水晶谷からクラシ)
中峠から西は若干雪が増えるが、下りのことゆえさしたることはない。この通いなれた道さえ、白一色の中では記憶が曖昧になることがある。大トロ橋に着くと、聞いていた通り、巻き道の案内板ができていた。しかし目と鼻の先にある地点へ行くのに、わざわざ下りて渡渉するなどバカらしい。安全より安楽である。深夜の泥棒のように、抜き足差し足忍び足で渡る。右に傾いているのがスリルである。大トロ橋を渡るのはこれで最後にしようと毎回思う。今日も同じことを思った。 (写真:水晶谷からクラシ)
これは自己責任の愚行であり、決して推奨しているわけではないことをご賢察頂きたい。
橋を渡った地点からそのまま西へ斜面を登る。これが冒頭に書いた未踏のルートである。オゾ谷左岸尾根(高岩東尾根?)の支尾根である。ともかく登っていけば作の峰と高岩の鞍部に出るはずである。ヤクザな尾根でない限り、積雪期はオゾ谷を登るより楽かも知れないという期待もある。
取り付きの支尾根は本尾根に上がるために掛けられたタラップのような存在である。痩せた尾根芯にヒノキやアセビのヤブがあって歩き難い。しかし激ヤブというほどのものでもない。岩の台座に囲まれた二俣の大ヒノキがあった。幹が途中で下向きになり、輪を描いてまた上に伸びるケッタイなヒノキもあった。どういう原因があるのだろう。ヤブが切れて展望のよいところで小休止してパンを食べる。本尾根との接続点は急登であった。


台座付きヒノキ 何があったのだろう
本尾根は勾配は緩いが小ピークが幾つもある。高岩や作の峰が樹間からチラチラ見える。雪の抵抗は大したことはないが、それでも無雪期よりは消耗の積み重ねとなっていく。雪でハッキリとは分からないがピークを巻く杣道が見られず、この尾根は山仕事で用いられていなかったようである。登山者も使わないのか、テープ類も皆無である。やがて高岩北のコルが見えてきたので尾根を捨ててトラバースした。ブナの樹を越えて鞍部に到着。ワサビ峠に似た良い場所だ。御在所方面がよく見える。バリエーションながら人の通る道に出て、なぜかほっとする。



傾斜の緩いオゾ谷左岸尾根 尾根から見る作ノ峰 高岩と作ノ峰のコル
高岩への登りは短いながらもしんどい。久々の山頂には新しいプレートが付いていた。しかしまだ奥村さんのプレートも残っている。こちらはマジックが消えかけて読み辛い。以前地図もろくに見ずに高岩から直進してオゾ谷に下りてしまい、ワサビ峠へ登り返すのに大汗をかいたことがある。今回は学習効果で真西へ右折する。ズリズリと雪の斜面を下りていくとワサビ峠に着いた。ようやくワサビ峠かというのが実感である。大トロからけっこう時間を喰ってしまった。オゾ谷の登山道から上がったほうがやはり楽かな。ここにも新しいプレートがあり 「2008・12・07京都北山ウォーク by ○○○○○」 とある。日付はまだついこの間だ。
さてここからがクラシ北尾根の核心部。痩せ尾根岩稜、シャクナゲ地獄、急登、急降下とジェットコースタームービーのような尾根である。しかし記憶力が弱いので、前回(8年前)何がどういう順番だったか覚えていない。前回どころか今回すら記憶が危うい。メモをとるのも面倒、ICレコーダーで実況録音しながら歩くといいかも知れない。
峠からいきなりの急登。雪が腐りかけてきて下の腐葉土とともにズルズル滑り、これは難儀だ。アイゼンを履く雪質ではないが、効果はあるかもしれない。一日中担いでいるだけなのもマヌケなので、ここで使おう。やはり土アイゼンは効果があった。このあと極端な岩の痩せ尾根で、岩が風化して下に穴が開いている。前回この穴を見たかどうか覚えていない。これを渡って振り返るとマツを前景に釈迦ヶ岳が絶景である。



静寂のワサビ峠 釈迦と松 帰路にとったP900の尾根と御在所岳
ボロボロの岩を渡る場所は左を巻いてシャクナゲ地獄につかまった記憶がある。今回は木の根につかまって右を巻く。高度感があっていい場所だ。定かではないがジャンダルム(緑ちゃん命名)と呼ばれる怪峰が見えたのはこの付近だったか。奥穂のジャンに比べれば毛だらけではあるが、山水画の趣がある。シャクナゲは左に張り出した雪庇に埋まっているようで、上を歩ける。
ときどき岩稜をアイゼンのまま登る。岩と雪のミックスでアルプスの訓練のようだ。ピークから次のピークを眺めると、こんな所を登れるのかという急傾斜である。高度が上がってきたので二層の下の雪が凍っている場所もあり、アイゼンとピッケルが大いに役に立つ。やはり冬は必携だ。この尾根は高度感があるが、木があるだけ恐怖が和らぐ。岩だけだったら心胆寒からしめる場所もある。冬期の下りには使いたくない尾根である。



クラシジャンダルムと呼ばれる突峰 水晶岳とオゾ谷 高岩・作ノ峰・塔ノ峰を振り返る
夢中になって遊んでいるうちに傾斜がなくなり、太くはないもののブナの林になった。三更月下無我に入る境地、夜中ではないが何かに集中していると下界の憂さを忘れるものである。周囲のブナは百年後が楽しみだ。この付近はアイゼンよりもワカンが欲しくなるが、なくても困るほどではない。クラシと越百岳の三叉路を越えると視界がパッと広がり、雪原のパノラマになる。ところで越百岳の出典は何? その先の木に彫ってあるだけで他の根拠はなさそうである。所々土が見えるその丘に立つ。冬のクラシに臥薪嘗胆のKASAYA氏がリベンジに来ているかもと思ったが、イブネ方面から銚子まで四望人無く、無論トレースもない。


クラシ目前のブナ林 クラシから銚子を眺める
風が強い。御在所、鎌方面は見えるが、北の御池はぼんやり霞んでいる。雨が近いのかも。夕方には所用もあるし、雪の北尾根という目的はもう果たしたので、散歩はやめて帰ることにする。おっと昼食がまだだ。帰路に合わせてクラシの標識の向こうに下りて昼とする。今日はコンロなし。テルモスの湯でアサリのみそ汁を作り、お握りを二個食べる。簡素にして手早い。ここからP900の尾根を帰ろうと思う。何度か登ったが、下りに使うのは初めてである。私の場合、ボーっとしてたら外すこと請け合いである。
このルートは下降点からして判然としない。左へ振るとオゾ谷コースになってしまう。何とかコンパスで尾根に乗るが、もうひとつのポイントは980m付近での右折である。地図と高度計とコンパスを確認しながら慎重に下る。北に向きを変えてからひとつ尾根らしいものを見送って進む。高度計はまだ1000mを割っていないからである。しかしどうもさっきの分岐がくさい。真っ直ぐ行くと逆落としである。戻って東へ折れるが、これが正解だった。高度計はあまり当てにならない。それとも地形図がおかしいのか。
やがてP900手前の見事なブナが林立する鞍部が見えてきた。しかしその手前のブナが目に留まった。見送るには太すぎるが、残念ながらメジャーを持って来なかった。細引きで簡易測定するが、胸高で約250cmあった。何で今までスルーしてきたのだろう。この木は胸高より上で更に太くなるので貫禄がある。また正式に測りに来よう。鞍部の数本のブナは50年後の楽しみだ。登り返したP900は昨年御池庵で泊まった翌日に皆で来て、のりや君が記念撮影した場所だ。あの時山登りはできなかったが杣人さんはまだ元気だった。



250cmのブナ 同じブナを真横から 鞍部のブナ林
尾根の先の二俣を右手にとり、クラシ谷出合に下り立った。その後タケ谷の登山道で帰る。タケ谷三叉路でようやく人の足跡を見る。付近の平坦地をスノーシューで歩き回ったようだ。ツボ足で不足はないが、買ったばかりで嬉しかったのだろうか。根ノ平峠を経て朝明に着いたのは4時半頃。最近ずっとお気楽山行を続けていた。久しぶりの長丁場のせいか、ふくらはぎが張った。


寒々とした愛知川 河畔の美しいツララ
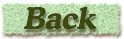
 中峠から西は若干雪が増えるが、下りのことゆえさしたることはない。この通いなれた道さえ、白一色の中では記憶が曖昧になることがある。大トロ橋に着くと、聞いていた通り、巻き道の案内板ができていた。しかし目と鼻の先にある地点へ行くのに、わざわざ下りて渡渉するなどバカらしい。安全より安楽である。深夜の泥棒のように、抜き足差し足忍び足で渡る。右に傾いているのがスリルである。大トロ橋を渡るのはこれで最後にしようと毎回思う。今日も同じことを思った。 (写真:水晶谷からクラシ)
中峠から西は若干雪が増えるが、下りのことゆえさしたることはない。この通いなれた道さえ、白一色の中では記憶が曖昧になることがある。大トロ橋に着くと、聞いていた通り、巻き道の案内板ができていた。しかし目と鼻の先にある地点へ行くのに、わざわざ下りて渡渉するなどバカらしい。安全より安楽である。深夜の泥棒のように、抜き足差し足忍び足で渡る。右に傾いているのがスリルである。大トロ橋を渡るのはこれで最後にしようと毎回思う。今日も同じことを思った。 (写真:水晶谷からクラシ)
















