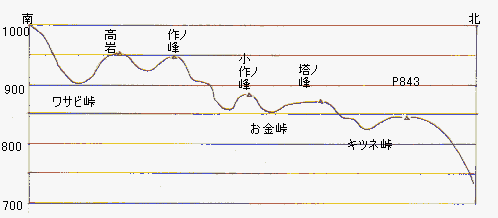クラシ北尾根縦走 00.11.26
![]()
クラシ北尾根とは分かりやすく言えば、谷尻谷と愛知川の間の尾根である。今日はそのうち、843独標からワサビ峠までを歩いた。
8:05朝明発。8:32ハト峰通過、9:03ヒロ沢出合着。この間超メジャーコースゆえ描写省略。三週間ぶりの山で体がやや重い。
ヒロ沢出合には遭対協の真新しい看板があった。水量は平水。しかし安全に飛び渡れる自信がないので、少し上流へ進む。まあここならばという場所で石を飛んで、対岸へ渡った。しばらく左岸を進むと段々と高巻になってくる。
チョロチョロ水の滝で水を1リットル3分ばかりかかって補給。これが狐峠へ至る谷だと思って、登りにかかる。岩の上は落ち葉のどっさり堆積したふかふかの谷である。朴の葉が白い腹を見せて大量に落ちている。どうしてみな裏返しに落ちるのか不思議である。
そのうち段々と急になってきて、上部は木につかまっていないとズルズル後退してしまう。仕方ないのでジグザグを切って進む。やがて前方が明るくなり、尾根上に出た。高度はたった720m。谷を間違えてしまった。狐峠どころか、P843の遥か手前である。まあいいか。どうせ峠から独標までは戻るつもりだったから。
それはいいが、どうにもならん薮尾根で閉口する。時間ばかり食って進まない。9:55下部が岩小屋になった大石に到達。このあたりから、キャットフードの袋を裂いて木にくくり付けた目印が頻繁に出てくる。この人よほどの猫好きか。それとも山でキャットフードを食べてるのかしらん。
10:15やっとP843到着。花崗岩の細長い場所で、東の展望が開け釈迦ヶ岳が妙な形で見えている。西には樹間から銚子ヶ口が見えているが、完全に西の展望が開ける場所は無い。花崗岩の東側はすっぱり切れ落ちていて、ちょっと怖い。ここで休憩。
下るとすぐ狐峠である。ほんの小さな乗越しで峠という感じはしない。逆コースの場合、ここから愛知川(神崎川)へ降りた方が得策である。この谷には名前が無いがキツネ谷で差し支えないだろう。
狐峠から急登で小ピ−クへ。塔の峰かと思ったら、まだ先だった。塔の峰はちょっとした広場になっていて雰囲気の良いところである。岩にスプレーで97.10.10と書かれていた。この真下にお金明神があるはずだが、樹林で見えない。西の展望も相変わらず完全ではないが、銚子ヶ口から大峠にかけてのラインが何とか見える。。葉の茂る季節だったら全く見えないと思う。右手から谷尻谷の沢音が聞こえる。
 細長い塔の峰を下るとお金峠へ出た。お金明神10分の看板あり。オクムラと書かれている。大分前に北谷尻谷へ釣りに入ったときこの辺りを通っているはずだが、今となってはどこを通ったか記憶なし。峠らしきものはこの前後に幾つもある。このあとはぐっと道が歩きやすくなった。キャットフード氏の目印はとうに消え、赤テープが巻かれている。大きな杉があり枝はなぜかみな西を向いている。
細長い塔の峰を下るとお金峠へ出た。お金明神10分の看板あり。オクムラと書かれている。大分前に北谷尻谷へ釣りに入ったときこの辺りを通っているはずだが、今となってはどこを通ったか記憶なし。峠らしきものはこの前後に幾つもある。このあとはぐっと道が歩きやすくなった。キャットフード氏の目印はとうに消え、赤テープが巻かれている。大きな杉があり枝はなぜかみな西を向いている。
峠から小ピークを越え(気付かなかったがこれが小作の峰)また峠状へ。南を見ると大きな小山(変な言い方だが実際そんな感じ)が立ちふさがっている。花崗岩が積み重なっている。これが作の峰だろう。
花崗岩をよじ登ってピークへ出たと思ったら、その先にまだピークがあった。それが本当の作の峰。気合を入れなおして登る。11:37到着。オレンジのプラスティックの札が下がっている。「作ノ峰946m伊ト」。作ノ峰は948m独標だから6は不思議。平たいがそんなに広くないピークである。この下の谷が古い地図ではお金谷になっている。
 下ったらすぐ、二重山稜になった所に出た。間の凹地は落ち葉の絨毯広場で素晴らしい場所だ。高岩で昼食の予定だったが、あまりに素晴らしいのでここでお昼とする。風も無く、木漏れ日のあたる広場は暖かくて快適である。朝汲んできた水で塩ラーメンを作る。沸騰するまで炊き込み御飯のおにぎりを食べる。おいしいなあ。小さな幸せってこういうことかな。雲南省茶葉のプーアール茶をたてる。静かだ。時折、残り少ない落ち葉が舞い降りてカサカサいうだけの静寂のひと時。オカリナを取り出して吹いてみる。へたくそでも誰もいないからいい。
下ったらすぐ、二重山稜になった所に出た。間の凹地は落ち葉の絨毯広場で素晴らしい場所だ。高岩で昼食の予定だったが、あまりに素晴らしいのでここでお昼とする。風も無く、木漏れ日のあたる広場は暖かくて快適である。朝汲んできた水で塩ラーメンを作る。沸騰するまで炊き込み御飯のおにぎりを食べる。おいしいなあ。小さな幸せってこういうことかな。雲南省茶葉のプーアール茶をたてる。静かだ。時折、残り少ない落ち葉が舞い降りてカサカサいうだけの静寂のひと時。オカリナを取り出して吹いてみる。へたくそでも誰もいないからいい。
名残惜しいが、12:30に出発。食後にこたえる急登一発で高岩へ。高岩といっても岩ではなく、土のピークだった。ここにも「高岩957m丹下」の札。「鈴鹿の山と谷」には地図にも本文にも1005mと書いてある。これは明らかに間違いで、西尾氏は50m等高線を読み違えている。樹間に見える作の峰と比べても分かることだ。この著書は大作だから、細かい間違いはしょうがないだろう。等高線からは950m以上であることは分かるが、札をつけた人は7という細かい数字をどうして割り出したのだろう。
高岩からは急降下。石を落としたらどこまでも転がっていく。それにしてもひどいと思っていたら、道を外していた。ワサビ峠遥か下のオゾ谷途中へ出てしまった。どうせ下るのだから近道になったのだが、どうしてもワサビ峠を通りたかったので、見上げるような急登を登り返す。こういうのをアホと言う。谷の左岸にテープがある。これは今日一番しんどかった。やっとこさワサビ峠へつく。なかなか峠らしい風情のあるところだ。御在所がよく見える。峠直前にも奥村氏他三名の看板あり。この連名は作の峰と高岩にあった名である。ということはすべて同じグループがプレートを付けたのであった。
 また急降下してオゾ谷を下る。谷へ降りてしまうと傾斜は緩い。滝もない。790mの二俣に鉄鉱石あり。その少し下の右岸に小さな洞窟発見。覗くと水がたまっていて奥が深そうである。ヘッドランプを取り出して再度覗く。光が届かないほど続いている。明らかに採鉱跡である。それにしても人が入るにはかなり狭い。更に下の右から小ルンゼが入るところに、石組みがあった。炭窯ではなく精錬用のものと思われる。
また急降下してオゾ谷を下る。谷へ降りてしまうと傾斜は緩い。滝もない。790mの二俣に鉄鉱石あり。その少し下の右岸に小さな洞窟発見。覗くと水がたまっていて奥が深そうである。ヘッドランプを取り出して再度覗く。光が届かないほど続いている。明らかに採鉱跡である。それにしても人が入るにはかなり狭い。更に下の右から小ルンゼが入るところに、石組みがあった。炭窯ではなく精錬用のものと思われる。
下流になるにしたがって地形的に歩きにくくなる。落ち込みが続くからだ。やがてトイ状からナメになってすだれになる美しい滝に出会う。右岸を慎重に下る。下から写真を撮ろうとして驚く。滝の釜の左に、先ほどよりずっと大きな洞穴が。これも覗いても奥が知れない。水が溜まっているのでウエーダーでも履いてヘッドランプをつけて探検したら面白そうだ。この谷は釣りで入り口しかやってないので知らなかった。1:55愛知川との出合着。あー、楽しかった。
この先は普通の道であり、不景気の折、電気代節約のため省略。