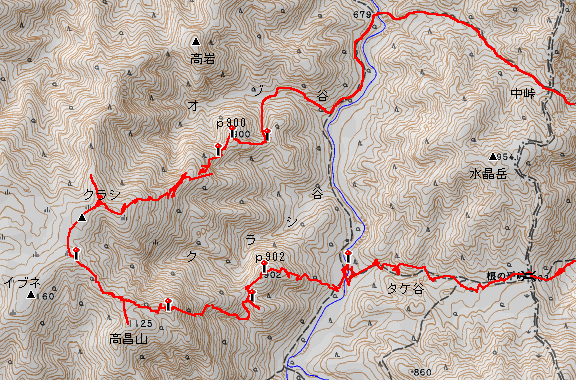錦繍のクラシ谷左岸尾根 04.10.31
今日は雨の予定だったが、昨夜の予報では急に降らないことになった。実際、部分的に微かな青空も見え、山肌はくっきり見えている。しかし昨夜の雨で河川は増水し、木の葉やササには水滴がたっぷり付着している。
クラシはどこを基点にしても遠い山だ。まして日の短い秋は早発ちが肝心。7時ごろ朝明を出発。曙滝は景気よく水塊を落下させていた。伏木谷を離れて急斜面を上がると、紅葉に染まった釈迦ヶ岳が姿を現した。
しずくと汗に濡れながら中峠に立つ。西に見える銚子ヶ口の山裾には、愛知川から立ち昇った川霧が漂っている。しかし休息しているうちにそれは山全体を覆い、赤・黄・緑の段だら模様を隠してしまった。再び露に濡れながら愛知川に向かって降りていくと、時折り日が差してガスは晴れていった。朴の落ち葉が散乱する大瀞橋手前に出ると轟々と川の音がした。いつもこの橋を渡るのは気持ちのよいものではない。
左折してオゾ谷を目指す。登山道が本流に接近したところで河原に下りてみる。流れは強く、ササ濁りがでている。両岸の木々は色づき、今が最盛期だろう。黄色はシロモジ、タカノツメなど、赤はウリハダカエデ、モミジ、ツツジの類。しかしこの辺りは色の出る木がやや少ない。オゾ谷に入ると左岸に良い道が続く。ただ谷から離れているため、支流の分岐が分からない。750m過ぎの左支流に入りたいので途中から川沿いを歩くが、早く入りすぎてよけいな苦労をした。
この小支流はちょろちょろ水で足を濡らすこともなく、傾斜も緩くて良い登路になる。じきに稜線が見えてきて、あっけなかったなと思ったが、詰めは急登で汗を絞られた。コルはブナの木がある雰囲気のいい場所だった。クラシ谷対岸の紅葉を愛でつつ、しばし休憩。
ヤブのない美しい尾根を西へ向かうと、やがて以前から気になっていた900mジャストの標高点に登りついた。大きなブナが二本ある。西のブナ越しには色付くクラシ北尾根が見える。このピークは南北に広がりがあり、北へ行くとブナが数本並んでいる。そのブナの木肌は地衣類の紋様に味があり、周囲の紅葉とよく馴染んでいる。その背後、愛知川越しに見えるのは水晶岳か。下界にいては絶対味わえない異次元の世界だ。ここはいい。
オゾ谷支流から登ったコル P900のブナ(背後は水晶岳) 同
期待にたがわなかったP900を降りた鞍部には相次ぐブナのお出迎え。この辺りのブナは軽くひと抱え以上あり、逞しくも美しい。やはりブナは森の重鎮だ。あるとなしでは森の品格が違ってくる。黄金の黄葉は台風でやや葉が少ないが今が盛りだ。右手には北尾根にある高岩のピークが見えている。しかし高い山はガスに包まれつつある。
やがて斜面は傾斜を加え、シャクナゲの密ヤブになってくる。ここはヤブを避けて左の山腹をトラバースしていく。尾根の登りは方向を気にせず、高みを目指していけばいいので気は楽だ。ただし体はしんどい。再び尾根に戻るとオゾ谷側が切れ落ちていて緊張する。
P900西のコルから高岩 同場所のブナ クラシ直前のヌタ場
やがて緩やかな森になり、クラシが目前であることを告げる。ヌタバには大雨によって水が溜まり、臨時の池となって木々を映している。水平になる取掛かりにクラシの標識があるが納得できない。標高も違っている。まあこれは前にも書いたような気がするので止めておこう。三叉路にザックをデポして北尾根のブナを見に行く。。しかし標高が上がったためか、風当たりのためか、ここのブナ群は丸坊主に葉を落としていた。それでもやはり美しい風景だ。まだ若い木が多く、100年後には見事な森になるだろう。ここで風景を副食としてお昼にする。
もはや背を越すササがあった痕跡すら消えたクラシからイブネの平原を歩く。薄くガスがかかって遠景は見えたかと思うとまた消える。潅木帯を抜けて緩く登るとイブネ北端の標識。ここから高昌山(P1125)に向かう尾根に乗る。鹿の声が錦繍の森に吸い込まれていく。 「奥山に紅葉踏みわけ鳴く鹿の 声きく時ぞ秋は悲しき」 この和歌そのままの世界が眼前に展開している。ただ、今はあまりしみじみとした哀愁は感じない。
高昌山のコル下重谷側 同猪子谷側
二つ目の小ピークにザックをデポし、南の高昌山を往復。ここはピークよりも、その間のコルが絶品だ。東は緩やかな猪子谷の源流美。西には下重谷越しにイブネの大平原が天上世界のように浮かんでいる。そして落ち葉の地面は人為的かと思えるほど平坦である。ここにテントを張ってくれと言わんばかりだ。立ち去りがたい御伽噺の世界に別れを告げて、デポ地点から更に東へ進む。東西に細長い1100m等高線の地点に立つ。以前ここから南東の尾根に乗って小峠へ下りたが、今日は東へ下りてP902を踏む予定。ただ等高線の込み具合が尋常ではないのが気がかりだ。
下り始めると案の定サルのように木にぶら下がり、ストックを収納して手足を総動員する。枯れ木をつかんだらアウトだ。とても人間がルートにするような傾斜ではない。これも等高線からしてしばらくの辛抱だろうと思う。しかし一向に良くならず、ますます悪場の度合いが増してくる。目の前に谷が出てきた。これは外したと悟る。右へ振り過ぎたようだ。左へ振るとこれも黒い岸壁の谷で、とてもトラバースできるような地形ではない。仕方なく木の根、岩角をつかんで谷に下り、そのまま慎重に下降する。二俣に平らな場所があり、一息ついて状況を判断する。高度計と地形図から容易に現場が特定できた。頭上のピークがP902南の870mだ。
そのまま谷を下降すればすぐ愛知川だが、悔しいのでヘロヘロになりながら右俣を登り返す。870ピークは木がなければいい眺めだろうが、殆ど展望がなかった。尾根に戻ってまた登り、P902を踏んだ。クラシ谷を挟んだP900と同じような標高だが、こちらに目立ったブナはなく風情はP900に軍配が上がる(左写真)。そうこうしているうちに恐れていた雨が降りだした。カッパを着、タケ谷出合を目指して東の尾根を下りる。結構な傾斜だが、先ほど地獄を見てきたので何でもない。あっという間に愛知川沿いの登山道に下り立った。本流渡渉では靴を脱いだ。かなり冷たかったが、厳冬期に渡ったことを思い出せば物の数ではない。峠を越え、長い伊勢谷を下って車にたどり着くと雨は本降りになった。