御池岳1000m鉢巻行 Vol.3 07.10.07
(写真が二段になる場合は画面を広くしてご覧ください)
御池岳1000mラインの一周がまだ完成しないまま放置してあった。これにカタを付けないままでは気分がすっきりしないが、暑いうちはやりたくなかった。やっとしつこかった残暑も終焉を告げ、よい時節になってきたので実行することにした。残るラインはボタンブチの真下から南西の懸崖をアザミ谷まで。それとヒルコバから鈴北岳北斜面を半分。初回の激しい雨のなかで根負けして、鈴北岳北斜面を残してしまったことが今回の負担となっている。コース取りも悩むところだ。
鞍掛尾根の1056付近から突入してヒルコバ下へ達し、ヒルコバからボタンブチまで崖下をトラバースし、ボタンブチを這い上がってテーブルランドを横断して帰るのがベストか。先日完成した1万分の1立体模型を眺めながら作戦を練る。しかしそれでは新鮮味がないし、鞍掛尾根はもう飽きた。遅ればせながらゴロ谷デビューするか。私が今までゴロ谷から登らなかった理由はただひとつ。三重県側から御池橋まで行くのが面倒だから。それ以外の理由はない。
道路地図でシュミレートすると、自宅−宇賀渓−石榑峠−政所−君ガ畑−小又谷−御池橋で約40km。しかも普通の40kmではなく、腸捻転を起こしそうな峠越えと、向こうへ行けば長々しい林道である。そういうことは苦にしない人もいるが、鈴鹿中北部ならどこでも10分から20分で行っている私は苦になる。アルプス遠征なら4時間でも5時間でもかまわないが、鈴鹿に一時間半は勘弁である。霊仙山や仙ヶ岳以南へあまり行かないのも同じ理由。いつも長駆、県外の山へ行っている人なら呆れるような理由であろう。我ながら少しグータラであるとは思う。しかし毎週県外遠征している人もやや異常ではないか。
検索するとゴロ谷起点の記事は思ったより少ない。たいてい滋賀県中心の関西組である。私が登りたい第四尾根の情報は見つからなかった。まあ、行けば分かることだ。休日の早朝からガタガタするのも家族に迷惑なので、土曜の夜に現地入りした。夜中の石榑峠や御池林道で、まれに対向車に会うとドキッとしてすごく怪しいやつに見える。灯りの少ない君ガ畑集落を越えればもう人の気配はない。君ガ畑さえ異様な山奥なのだが。
小又谷広場を過ぎてから、シカと鉢合わせして、急ブレーキを踏んだ。普通なら斜面を駆け上がって逃げるが、コンクリートの絶壁ではさすがにシカも登れない。立派な角を持った牡鹿はヘッドライトに照らされたままじっとこちらを見ている。やがて反転して道路を駆け出した。あとを追ったが、カーブを曲がると消えていた。
ようやく御池橋に着いて、雑草茂る空き地に駐車する。トリップメーターは40.1kmになっていた。エンジンを切ると急に静かになって、人里離れた狐狸妖怪のテリトリーに入ったことをひしひしと感じる。空は一面の星で、御池岳のシルエットに北斗七星の柄が、生け花のように立っている。時折雲に隠れる三日月の下には、月を欺く明るい星が輝いていた。明日の天気予報は下り坂だが、この分では午前中くらいは晴れるかもと思う。さあ寝よう。
午前4時半に目覚めるが、外は真っ暗なのでまたうとうとする。とても長谷川さんのように暗いうちに歩く気にはなれない。外が薄明るくなってからパンを食べ、車から出て周囲を偵察する。どこもかも雑草だらけで、どこから入渓するのか分からない。夜の星が嘘のように空は雲で覆われていた。どうも天気の崩れは早そうだ。早発ちが吉だろう。車に戻って身支度をし、軽く体操して5時50分出発。橋の袂をいったん下流側へ踏み跡を辿り、川原へ下り立った。
広々とした川原に狭く浅い流れ。すぐに本流とゴロ谷の出合。水流は等分である。地図を見ればこれから伊勢尾と丁字尾根の間を行くことになるが、この狭隘な部分を埋めて両尾根をつなげてしまったらどうなるか。ゴロ谷とアザミ谷に水が溜まり、ロシアのバイカル湖のような形の湖ができよう。そこに屋形船を浮かべて綺麗どころを侍らせ、紅葉見物でもしたらさぞ面白かろう・・・阿呆な想像をしつつ、明けたばかりの薄暗い谷を遡行する。
やがてアザミ谷出合。オニグルミの枝越しに西のボタンブチ付近が見えている。猫の額ほどの青空さえなく、どんよりとした空模様にややブルーな気分。ここは地形図に635の表記があるので高度計を合わせる。
ゴロ谷は土砂の堆積がすごく、ちょうど現在の茶屋川のようである。だからここも以前の茶屋川のように、もっと風情と渓谷美があったことが類推される。これでは渓魚も生きられまい。ヤナギの類が茂る両岸の台地にはときおり杣道もあるようだが、「露もまだ干ぬ」状態では歩きたくない。川原の端には、白い化石状になった手形が落ちていた。



アザミ谷出合から御池岳西端 ワサビ谷出合 小ショベン谷出合
やがて第一支流(ワサビ谷)出合に着いた。凄絶な岩屑の押し出しで水流はない。三筋滝上の「流れ洞」と同じである。視線を上に転じれば平坦な御池岳に少しの盛り上がりが見える。丸池付近の丘か。ここを過ぎると坦々とした川原だったゴロ谷も、少し渓流らしくなってきた。そしてすぐ第二支流(大ショベン谷)の出合があった。いかにしても近すぎると思ったが、地図を見ると二つの谷はV字状に近づいてくるので間違いない。少量の水流あり。
谷はまた平坦な川原に戻った。しばらく歩くと第三支流(小ショベン谷)出合。流木やヤブであまり風情のない谷で、水流もない。ゴロ谷上流は巨大な丁字尾根が壁になり、付近全体が閉塞的な空間になっている。ここから右手の第四尾根に取り付けばよいだろう。
付近を偵察して取り付ける場所を探す。ウナギの背中のような痩せ尾根から本尾根に上がった。結構な急傾斜である。この尾根はどの木も根張りが地表にむき出しで、血管のように這い回っている。表土が流れてしまったのだろうか。スギやマツが混じり、まだ高度が低いことを表している。涸れ谷と思っていた左眼下の谷からチョロチョロ水音が聞こえる。伏流と表流を繰り返しているのだろう。そこがショベン谷の由来かも知れぬ。
750m付近で南の展望があった。丁字尾根が壁のようになって、その向こうは分からない。昨日はからりと乾いた風が吹く絶好の秋晴れだったが、今日は湿った風が吹き上げて肌寒い。日曜のたびに天気が悪い気がするのはヒガミだろうか。
傾斜が緩んで歩きやすくなった頃、右手に何か動く気配を感じた。シカだった。逃げずにこちらを見ている。これはチャンスとカメラを向ける。ファインダーを覗いていると、50mくらい離れているのに、ピントが合う音に耳がピクッと反応するのが見える。すごい聴力だ。そのうち他のシカも現れ、最後に立派な角の牡鹿が残った。こちらを見ている。なんだか人間くさい顔をしていて笑える。暗い中のズームなのでブレまくりだが、少しましなものを載せる。

尾根の下部は根がむき出し 変なやつが登ってきたぞ・・・と警戒 こちらは角持ち
800mを超えると緩やかな尾根はブナ・ミズナラ帯に変り、とてもよい雰囲気になった。突然目の前で牡鹿が一目散に駆け出した。地面を見ると寝床があった。驚かせて申し訳ないことをしたが、こちらも驚いた。900m付近からまた傾斜がきつくなる。地面には白い岩屑がポツポツと現れ、前回のトラバースラインに近づいてきたことを感じる。一汗かくと、ようやく腕時計の高度計が1000mを指した。ここは肝心なので、GPSのデータと地図を照合して正確な高度を求める。20m位余分に登っていたので高度計を修正。
前回はボタン岩下部の難儀さに嫌気がさして、ボタンブチの真下の小尾根からガレ場へ出、テーブルランドに這い上がってしまった。だから現在地点まで到達していない。ラインをつなげるには、そこまで戻らねばならない。高度をやや下げつつ東へトラバース。たいした距離ではないが、自分の中ですっきりするために必要だ。ゴロ石帯を渡り、やがて明確な尾根に到達。ゴロ谷第五尾根というには小規模なので4.5尾根くらいなものか。これですっきりしたので元へ戻って本来の西側ラインを目指す。傾斜はきついが、まずまず歩ける。東ボタンブチ下付近のように、身の危険を感じる場所ではない。樹林は適度な密度で、雰囲気は申し分ない。
トラバースを始めてすぐ大崩壊地にぶち当たる。地図では上部をかすめる筈だが、実際は横腹に当たって進めない。地図のマークより侵食が上部まで進んでいるわけである。雨乞岳の念仏ハゲのような感じで、落ちたらえらいことだ。これは上へ巻くしかない。高度差にして20mほどか。真上に達すると樹木がないので展望がよい。丁字尾根越しに天狗堂が見えている。下り一方と思われた天気だが、薄日が差してきた。空が明るくなると気分も明るくなる。物見遊山なら雨もまた楽しと余裕も出るが、危ないルートで雨に降られるのはまっぴらである。



緩やかな傾斜になるとブナが現れる 1000m付近に到達 地図のガレマーク地点
付近の樹木は地衣類が付いて白っぽく見え、涼しげな高原の雰囲気がする。鼻歌気分でトラバースと言いたいところだが、やがて数十cmの石灰岩がゴロゴロするゴロ石帯が現れる。ボタン岩の下付近と同じだ。この石が安定していれば土の斜面よりマシなのだが、非常に不安定で歩きにくい。苔むして何百年も鎮座しているような顔をしているが、足を置くとグラグラするし、大きな石でも平気で周囲の石を巻き込んで流れ出す。間に足首を突っ込んで捻挫したり、下敷きになったら大変だ。ここは地雷原を行くような慎重さが必要である。
しばらくして二つ目の崩壊地。これは上端の高度が1000mに達していないので問題ない。しかしすぐ下に見えるので、地形図よりはかなり進んでいる。この崩壊は第一支流の源頭である。これであの川原の状態が理解できる。
天気もますますよくなってきたので、ちょっと休憩する。座り込んで一個目のおにぎりを食べる。まだ8時40分だが、朝が早かったので腹が減る。進行方向でガラガラと不吉な落石音がした。めったなことはないと思うが、いやな感じである。
この先はゴロ石帯の連続で仕事がはかどらない。疲れてくると余計バランスも悪くなりフラフラだ。このゴロ石地獄も第一尾根の上部辺りでいったん終わった。やれやれと思ったのも束の間、岩尾根が張り出してライン上を塞いでいる。様子がよく分からないので、行ける所まで行ったら絶壁に入り込んでしまった。ラインが変わってしまうが、命が大事なので巻き上がるしかない。下を見ないようにして三点確保で攀じ登る。ああ、怖かった。
這い上がった尾根の鼻は平坦で、窯跡らしきものがあった。その中に何かの蓋のような陶器が落ちていた。先人の足跡は何処にでもあるものだ。風が寒いので、窯の底で休憩。



ゴロ石地獄を行く 窯跡に暮らしの跡が 根曲がりの花道
尾根の鼻から少し下りて1000mラインに復帰し、先へ進む。またゴロ石帯だ。しかし傾斜は差ほどでもない。同じゴロ石帯でも傾斜の具合によって難易度が違う。ここは木がなくて展望が開けているが、どの付近が見えているのかちょっと分からない。
やがてまた傾斜が強まってきた。かなりの難所だ。歩きにくくて、疲れて、泣きたくなってくる。こんな傾いた場所をトラバースしていると体がねじ曲がってきそうだ。こういうときはいつも 「なんで俺はこんな阿呆なことをしているのだろう」と自問する。答えはひとつ、阿呆だからである。たいていメモに難所と書いたところは、後で地図を見ると、等高線が密集して判読できないような場所である。そのときは認識していなかったが、ちょうど冠谷源頭付近だったようだ。
難所を過ぎても南西の崖下はいやになるほど長い。時折現れるアケボノソウやジンジソウに慰められる。まあ気長に歩いていればいつかアザミ谷に着くことは自明である。やがて果てしなかった右手の斜面に光が見えてきた。お花の尾根である。尾根のほうが徐々に1000mに近づいてきたということだ。それと同時にシカ道を追うことが可能になり、歩きやすくなってきた。やはりお花さんは優しい。地面には夥しいオニグルミの実が落ちている。樹林の間から鈴ヶ岳の盛り上がりが見えるようになり、ようやくアザミ谷に達した。
疲れているのでヒルコバまでの数十mの登りがとてもきつかった。ようやく這い上がったヒルコバにへたり込んで大休止。時刻は10時25分。ずいぶん私も体力が落ちたなあと思う。二つ目のおにぎりをいただく。誰もいない。鉢巻初回にヒルコバまで到達していれば、ここで一周完成だった。あとは伊勢尾から帰れば楽である。しかし鈴北岳北面を残したことで、今日は丸一日遊ばせてもらえることになった。ミズナラの木にもたれてしばし目を瞑る。
ヒルコバは等高線から判読して1045m。高度計を微修正して御池谷へ下りる。1000mになったらヤブを掻き分けて東へトラバース。ヤブの向こうは、うまい具合にラインが岩棚になっていて順調に進む。やがて土の斜面になるが、北面は日が当たらないのでいつも濡れていてよく滑る。10mほど高度を下げてシカ道を追う。そうしないと歩けない。突然目の前の傾斜が緩くなった。小さな尾根の上で、少し下にはコバもある。そして尾根を横切れば当然谷がある。大きくえぐられて歩きにくい。難所を過ぎると見覚えのある岩塔に出た。初回に雨に負けて打ち切った場所だ。とうとう1000mライン一周を成し遂げた。握手をしようにも誰もいないので、右手と左手で握手だ。
ここから前回と同じく鈴北岳を目指して急斜面を登る。傾斜は急で心臓が早鐘を打つ。しかし、しっかりした石灰岩があるので足場には困らない。それを過ぎるとシダの大草原になる。鞍掛尾根1056から見えているハゲである。背後の視界が開け、烏帽子・三国・ダイラの頭が並んでいる。鞍掛尾根もすぐ近くに見える。開放感はあるが、シダが腰まで伸びているうえに、傾斜がきついので登りやすくはない。しばし立ち止まっては、景色を眺めて休む。



石灰岩の塔で鉢巻のゴール シダ原から鞍掛尾根1056を望む オニイタヤの大木
1100mで前回見つけたオニイタヤの木に到達。カエデにしては太い幹で、大きく枝を広げているので遠目にも目立つ。今日はスケールを持っているので計ってみた。胴囲238cm。ここからもうひと頑張りで鈴北岳への登山道へ出る。以前のような頑強なササがあったら泣きたくなる場所だが、枯れただけではなく密度も低下している。鈴北岳付近にはパラパラと人がいた。丸山は見えるが、奥ノ平はガスが流れている。そういえば二週間前のお昼ごろにもここに居た。南方を眺めても、今日はヨメナの中で傘をさしている人はいないようだ。
適当にショートカットして真ノ池に駆け下りた。池の畔で怪しい人物が何かしている。よく見ると池の泥を小さな網で掬っている。「何かいますか」と尋ねると、驚いてこちらを振り向いた。案外若い人だ。イモリやマメシジミがいるとのこと。「トンボがいますねえ」とわざと聞いてみたら、「ルリボシヤンマでしょう」との返事。こやつできるな。まあ、わざわざ観察しているのだから、その道の愛好者なのだろう。
ここから奥に入り、南池、サワグルミの池、ウリハダカエデの池と通過する。ウリハダカエデの池にはまだ例のプレートが下がっていた。この池の水面の反射はきれいだなといつも思う。そして尾根に上がって丸池へ。左斜面にメガネの木。まだこの木をくぐってはしゃいでいた人達の体温が残っている気がする。誰もいない丸池の畔に腰をおろし、最後のおにぎりを食べる。静寂の水面に浮かぶ落ち葉を眺めていると、時間や空間の概念が曖昧になってくる。


鈴北岳から奥の平の木々を望む 静寂の丸池
さあ帰るか。テーブルの端に出て、南西の急斜面に身を投げ出す。草や木をつかんでズルズルと滑り下りていく。地図が正しければ、重力に身を任せているうちに第一尾根に乗るだろう。ここは登るのも大変だろうが、下るのも難儀だ。つかまる木がないところは、土のグリセードで滑り降りる。ジンジソウやアケボノソウが残る岩場で一休み。もうおにぎりはないのでチョコレートを食べる。
1000mで午前中のラインと交差したはずだが、何処も似たような景色で記憶はない。ただこの付近はケヤキが多い。北面のケヤキはアガリコだが、こちら側はスッと高く伸びている。
900mで傾斜が緩み、窯跡と思しきものがが3基ばかり。先には明瞭な尾根が見えている。うまく第一尾根に乗ったようだ。この先800mまでは本当にすばらしい尾根で、紅葉時に今一度来てみたい。紅葉時と言っても、そんなに先の話ではない。しかし木々は青々として気配もない。9月が暑かったので今年は遅れるだろう。キノコも不作のようだ。マスタケを見つけたが、もう硬くてダメだ。
お隣の尾根の様子を窺いたいが、樹林が濃くてよく見えない。ただ午前中に見下ろしてきた崩壊地がチラチラ見えている。



急斜面で心が和むジンジソウ 950m付近の樹林 第一尾根に乗る
800m先端の小ピークから尾根は向きを変える。急にアセビやらシャクナゲでヤブっぽくなる。しかし間を縫っていけばどうということはない。途中で大崩壊地を見渡せる場所があった。その向こうにはボタンブチなどの出っ張りが並んでいる。
どんどん下ると左手に白い筋が見えた。ゴロ谷にしてはおかしいので支流だろう。せっかくだからちょっと観察していこう。急斜面から第一支流ワサビ谷に下り立つと、一面岩屑の押し出しで、すさまじい光景だ。昔は名前どおり、ここにもワサビがあったのだろう。少しだけ水ががチョロチョロ流れて、また消えている。この水は清浄なようだが、今日は飲み水に不足していないのでやめておこう。出合まで下ると、あとは往路をたどるのみ。満足感に浸りながら帰った。



樹林の隙間から崩壊地 岩屑が押し寄せるワサビ谷 ゴロ谷の平流
さて今さら御池岳を一周して、それがどうなんだ、何か意味があるのかと問われれば、大半は単なる自己満足である。しかし西尾本にこうある。
「御池岳のような大岳は通り一遍のコースでお茶を濁さず、あらゆる可能性を求めて積極的なチャレンジを行うべきだと思う」
一周したことで御池岳の概要をつかむことに、自分の中では一歩前進したと思う。すでに過去の御池ブームのときに何人かの先達が一周しておられると思うが、高度は1100から1150ではなかっただろうか。高度により、季節により御池岳はまだ無限の表情を見せてくれるだろう。
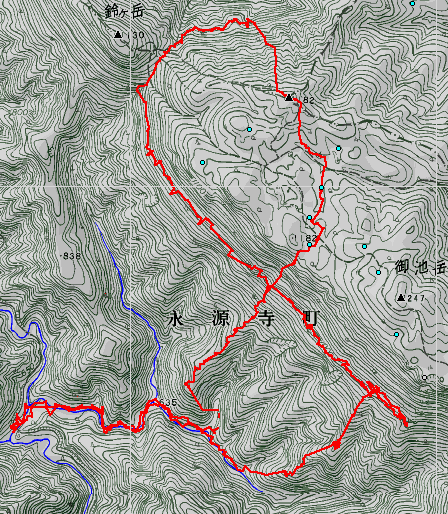
まずまず1000m等高線に忠実であったが、難所で多少の上下はある。鈴北岳北斜面ではなぜか前回と同じく少し高度が下がってしまっている。やはり歩けるところを選んでいると、自然にそうなるのか。