日本コバ(新ハイ関西同行記) 02.01.20
![]()
日本コバにまだ登った事がなかった。無論この大層な名を持つ山の存在は充分承知していたが、こんな山いつでも登れるだろうと思ってずーっと引き伸ばしてきた。せっかく永源寺町へ行ったなら他に魅力的な所がたくさんあるからだ。いつでも登れると言う事はいつまでたっても登れないということと同義語である。せっかく新ハイに入っているのだし、よく名を聞く岩野氏とは如何なる人物かという興味もあったし、笠松尾根と言うルートも魅力的だったので参加体験してみた。
石榑峠は一片の雪も無く、乾いた舗装路面のままだった。今日は暦の大寒。異常現象だ。ただし原則通行止めだから推奨はしない。早く着きすぎたと思ったら如来堂の郵便局の空き地は満車だった。すごい人数で圧倒される。リーダーの岩野氏が点呼を取ったら総勢37名。こんな団体で登った事が無い。しかも大勢ながら見渡す限り知った顔は一人もなし。他の皆さんは常連らしくガヤガヤと賑やかだ。何か疎外感を感じる。老人会と言っては言いすぎだが、私より年長の(に見える)人ばかりだ。50〜60代中心か?
何故か知らないが、今日は笠松尾根をやめて藤川谷右岸尾根を登るらしい。藤川谷登山道を少し歩いてから、左手(右岸)の尾根に取り付く。植林道らしく道型はある。なかなかの急斜面だが皆さんハイペースで登っていく。ムム、この老人会は侮れんなあと思いつつ、最後尾辺りを着いていく。やがて前がつかえてきて9時頃休憩となった。やはりねえ。歩き出しは急いではいかんて。見知らぬ方(と言っても全員見知らぬ方なのだが)にミカンを頂く。有りがたや。
 急登は続き520m辺りで細長いピークに着く。そこから少し下って、また痩せ尾根の登りになる。地形図どおりだ(当たり前)。9:30、620m辺りで休憩。9:45、695mで休憩。あまりに休憩が多いので「岩野さん朝から一杯入っとるな」の声があがる。列が長いので最後尾は斜面で一服となる。隣の人と話していたら、たろぼうさんを知っているとのこと。そう言えば今日は長靴の人が10人ばかりいる。新ハイで流行っているのだろうか。たろぼうさんの専売特許ではなかったようだ。背後に釈迦ヶ岳、割山などが見える。
急登は続き520m辺りで細長いピークに着く。そこから少し下って、また痩せ尾根の登りになる。地形図どおりだ(当たり前)。9:30、620m辺りで休憩。9:45、695mで休憩。あまりに休憩が多いので「岩野さん朝から一杯入っとるな」の声があがる。列が長いので最後尾は斜面で一服となる。隣の人と話していたら、たろぼうさんを知っているとのこと。そう言えば今日は長靴の人が10人ばかりいる。新ハイで流行っているのだろうか。たろぼうさんの専売特許ではなかったようだ。背後に釈迦ヶ岳、割山などが見える。
ここから等高線が込み入っていてすごい急登になる。T字尾根からテーブルランドに這い上がる所ぐらいの斜度だ。しかも落ち葉で滑る。皆さん左右に展開して思い思いの所を喘ぎながら登る。写真では斜度が分かりづらいがかなりすごい斜面が延々と続く。途中で大人げない考えが浮かんだ。「よし、ここでごぼう抜きにしてやろう」。何もする事がないから、こんな事で遊ぶ。ムチを入れて25人ばかり抜いた所で800mの肩に着いてしまって、全員抜く事はできなかった。やはりこの敬老会は毎週ほど登っているだけあって侮れん。この肩でまた休憩。
少し歩くと838標高点。ここは広いコバで、いい雰囲気だ。ヌタ場に氷が張っている。雪はここで初めてうっすらと姿を現す。世が世なら今ごろラッセルを楽しんでいる時期だ。今年は正月から大雪が降って喜んでいたが竜頭蛇尾に終りそうだ。まだ厳冬期はこれからだから分からないが。
地形図を見る限り、もう山頂までキツい所はなくのんびりと尾根を歩く。団体歩きに慣れていなくて前がうっとおしいので、ここからは先頭のリーダーのすぐ後ろを歩く。団体登山は何もルートファインディングをしなくていいので楽だ。反面つまらないとも言える。左下に永源寺ダムが見えている。右手には遠く白い山がチラチラ見えているが、樹林が濃いので良く分からない。赤松がけっこうある。
山頂手前、笠松尾根からの出合でまた休憩。見知らぬ女性からオレンジを頂く。皆さん親切だ。岩野さんにお歳を聞いたら「もうとうに還暦を過ぎました」とのこと。あとでオレンジを下さった女性がナイショで「岩野さん、昭和○○年生まれなのよ」と教えてくれた。私の母と同い年だ。
 一人の男性から「石榑峠は通れましたか」と声を掛けられてびっくりした。私が山手から車で来たのを覚えていらしたのだろう。話してみれば四日市の人で、石榑峠を諦めて1号線回りだったそうだ。私は菰野から来ましたと言う事で話がはずむ。パソコンはやってますかと尋ねたら「あんた、ホーネンマンサクさんと違いますか」と言われて驚く。インターネットはやってないけど、たろぼうさんに鈴鹿百人一首のコピーをもらったと言う。周りにいたおばさん達から「あのホーネンマンサクさん?」と声が掛かる。私はそういう名前は名乗った事はないが、近藤先生が新ハイ関西誌に書いたので私はマンサクで通っているらしい。近藤先生(御池杣人氏)は新ハイにも影響力があるようだ。有難いような有難くないような。
一人の男性から「石榑峠は通れましたか」と声を掛けられてびっくりした。私が山手から車で来たのを覚えていらしたのだろう。話してみれば四日市の人で、石榑峠を諦めて1号線回りだったそうだ。私は菰野から来ましたと言う事で話がはずむ。パソコンはやってますかと尋ねたら「あんた、ホーネンマンサクさんと違いますか」と言われて驚く。インターネットはやってないけど、たろぼうさんに鈴鹿百人一首のコピーをもらったと言う。周りにいたおばさん達から「あのホーネンマンサクさん?」と声が掛かる。私はそういう名前は名乗った事はないが、近藤先生が新ハイ関西誌に書いたので私はマンサクで通っているらしい。近藤先生(御池杣人氏)は新ハイにも影響力があるようだ。有難いような有難くないような。
日本コバの山頂10:52着。白い山は霊仙山だった。そして背後にこれまた真っ白な伊吹山がピタリと重なっている(帰ってから地図に定規を当ててみたらこの三山の山頂は寸部の狂いもなく一直線上に定位している。お見事)。南に目を転じれば綿向山、イハイガ岳、雨乞岳、手前にカクレグラなどが見える。この場所は山頂などと言う雰囲気はなく、尾根の通過点に思える。しかしいっちょ前に三角点がある。日本コバの名の由来に二本(一本は山用語で休息の意)とったら登れる山と言う説がある。今日は五本コバくらいだった。昼食かと思ったらすぐ通過だった。
 そのまま北西に大したアップダウンもなく進んでいく。地図を見ると、このまま行ったら新開道だ。途中どうもリーダーが道に自信がなくなったらしく暫し立ち止まって人を呼ぶ。衣掛山への尾根を行かず、このまま東の沢へ降りようと決す。藤川谷源頭だ。10cmほどの雪の斜面を駆け下りる。左岸をトラバースしてどんどん下ると、やがて疎林の平坦な湿地帯へ出た。11:50、いい所だ。池がひとつあって凍結している。「衣掛の泉」と言うそうな。
そのまま北西に大したアップダウンもなく進んでいく。地図を見ると、このまま行ったら新開道だ。途中どうもリーダーが道に自信がなくなったらしく暫し立ち止まって人を呼ぶ。衣掛山への尾根を行かず、このまま東の沢へ降りようと決す。藤川谷源頭だ。10cmほどの雪の斜面を駆け下りる。左岸をトラバースしてどんどん下ると、やがて疎林の平坦な湿地帯へ出た。11:50、いい所だ。池がひとつあって凍結している。「衣掛の泉」と言うそうな。
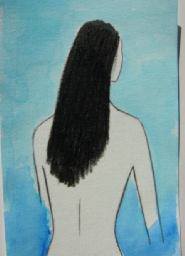 衣掛(きぬかけ)の由来は西尾本にも出ていない。では自説を披露しよう。これはずばり天女の羽衣伝説である。この泉のほとりに天女が舞い降りて、枝に衣を掛けてあられもない姿で水浴びしたと言うのはどうだろう。だから泉が先で、衣掛山の名はあとから付いたと思う。
衣掛(きぬかけ)の由来は西尾本にも出ていない。では自説を披露しよう。これはずばり天女の羽衣伝説である。この泉のほとりに天女が舞い降りて、枝に衣を掛けてあられもない姿で水浴びしたと言うのはどうだろう。だから泉が先で、衣掛山の名はあとから付いたと思う。
ここで昼食タイムとなった。腰を降ろしてさあ、腹減った、飯だ飯だとザックを探って青くなった。いくら探してもおにぎりが出てこない。どうも車に忘れてきたらしい。何たる失態だ。幸いスープ変わりのカップヌードルミニとインスタント味噌汁は入っていた。食べてはみたものの腹が膨れるはずもない。何かないかと探れば非常食に持ち歩いているカロリーメイトがあったのでかじる。激マズ。おやつのチョコも食べるが味噌汁にチョコでは食事ではない。ああ情けなや。周りは見知らぬ人ばかり。

しかし私は図々しいので、朝たろぼう氏を知っていると言っていた大津のG氏に「いやー、まいったなあ。おにぎりを車に忘れてしまいました」と言った。むろん「何か恵んでくれ」という催促である。するとG氏のザックから小さなパンがたくさん出てきた。オマケに鍋に入っていたソーセージまで分けて頂き、即席のホットドックにして食べた。ああおいし。Gさん、あなたは神様です。有難うございました。
帰りはここから少し下って北へ向きを変えて藪を漕ぐと登山道に出た。登山道をどんどん進み、岩屋を見物。洞窟の中はかなり広く、全員が入れるくらいだ。どうもあまりに天井が平らなので人工的なもののような気がする。名付けて「奇人の窟」と言う。ここからは岩の急降下だが大渋滞となる。団体登山の宿命だが、じれったくてイライラする。上から見ていると皆さんへっぴり腰で前かがみになりすぎだ(特にオバサン方)。こんな所は体を立てて垂直に荷重をかければそう滑るものではない。しかし初参加で昼飯まで恵んでもらっている私には「何やっとんじゃー」とは口が裂けても言えない。
だいたいこんな事でイラつくのは私の精神修養が足りない証拠である。タバコでも吸いながら「あわてんでもいいからゆっくり降りてちょうだいね。怪我せんようにね」と悠然と構えていなければならない。
 更に登山道をどんどん下る。サブリーダーのY氏に「ヒョウの穴」に付いて尋ねる。もうすぐらしい。登山道から離れて斜面を登ると小さな洞窟があった。すぐ行き止まりの小さな穴だ。えらいチンケな穴やなあと思ったら「豹の穴」はその上だった。小さい方は「ねこの穴」にしとこう。豹の穴にヘッドライトを持って入る。奥はすごく深い池になっていて通過しようと思ったら泳ぐしかない。澄んだ水を満々と湛え恐ろしくも神々しい。入り口を降りた左の岩棚に登るとまだ上にも細長い穴があって、何処まで続いているやら分からない。
更に登山道をどんどん下る。サブリーダーのY氏に「ヒョウの穴」に付いて尋ねる。もうすぐらしい。登山道から離れて斜面を登ると小さな洞窟があった。すぐ行き止まりの小さな穴だ。えらいチンケな穴やなあと思ったら「豹の穴」はその上だった。小さい方は「ねこの穴」にしとこう。豹の穴にヘッドライトを持って入る。奥はすごく深い池になっていて通過しようと思ったら泳ぐしかない。澄んだ水を満々と湛え恐ろしくも神々しい。入り口を降りた左の岩棚に登るとまだ上にも細長い穴があって、何処まで続いているやら分からない。 「虎穴に入らずんば虎児を得ず」・・・豹の穴では何が得られるのだろう。
「虎穴に入らずんば虎児を得ず」・・・豹の穴では何が得られるのだろう。
更に降りて小さな神社の境内で大休止。また色々なお菓子やら果物が回ってきた。気前のいい人ばかりだ。ここからはすぐ駐車場に着いて点呼を取り、リーダー岩野氏の挨拶の後解散。日本コバは岩野氏の言われる通り「つかみ所の無い山」で無数にルートが取れる。一度行ったきりでは魅力のすべては味わえないだろう。今度はこんな大人数はかなわんから、一人で笠松尾根を登って天女のストリップショーを見てこよう。