釈迦ヶ岳東尾根 01.04.15
![]()
釈迦ヶ岳東面には段木、大平、岩ヶ峰〜北山、自他ヶ峰などの尾根があるが、山頂から直接東へ伸び尾高山に達するものが一番大きい。家から見ても良く目立つ。「鈴鹿の山と谷」にも詳しく出ていない。今日はここが登れるか偵察に行った。この尾根の名前を聞かないが、釈迦ヶ岳東尾根としておく。
 尾高山や焼合谷からやると長大すぎるので、良い取り付きが無いかと地形図を見ると田光川支流大谷の左股が都合が良い。この尾根には標高点が一つも無いので、以下P○○○というのはコンターから読み取った数字。
尾高山や焼合谷からやると長大すぎるので、良い取り付きが無いかと地形図を見ると田光川支流大谷の左股が都合が良い。この尾根には標高点が一つも無いので、以下P○○○というのはコンターから読み取った数字。
切畑の上から左折して東海自然歩道に入り、大谷採石場に車を止める。ここの工事はもう終っている。8:20発。大谷を遡行していき、南から西へ屈曲する地点で左股へ入る。出会いは花崗岩が重なっているが、右岸の道跡から簡単に入れる。
この谷の水は少ない。ガラガラの石くずを登っていくと段々傾斜がましてきて、やがてゴルジュ状のカラ滝が現れ、風化した花崗岩にてこずりながら登る。右手の薮に昔の道がありそうだったが、あえて谷の中を進む。ツメはすごい傾斜の砂礫で登れそうも無い。よく見ると古い道が谷を横断している。昔のそま道だろう。少しこれを左へたどり、木をつかんで尾根に這い上がる。この辺りはイワウチワの群落で大変美しい。
狙いどおり650mの痩せ尾根に出た。少しバックしてP660へ上がってみたが、樹林で展望は無い。再び戻って西へ登りにかかる。拍子抜けすることに、ここには踏み跡があった。目印さえあるではないか。やはり、地形図で行けるとふんだ所には必ず誰かが入っている。この尾根は痩せているので外すことは無い。樅、杉、松などの木は結構大きい。
鼻歌交じりで西へ進んでいく。コブシの白い花が、膨大な大谷上空の空間に飛ぶ鷺のようだ。P740は右手を巻いている。地形図どおり750mから急登になるが、手掛かりは豊富だ。10:23 P840通過。あまり展望は無いが右手の樹間から岩ヶ峰が見えている。下流で咲いていたツツジはまだ蕾だ。
ピークを巻く道型もあるが、せっかくだから全部ピークを踏む。10:38 P910着。ちょうど良い平石があったので腰を降ろして休憩。お茶を飲みながらおやつを食べる。大谷から心地よい風が這い上がってくる。人生の何気ない幸せはこんな瞬間だ。
岩を這い上がるとP930。やっとここで北側の大展望が得られた。ここから岩ヶ峰と三池岳が一直線になり、その向こうに竜ヶ岳が望まれる。見上げれば釈迦ヶ岳山頂が聳えている。今日は春にしては上天気で、絶景であることよ。
P960あたりはシャクナゲが多い。ここからいよいよ急登の笹薮こぎとなる。笹は邪魔であるが、手掛かりにもなる。やはりバリエーションはこうでなくちゃね。最後は目印も無く、適当に薮を掻き分けて進む。やがて松尾尾根に至る登山道が、上部に見えてきた。おう、生きた人間が歩いている。ひと踏ん張りで登山道に飛び出した。三角点すぐ南だ。11:42山頂着。道草していたとはいえ3時間強かかっている。しかし印象としては左俣上部以外は案外あっけなかった感じである。
釈迦ヶ岳は懐深い良い山だが、山頂はいただけない。すぐ通過して、お気に入りの岩ヶ峰手前のコバまで昼食はおあずけ。三池岳方面へ駆け下って、ビール瓶を埋めてある所からトラロープに縋って急降下。コバには誰もいない。時計もちょうどお昼時だ。ザックの中身をぶちまけて地図を見ながらおにぎりをほおばる。静かだなあ・・・と思ったのも束の間、ガヤガヤ人の声が聞こえてきた。
来るは来るは総勢三十数人。リーダーの合図で皆さんここでお昼にかかる。この静かな場所が、いっぺんに街なかの雑踏の如く変貌した。こんな大パーティーと出会うのは初めてだ。しかもこんな場所で。名古屋 山想山歩の会他ということだ。多勢に無勢で恐れ入って昼食もそこそこに立ち去る。皆さん何処から取り付いたのか聞けばよかった。たぶん栃谷だろう。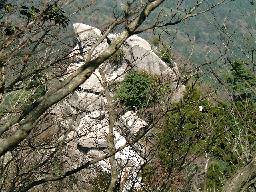
ここから北山まではっきりしたルートがついている。ただし一般道ではないのでまっ逆さまの急降下である。途中大きな花崗岩の中ほどにある岩小屋に登ってみた。2〜3人は入れそうだ。下りるのは危ないので尾根に這い上がったが冷や汗ものだった。尾根からは北に花崗岩の積み重なった奇岩がみえている。たぶんこれが 鏡岩と呼ばれているものだろう。この先も木をつかんでの急降下だ。往路に使った東尾根の写真をとろうと思ったが、樹林が邪魔で果たせなかった。この辺りは切畑の対岸にあったという花市場の木地師のテリトリーだったと言う説がある。
北山からは以前降りた牛首の尾根ではなく、直接北谷を下降した。ここの上部はとんでもない所で全身を使って落ちてゆく(降りるという表現を超えている)。西尾氏の言うルートは左岸にあると思われる。谷自体は崩壊激しく落石が危ない。しかも水は少ないが滝だらけで、下降は容易でない。590m付近でついに降りることができない目の眩むような滝に会う。近寄るのも危なく、命あってのものだねでなるべく遠く左岸を高巻く。なんとなく道のようなものがある。高所に上がったら、朝置いた車が豆粒のように見えている 。
。
発破を掛けていた採石場のてっぺんへ出たのだ。ここから急斜面の砂地をズルズルと下っていく。菰野町北部が一望できる。右手の北谷は滝の下から倒木に埋まって無残なものとなっている。2:27車着。まだ時間が早いので切畑からキャンプ場のほうへ上がってみた。まだこの辺りは桜並木が見事である。今日は田光で4年ぶりに草競馬が行われ、帰りの渋滞にはまってしまった。
釈迦ヶ岳東面は朝明からのルートより、古(いにしえ)の風情がある。