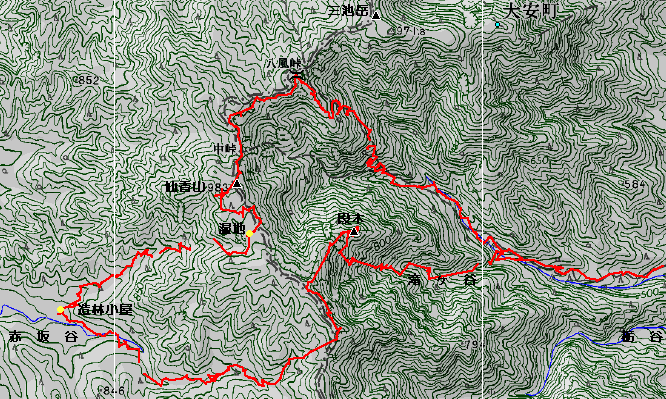滝ヶ谷から段木・赤坂谷 04.07.12
![]()
三池岳はどんな形の山だというイメージが湧かない。いわゆる絵になりにくい山だ。前回は天気も悪く、取材写真もそれだけが心残りで再訪することにした。といっても遠景写真だけなので三池岳に登ることはない。段木辺りからどうかと思い、ついでに少ししかトレースしていない滝ヶ谷を登路に選んだ。
天気は梅雨時にしては上の部類。薄く霞んでいるのは致し方ない。八風キャンプ場は結構賑わっていた。しかし射撃場上の空き地に車はなかった。荒れた林道を歩く。ジムニーに乗っていた頃は一番奥の広場まで乗り込んでいた。荒れたと言っても車の立場であり、歩くのは快適な道だ。石の鳥居の真上に朝日が輝いている。御旅所旧陵の石碑を過ぎると、じきに堰堤下の広場だ。ここから坂を一段上ったところから滝ヶ谷に入る。
入り口の奥には30mはあろうかという見事な斜滝が掛かり、人の侵入を拒んでいる。探せば右から巻き道があるのだが、めったに使われないので快適とはいえない。ここへ入るのは約10年ぶりで、そのときは釣りには水量が少ないので、途中で引き返した。巻いたあとは右岸に使える道がある。以前の地図に滝ヶ谷から大平の尾根に登り、稜線に出るルートが破線で書かれていた。もう完全な廃道である。土曜の雨の後なので水量は多いほうなのだろう。それでも谷中を歩いても濡れずに済む。


入口の大滝 階段状の滝
小ぶりながらも美しい渓流で、おいしい水が飲み放題である。田光川の水は水道に使われている。滝は入り口のものだけで、問題になるような障害はない。先週の猛暑は堪えたが、ここの涼しさはどうだろう。日が当たらず爽やかな風だけが通り過ぎていく。汗がまったく出ない。700mを越えて傾斜が強まると、背後に視界が開けてきた。山はこの高度感がたまらない。だんだん傾斜がきつくなり、水は消えかけ、ガラガラの岩だらけになる。地形図を見てそろそろ段木に取り付かねばと思う。しかし右側の山腹は急斜面、ルンゼも急だ。同じ斜度なら木につかまれるほうを選ぶ。
 よじ登ってみるとどうにもならない密林になってきた。転落こそしないが、前進の抵抗がきつくて苦労が多い。見上げるような傾斜をサルのように木から木へ登る。いや本当のサルなら軽やかに登るだろうが、ひざ痛の中年ではドンくさいことである。アルプスにはこんな難所はない。マジで泣きたくなってきた頃、傾斜が緩く樹林もまばらな地帯に出た。よく見れば炭焼き道が横切っている。どうも取り付き箇所がまずく、余計なアルバイトをしたようである。まあ、ちょっと一服だ。
よじ登ってみるとどうにもならない密林になってきた。転落こそしないが、前進の抵抗がきつくて苦労が多い。見上げるような傾斜をサルのように木から木へ登る。いや本当のサルなら軽やかに登るだろうが、ひざ痛の中年ではドンくさいことである。アルプスにはこんな難所はない。マジで泣きたくなってきた頃、傾斜が緩く樹林もまばらな地帯に出た。よく見れば炭焼き道が横切っている。どうも取り付き箇所がまずく、余計なアルバイトをしたようである。まあ、ちょっと一服だ。
かすかな道跡をジグザグに登る。障害物がないことがこんなにも有難いとは。そのうちまたヤブになってきた。右側の端が明るいので行ってみたら、至近距離に段木の坊主頭が見えていた。ここから樹林帯を捨てて砂の斜面を降り、段木手前のコルに登り返すことにした。アセビの新芽がもえるように赤い。シロヤシオやアセビの斜面を登り返すと目的地に飛び出した。吹き荒れる強風に長い草がなびいている。帽子を脱いでザックに入れる。三池岳をはじめ稜線の山々が並んでいるが、青空はなく霞が掛かっている。とりあえず休憩をかねた撮影タイムとする。低い雲がすごい速さで移動していく。



滝ヶ谷を見下ろす 鮮やかな新芽 八風峠の稜線
 県境稜線へ上がる途中にも撮影ポイントは幾つかある。稜線出合を左折して釈迦ヶ岳方面へ進む。自宅付近がよく見える場所があったので眺めていたら、ソロの登山者が追い越していった。釈迦ヶ岳へ登るのだろう。そこから適当に滋賀県側へ降りた。この辺りはどこから降りても赤坂谷に収斂されていく。谷筋は砂が柔らかく、靴が潜るので尾根を歩く。やがて釈迦ヶ岳からの谷と合流する出合に着いた。ここは私のお気に入りの場所である。少し早いが昼食としよう。デザートの水ようかんを谷で冷やしておく。今日はもう少し下流の淵でひと風呂浴びようと思っていたが、すでに十分涼しいのでやめた。風邪をひいてしまう。
県境稜線へ上がる途中にも撮影ポイントは幾つかある。稜線出合を左折して釈迦ヶ岳方面へ進む。自宅付近がよく見える場所があったので眺めていたら、ソロの登山者が追い越していった。釈迦ヶ岳へ登るのだろう。そこから適当に滋賀県側へ降りた。この辺りはどこから降りても赤坂谷に収斂されていく。谷筋は砂が柔らかく、靴が潜るので尾根を歩く。やがて釈迦ヶ岳からの谷と合流する出合に着いた。ここは私のお気に入りの場所である。少し早いが昼食としよう。デザートの水ようかんを谷で冷やしておく。今日はもう少し下流の淵でひと風呂浴びようと思っていたが、すでに十分涼しいのでやめた。風邪をひいてしまう。
食後、右岸の道をゆるゆると下る。この道は三重県側の労働者が、赤坂谷周辺で山仕事をするために付いたと思われる。まだ十分生きている。久しぶりに造林小屋まで行こう。地形図を見れば分かるが、この辺りは殆ど傾斜がなく楽園のような場所である。
二棟ある造林小屋は荒れ果てている。屋根も窓も壊れているので雨は入り放題だ。外は一升瓶やビールの空き缶、内部は乾電池、蚊取り線香、空き缶等が散乱している。布団は湿らないようロープで吊ってある。それでも何年か前に見たままで、意外と建物の傷みは進行していない。木陰で昼寝でもしようかと思ったが、晴れてきて三池岳の写真が気になるのでやめた。



放棄された造林小屋 赤坂谷左俣の二次林 湿原の池
ここで折り返して赤坂谷左俣に入る。八風南峠へ向かう谷だ。道はないが右岸が途中まで植林なので歩ける。もう使う人もいないが、一応峠の名があるので昔の道型も一部ある。ここを通るのは 「あわやSHIGEKIさんと全裸遭遇事件」 以来だ。植林が終わると美しい二次林になるが、詰めは歩きにくい。谷筋を外さないように登ると、最後は鳩峰のような湿地帯になる。あまり知られていないが、ここには美しい池がある。トンボが群れ飛び涼味を添える。
南峠付近もいい撮影ポイントだ。朝通ってきた段木の向こうには、下界が箱庭のように展開する。ここから中峠道に降りれば近道だが、八風峠の写真を撮るために北へ向かう。その前にいつも通り過ぎるだけの仙香山のミニ探検をする。この山へ突き上げる谷中は巨岩がゴロゴロしていた。先ほど登った谷の支流だろう。中峠の次のピークも岩の上から展望がよい。朝よりは光線に恵まれてきた。コントラストの狭いデジカメで、絵葉書のような遠景写真を撮るには光量がものを言う。見通しのよいときに山に纏いつくガスは絵になるが、空気に透明度のないベタ曇りは写真にならない。


南峠から段木 八風峠と三池岳
八風峠には丘に上げたマグロのようなものが二体転がっていた。死んでいるのかと思ったが、鮮度がよいのでお昼寝中のようだ。顔にはタオルや帽子が乗っているので性別も判然としない。なにも夏の直射日光にさらされて寝なくても、涼しい木陰で寝ればいいものを。まあ、人の好みはそれぞれだから、私の関知するところではない。しかしあまりの熟睡が羨ましかったので、私も木陰を探して寝ようと思う。もう写真は撮ったので急ぐことはない。峠から街道を少し降りると平坦な樹林帯がある。シロモジの林の中にシートを敷き、登山靴を脱いで横になった。ああ、なんという気持ちよさ。ヒグラシの鳴き声が5.1Ch サラウンドで響き渡る。その日暮らしの私にはヒグラシのBGMがぴったりだ。熟睡はしなかったが涼やかな風を感じながら、ウトウトと夢うつつの時間が過ぎていった。