


栃谷から岩ヶ峰 09.06.07
昨年の豪雨は八風キャンプ場西のコンクリート橋(栃谷橋)を破壊して押し流した。この谷の土石流もすさまじいものがあったのだろう。前回来たときには渡渉したが、現在は工事車両が通る臨時の道ができている。ただし一般車両は通れない。壊れた橋には新しい橋脚が一部できていた。今日はこの栃谷を久々に歩いてみようと思う。この谷は実に10年ぶりで、記憶も薄らぎかけている。
左岸林道は堰堤修復工事のため、以前より立派になった。あちこちに大型重機が置いてある。その脇には飴のように曲がった鉄骨が回収されて積み上がっており、堰堤の上部は流れてきた石によってボロボロに欠けている。自然の持つパワーは恐るべきものだ。それとは無関係に林道の端には長閑に満開の卯の花が続く。
最終堰堤で林道はなくなる。以前は左から巻いたように思うが、谷がえぐれているので右の藪の中を巻く。谷芯に下りると累々たる花崗岩の堆積で、以前より明るく広く見える。水流は広い河原の一部分であり、渓流シューズの必要はない。庭石に持って帰りたいような見事な花崗岩が散乱しているが、20トンクラスでは担いでいくわけにもいかない。まだ傾斜はあまりないが、石の上を渡り歩きながら進まねばならない。バランスやルートファインディングの訓練によい。と言っても今更向上するでもなし、衰え防止というところか。



栃谷橋は架け替えられるようだ 石に削られた堰堤 抉り取られた堰堤
何処まで行っても何ら記憶にない風景で、以前の記憶がある場所と対応させようがない。川が曲がる部分ではブッツケの岸が浚われ、樹木もない岩盤が立ち上がっている。栃谷の印象と言えば両岸から緑が覆いかぶさり、石と石の間には草木が生え、ヤブっぽかったような覚えがある。今はただただ明るく広く、無秩序に散乱した花崗岩のゴーロになってしまった。しかし水流は澄み切って美しく、御在所のような変色は見られない。水は澄んでいてもこの様子では渓魚は全滅だろう。



何処までも続くゴーロ 岩盤が剥き出しになった左岸 重なる岩塊
高度が上がるとやや谷は狭くなってくる。570mでようやくアザミ谷出合。この谷を登れば鏡岩の脇に出るはずで、上部は相当峻険だと思われる。出合は本流からの押し出しで石と砂の壁が築かれ、隠されてしまっている。一応土手に登って様子を確認するが、やはり登る気がしない谷である。ところで出合手前だったと思うが、栃谷で一番印象にあったヤブだらけの巨石堆積地は何処へ行ってしまったのだろう。丸ごと流出したのだろうか。想像すると背筋が寒くなる。
本流に戻るとすぐに雫石(しずくいし)が現れる。これは以前のままであった。推定700トンの巨石で、もう一つの岩との間から水流が落ちている。以前赤ペンキで何か書かれていたような記憶があるが、すっかり薄くなってもう読めない。雫石を右から越えて登ると左に崩れた窯跡があり、その先にも数百トンはあろうかという斜めになった巨石がある。この岩の上で休憩。



シズク石は無事だった その上の畳のような巨石 またゴーロが続く
その上はまた下部と同じようななゴーロであるが、630m付近に10mの滝がある。左右どちらでも越えられる。滝の落ち口に黄色い花が咲いていたが遠くて何の花か分からない。やがて左俣と本流の分岐。ここも土砂で塞がれている。以前の昭文社地図には栃谷に黒い破線が入り、この左俣がルートになっている。前回もここで左俣に入った。しかし少しだけ偵察しようと本流を登る。すると左上の高い斜面が崩壊し、樹木が流出して岩を含んだ土砂が剥き出しになっていた。土石流の元凶はこの付近かなと思う。



10m滝。左に隙間ができた 山腹斜面の崩壊 左俣出合。谷は土手の向こう(上流側から見る)
ここで戻って左俣に入る。本流と一転して岩は苔むし、緑が覆い被さった鬱蒼とした谷である。水はチョロチョロ、やがて伏流してしまった。いかん、水を汲み忘れた。また本流まで下りて2リットルほど汲んでまた戻る。体力をロスした。左岸には微かな道跡があったがすぐに消える。谷芯を歩くほうが楽だ。本流と違って角張った石が多い。やがて左からガレ沢が合流してきた。これも使えそうであるが、さらに進む。羊歯や潅木が繁茂し、北斜面で日も当たらず薄暗い。恐竜でも出そうな雰囲気である。急傾斜になってくると、いつの間にやら水流が出てきた。本流で水を汲んだことは全くの徒労となった。
急峻な支沢をいくつか見送ると、本流も異常な傾斜になってきた。岩も安定せず、これはなかなかの難物だ。破線の道はこの付近から右の斜面に逃げて県境稜線に上がっている。私は岩ヶ峰の尾根に出たいので、もう少し谷を登りつつ左折のタイミングを窺う。830m付近で左へ伸びる溝を見つける。何だ、もう岩ヶ峰の尾根が見えている。しかしこの標高差100mほどの登りは、見た目以上に急傾斜で足場も悪く、かなりの消耗戦となる。土が濡れているのがハンデだ。滑り落ちないようにシャクナゲの枝に掴まって肩で息をする。



左俣下部。角張った石が多い 谷中にタニウツギやヤブデマリが咲く クサソテツも多い
ようやく這い上がったのは岩ヶ峰のコル西端だった。谷では感じなかった強風が吹き荒れ、ときおり横殴りの雨粒が飛んでくる。ランチ場所を探して東へ歩く。以前のヌタ場だった場所は立派な池になっていて、上の枝にはモリアオガエルの卵塊さえぶら下がっている。付近一帯は天気さえ良ければ絶好のランチ場所なのだが、今日は強風とぬかるんだ地面で場所が定まらない。まあシートがあるからいいやと、風の弱い凹地に落ち着く。ここでヤキソバを作ったり、紅茶を飲んだりと一時間ばかりくつろぐ。周囲は落ちたベニドウダンの花が散乱しているが、まだまだ枝にもたっぷり咲いている。強風で寒くなってきたのでカッパをはおる。
しかしこの尾根にこんなにドウダンがあったとは気がつかなかった。サラサもあるがベニが圧倒的に多く、枝がしなるほど鈴なりに咲いている。これがブドウだったらなあと、つまらないことを思う。食えないのは仕方ないとして、何とか写真を撮ろうと試みる。しかし只でさえ揺れやすいドウダンは風にあおられてシャッターチャンスがない。風の僅かな止み間を辛抱強く待ってピントを合わせる。するとその一瞬にまた風がビューッと吹いて大揺れ。さすがに堪忍袋の緒が切れて 「ええい、くそ!コノヤロー」 と風に悪態をつく。いくら悪口を言っても風は何処吹く風・・・



立派な池になっていて驚く 鈴なりのベニドウダン 風に揺れるベニドウダン
八風稜線はガスで見えず、行ってもしょうがないので岩ヶ峰の尾根で帰ることにする。久々に鏡岩に寄ろうと、適当に急斜面を下りる。しかし何処でどう間違ったものか鏡岩に着かない。コンパスを見るといつの間にやら北に向かっている。振り返ったら遠くに岩が見えた。これはいかん。サーカスのようなトラバを強要されつつ鏡岩の岩塊にようやく到達。岩に登って下界を見るとよく晴れている。しかし三池付近はガスの中。風は相変わらず強くて、岩から振り落とされたら谷底へまっしぐら。帽子も飛びそうなので早々と退散する。
鏡岩からトラバしてP825西の鞍部へ到達。ここが本来の道だ。疲れていたので825を登らず右から巻いているうちにまたルートを失い、洞ヶ谷に入りかけ、またトラバで軌道修正して余計に疲れる。今日は全くなっていない。ヤマカンゼロだ。しかもこの付近は外すと地形が厳しく、疲労困憊してルートに戻った。
北山付近は踏み跡がしっかりしていて外すことはない。ところが710mで右折する道を見落とし、真っ直ぐ北の尾根に入ってしまう。このとき何処かでコンパスを落としたことに気付く。ポケットやザックを引っ掻き回しても出てこない。それにザックに挿していたLEKIのストックも消えていた。ヤブに取られたようだ。両方とも15年くらい使った愛着の一品。残念だが仕方ない。災厄の日来たれりか。まあ自分自身を落としてこなかったから良かったとしよう。

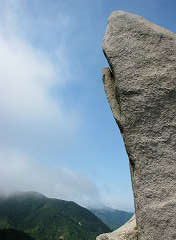

逆から見る鏡岩 鏡岩の上から三池岳方面を見る 北山から岩ヶ峰を振り返る
このまま入り込んだ尾根を下りても栃谷へ出るが、けっこう上流なのでやはり登り返して軌道修正。正規のP649の尾根に乗り換える。その後順調に岩場、砂地と通過し、犬尾山手前の鞍部から栃谷へ下りる。そこには青い重機が置いてあった。川で顔をや手を洗いながら反省しきり。
岩ヶ峰は7、8回は行っているはずだが、下りで3回も外すとは注意力散漫だった。こういうことは単独山行だから書かなければ誰にも分からない。しかしあえて恥をさらして戒めとしよう。おまけに長年の友、シルバコンパスとストックを失くした。多分外したところから復帰する途中と思うので、登山者に見つかる可能性も殆どない。しかしまあ、しょっちゅう物をなくす私と15年もよく一緒にいてくれたものだ。感謝。
追記: 栃谷工事現場は日曜で休みのようだったが、万一邪魔になるといけないので八風キャンプ場の駐車場に戻ってクルマを置いた。山から帰ってみるとワイパーに警告書が挟まれていた。「ナンバーを控えたので、二度とここに駐車しないように」 という暖かい?お言葉。何ら地元にカネを落とさず、遭難騒ぎだけ引き起こす登山者への目は冷たい。営業妨害ならともかく、この広い駐車場には他に一台も停めてなかったのである。しかし立場を逆にすれば無理からぬこととも思える。そう言えばキャンプ場よりずっと下に 「キャンプ場利用者以外は通るな」 という横暴な看板が立っていた。朝明にも八風にも居場所がなくなってきた。