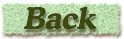治田銀銅山見聞録・青川峡 2015.9.20
御池・高昌・大蔵・コクイ・向山・蛇谷・・・鉱山と聞けばつぶさに見てきたが、なぜか治田鉱山だけは今まで未見であった。確たる理由はない。この領域はわりばしさんが熱心であり、かつて秋狸さんや宮指路さんを巻きこんでいたように記憶している。私は今頃諸先生方の後追いで、まずは現地見聞からである。
山中に人工的な遺物を見つけても、それが何なのか素人には判りづらい。まずは当時の採掘方法、精錬方法、専門用語、道具の名前など勉強せねば構築物の目的が分らないだろう。また、それぞれの道がどのような目的に使われたのか、人力・畜力・荷車を使い分けたのか?運搬するものは原石なのか半製品なのか、あるいは完全な製品なのかも知る必要がある。燃料である立木の権利はどうなっているのか。だが、私はそこまで調査する気は全然ない(^◇^)。
黒川静夫氏の本は十数年前に図書館で読んだが、手に入らないので重要と思われる部分だけコピーをした。そのまま現在まで放置。この前ふと手に取ってみた。江戸時代の地図は観念的なもので縮尺、方角は大雑把でピンポイントの特定は難しい。しかし出口幸雄氏の描かれた地図は二万五千図を基にしているので谷名・地名が手に取るように分かる。これは行ってみる価値があると思った次第。それに青川周辺は相当なスピードで地形が失われているので、後回しにはできない。
青川峡は林道が失われて以来、長大な河原歩きを強いられる。7月の茨川行きで思い知らされた。そこをまた行かねばならない。車が入れば本格的に調査もできないこともないだろうが、体力のなくなった私には苦行である。前回渡渉に苦労したので長靴で行く。登山靴は手提げ袋に入れて持って行った。しかし渡渉は楽だが、ゴロゴロの石で足が痛い。我慢しながら歩く。休みコバまで長い。退屈なので短歌でもひねろう。
荒涼の広き河原に我ひとり 朝日を背負い石を踏みしむ
ん〜。推敲の余地大ありだが、どうでもいいや。サルの群れが前方を横切って斜面を駆け上がっていった。上からバラバラと小石を落としてきよる。姑息なことせんで、正々堂々と勝負せんかい!と思った。ようやく休みコバ。といっても区切りにもならず、同じ河原が続くのみ。話が先に進まないので、もう銚子谷出合に着いたことにしよう。
先日痕跡も見つけられなかった隧道を再度探すがやはりない。さらに大通洞坑や橋脚跡、窯跡など探すが、もはやきれいさっぱり砂利の下になったようだ。諦めて久しぶりに大滝を覗いて来よう。まじまじと見ると立派な釜を持っている。巻きあがる風が河原で日に炙られた体に心地よい。檜谷を進むにはこの大滝が障害となって、日岡稲荷に上がるしかない。稲荷の先でまた道が崩壊しているので、急斜面を下って谷へ下りることになる。

治田峠へ道を分ける付近で長靴をデポし、登山靴に履き替える。この先濡れずに進めるかどうか分らないが、地形が厳しいので登山靴の方が安心である。檜谷は高い所に道があるそうだが、坑口を見落とすといけないので谷中を行く。しばらく進むと最初の滝で進退きわまる。釜は広い。沈思黙考、右の崖に取り付くと割と簡単に巻けた。しかし落差があるので怖い。
進んでも人工物は何もなく、間違えて支流に入ったのかと不安になる。しかし450m付近のカーブで立派な滝と出会い、左岸上に石垣が確認された。さてはこれがロクショウ滝か? GPSにポイント登録する。それにしても出口氏の地図よりかなり手前である。左岸の滑りやすいルンゼを這い上がると坑道が口を開けていた。これが仙右衛門シキだろう。古びた警告の札が下がっているが、頼まれたって入れるものではない。その先の石垣は仮設住宅跡なのか窯跡なのか私には分らないが、伸びた樹木が歳月を物語っている。


やがて多段(4段?)の滝が現れる。何だか進むにつれて逆に水量が増えるような感がある。檜谷は下流の賽の河原かはら想像できないような豊かな渓相である。今度は渓流シューズで入ってみたい。何気なく目を上げると対岸の高い所に穴がある。宗右衛門シキ? ハシゴを掛けて出入りしたのだろうか。その先すぐに、それは美しい釜をもつ滝があった。他の滝壺と全然色が違う。相当な水深があると思われる。見とれていると右端に明らかに人工の穴が開いている。三つ目の穴であるが、これは水抜きかも知れない。



出口氏の地図に「高コバ」という文字がある。一見檜谷右俣かと思うが、語感からして谷名であるはずがなく、七曲りの坂上の平坦地であろう。適当な所で谷を捨て斜面に上がると石垣がたくさんあった。炭釜に見えるが、場所からして黒川本P51にある床屋・焼窯跡だろう。床屋とは散髪屋ではなく精錬所のことなり。このあとツライ登りをこなすと、はっきり道型のある尾根芯に出た。ここで谷を離れる時、昼食用の水を汲み忘れたことに気付く。大失態だ。まあどうにかなるだろう。ジグザグが七回あったかは定かではないが、この尾根が七曲りなのは確実。でも藤堂係長率いる七曲署はなかった(^◇^)。しかし三光谷には寺があったというから、鉱山の荒くれ者を取り締まる警察署があったとしても不思議ではない。620mで小広い台地に出る。ここが高コバであろう。プレハブぐらい建ちそうな広さであり、集積に使われたかもしれない。
高コバから左へ明らかなトラバース道がある。古い道が未だに残っているのは驚きである。登山者が通ると言っても余ほどの好き者が年に数回程度だろう。どんどん進むと小谷のある場所に大きな杉があった。黒川本にある添水銀山の入口というべき場所だろう。この小谷にはチョロチョロと水が滴っていた。ラッキー! 結果的に重い水を担いで七曲りを登らずに済んだ。


明日ありと思ふ心のあだ桜
夜半に嵐の吹かぬものかは(親鸞)
水場を見つけたからと言って、後で昼食にしようと思ってはいけない。どこかで転落して昼も食えずに死ぬかもしれない。先のことは分らない。だからここで、ただちに昼食だ。湯を沸かしているとストックがないことに気付いた。最近よく置き忘れる。どうせ高コバだろう。そうでなければ諦める。
今日は夕方用事があるので長居はできないが、もう少し先を見に行く。窯跡はあったが坑口はもっと先だろう。添水銀山の探索は次回としよう。この付近へ来るなら茨川まで車で入って、伊勢谷を上がった方がうんと楽だ。長い河原歩きはもう懲りた。高コバへ戻ると案の定ストックはあった。中尾から帰りたいので、・614までトラバースしよう。はたしてそこには薄い道型があった。しかし山神谷の源流で崩れていた。木がないので展望はよい。南にクラのピークとガラン谷の崩壊が手にとるようだ。残りの距離は近いので適当にトラバースすると・614へ出た。高コバに比べると細長い地形だ。地図を見ると左は与平次谷の源流だ。下りていきたい衝動に駆られるが、長靴の回収に不都合だ。今日はおとなしく帰ろう。
中尾は少々急な痩せ尾根だが、通行に何も支障はない。この地面の下は両側の谷から坑道が掘られている。そう思うと妙な心地だ。陥没して穴に落ちたらなんて、ありもしないことを心配する。途中で右へ下りると長靴デポ地点まで近いが、凄い急斜面で下りられそうもなく、末端まで行くしかない。尾根の末端が崖で下りられないというオチも良くある話だが、ここはどうだろう。ズルズルの急斜面だったが、何とか着地して長靴の回収に向かう。
頑張るなり工夫するなりすれば登山靴で渡れないことはない。ちょっと靴の交換地点を引っ張り過ぎた。と、言う訳で帰りは行けるところまで登山靴で行く。ガラガラの河原は長靴よりも歩き易い。結局もう一度履き替えたのは最下流だけだった。三鉱谷も見なければならないが、長大な河原を思い返すと気が萎える。林道工事が何時までかかるかは不明。
追記:青川は鉱物マニアには少しばかり名を知られた場所らしい。方解石、水晶、蛍石、孔雀石、電気石、沸石・・・更に門外漢には聞いたこともない石の名が続く。こういうのをスカルン鉱物と言い、石灰岩などの炭酸塩岩中に花崗岩などのマグマが貫入してきた際、その接触部付近にできる鉱物の総称である。その地殻変動において銅や銀も集まるらしい。そういえば竜ヶ岳、青川は石灰岩(御池・藤原)と花崗岩(御在所・釈迦)の山の中間位置にある。鉱物マニアは湯の谷、滝ヶ谷、ガラン谷など結構危ない場所にも足を伸ばしている。
江戸時代の鉱山と言うと随分昔のように感じるが、こうした地球の営みから見れば直近の出来事と言ってよいだろう。