鈴鹿関連書籍
冬虫夏草 著者 梨木香歩 ![]() 新潮社
新潮社
鈴鹿が舞台となった小説を台高の主、zippさんに紹介してもらった。梨木という人は聞いたこともなかった。何せ私の読む本の著者はすべて鬼籍に入っている。自慢じゃないが現代作家の本は全く知らず、毎年ノーベル賞候補に挙げられる村上春樹だって一行も読んだことはない。このままでは化石頭になりそうだ。で、何故zippさんが紹介してくれたかと言えば鈴鹿山脈、小椋谷の事が書かれているからだ。政所、蛭谷、君ヶ畑、茨川辺りは登山を始めたころ神秘的で憧れの地域だった。今でこそトンネルができて簡単に行けるようになったが、当時は嫌になるほどハンドルを回して危険な石榑峠を越えなければならなかったのだ。
単行本を通販で手に入れた。美しいイワナが描かれた装丁である。が、実物と比べるとちょっと口先がとがり過ぎかな。タイトルの筆文字は実に素晴らしい。こんな字が書ける人が羨ましい。表紙をめくると枠の中に何だか「遠野物語」風の文章が書いてある。要約すれば主人公の綿貫征四郎くんは亡くなった友人の家を委託されて自然やら妖怪やらと交際しながら原稿を書いておるということらしい。
各章のタイトルが草木であることは洒落ている。鈴鹿でもおなじみの植物たちだ。節黒仙翁など出てくると何か嬉しい。本文を読む。征四郎君は一流作家なのか三文文士なのか知らないが、編集氏が熱心なところを見るとそこそこ売れているのだろう。女流作家が書く男というものは少女漫画に出てくる男と同じで、何故か現実感がない透明な存在に思える。征四郎君も毒がなく実体が希薄な感じがする。まあこれは著者が狙ったのかもしれないが。
ページをめくれどめくれど鈴鹿なんか出てこない。貧乏文士の所に図々しくて妙な学究南川など高等遊民が訪ねてきて浮世離れした話をして帰っていくのは漱石の作風を思わせる。最初気付かなかったが、高堂が訪ねてくる場面は幽霊なのか?冒頭の囲いに「亡き友」とあるが・・・どうも本作は「家守奇譚」の続編らしいが読んでいないので分からない。
いったい何時ごろの何処の話なのだろう。カイゼル髭、インパネスなどの言葉から時代設定がかなり古いことは分かる。明治か大正か。場所は文中に叡山や朽木村が出てくるので湖西南部と思われる。やがて減ってはいるがオオカミが出るという話が・・・最後にニホンオオカミが確認されたのが明治38年だから、それ以前ということになる。市中に最近できた電車に乗りに行ったという話は有力だ。市中とは京都のことだろう。ググってみるとそれが明治28年。だから明治30年前後の話だろう。
ちっとも山へ登らないので退屈で一度表紙を閉じる。何気なく帯を見れば「百年少し前の物語」と書いてある。なーんだ、せっかくの時代考証が無駄になった。本書の書き始めが2006年だから100を引けば明治39年。で、残りの「ちょっと」を勘案すればほぼ推測通り。著者の年齢を調べると私より四つも年下だ。それで明治の話を書くには相当な下調べが必要だろう。もはや太平洋戦争の聞き取りでさえ90歳以上の老人が頼りという時代だ。いっそ明治ならば知っている人がないので気楽かもしれぬ。帯裏を見れば場所も書いてあった。疏水とは琵琶湖疏水のことだろう。ということは大津から京都の間である。
70ページ辺りからいよいよ鈴鹿の旅へ出発だ。しかし動機が行方不明の愛犬探しと、イワナ夫婦の営む宿へ泊ることの二つであることが通常の小説ではないことを物語る。いわゆる山村奇譚の領域である。普通に考えれば大津から逃げた犬を鈴鹿山中で探すなど、可能性は思い切り低いし、イワナ夫婦に至っては何をか言わんやである。妖怪が出るといっても遠野物語のような怖い系ではなく、宮沢賢治風の透明で明るい雰囲気がある。
ちょっとあほらしくて肩透かしを食ったが、それは私が著者の本を初めて読むからだろう。まあそれはそれで御伽噺と分かって読めば問題ない。実際この物語の中では実在する生き物も空想上の生き物も平等に描かれている。河童や天狗、幽霊やイワナの半魚人!も。犬のゴローはもはや尋常ならざる人格(犬格)を備えていて神の遣いかと思われる。人々、特に綿貫君にとってはそういう者がいて当たり前らしく、一々驚きもしない。
この物語の白眉は現在の永源寺ダムの周辺に点在する集落(佐目、相谷、萱尾、九居瀬)の人々との交流であろう。山村の生き生きした風俗が存分に描かれている。著者は現地踏査、古老の聞き取りなど苦労されただろう。それでも明治の記憶を持つ人はいないから、相当文献も調べ、それで足りないところは類推や空想力ということになる。方言も味がある。私は鈴鹿山脈を隔てているとはいえ、直線距離では近いところに育ったので説明なしでもすべて分かる。土地の人とのやり取りは古典落語を思わせるユーモアもあって楽しくて飽きない。
文中に白鹿背山やサメゴ谷、御池鉱山や日丘稲荷などマニアックな名が出ると鈴鹿ファンとしては大喜びだが、この地と縁もゆかりもない他の読者にはどう映るのだろう。ともかく主人公綿貫君は寄り道ばかりして、いつになったら肝心の蛭谷や茨川に行くのかと思ったが、読後にはこの寄り道こそが本筋であったと知れる。
小椋谷の村々の描写は思っていたより淡白である。箕川など通過しているはずなのに名前も出てこない。筒井神社や金竜寺の深い話も出てこない。茨川での滞在もなかった。この辺りが一時茨川調査に熱を上げた私には食い足りないところだ。だがここではイワナの宿に泊まらねばならないから仕方ないか。この本を読んだらイワナを釣って焼いて食おうという気が失せる。倫理的な事ではなく気味が悪い。でもすぐ忘れるだろうな。まあ神崎川の方でなくてよかった。
茨川近くの龍の棲む大滝というのは三筋の滝のことだろうか。しかし滝裏に洞窟などない。イワナの宿は治田峠へ向かう伊勢谷付近にあるようだ。立て札に「おやど いわな」と覚束ない字で書いてある・・・という描写は賢治ワールドを彷彿とさせる。宿の建物は鉱夫目当ての女郎屋の跡だというが、まさか治田峠を下りて「下り藤」までは行っていないだろう。伊勢谷上流は傾斜が急で、お宿の適地はなさそうに思えるがどうだろう。茨川へ入る前のノタ坂の描写もないし、著者がどの程度現地を歩いたかは不明である。お宿から来た道を戻らず三筋の滝へ行ったというのも解せない。だが山岳小説とは全くジャンルが異なるので、リアルさを求めるのは野暮というものだ。
高堂の口から佐目付近の村々が水難に遭うような予言が出てくるが、今となれば永源寺ダムのことと容易に知れる。計画が持ち上がったのは戦後だから、本当に当時予言があったなら凄いことだが、これは現代に生きる著者の創作だ。伝統的で素朴な山村の生活を奪う現代文明の在り方を問うのがこの本のテーマなのかもしれぬ。だから佐目周辺を入念に描いたのだろう。宿の風呂でウロコ?を落としていった謎の死にかけ男は竜の化身という解釈でいいのだろうか。賢いゴローも竜神の遣いとしてそれを阻止するために小椋谷で働いていたのだろう。でもダムが現存するからには結局それはならなかったのだ。今度ダムのはたを通るときはゴローのことを思うだろう。
2017年11月
歌集 『千春萬冬 鈴鹿の山を謳う』 著者 石井明子
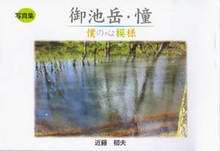 御池岳・憧 著者 近藤郁夫
御池岳・憧 著者 近藤郁夫
近藤氏久々の写真集。鈴鹿の山ばかり登る人も珍しいが、近藤氏のようにその中の一山だけ登る人は、もはや人間国宝と言っても良いだろう。氏の御池通いは現在も続いており、その蓄積が何らかの形で表出するのは必然であったとも言える。
前作「彩」に続いて御池岳とその自然に対する愛情が詰まっている。対等な愛ではなくタイトル通り憧れであり、自然崇拝に近い。形態は写真集だが、詩・散文・歌がセットになって完成度を高めている。今回は山仲間の作品も掲載され、幅広い内容となっている。
裏表紙にはドリーネの前に佇む著者の姿がある。足の開き具合とひざの角度、重心の位置、手の力の抜け具合。表情は見えなくとも、御池岳の見せる風景に呆然としている様子がありありと伝わる。
2004年8月 みずほ出版 ¥700
 YAMAPシリーズ ⑬ 鈴鹿大峰大台ケ原
YAMAPシリーズ ⑬ 鈴鹿大峰大台ケ原
著者 金丸勝実 小嶋誠孝
YAMAPとはガイドブックと地図が一体になった形態の本である。普通のガイドブックの地図はオマケ程度であるが、本書は5万、あるいは2万5千の地図が掲載され、各ポイントの詳しい情報が書き込まれている。つまり携帯して現場で使える本だ。
鈴鹿担当の金丸氏はご存知HP「歩人倶楽部」管理人である。特に花情報で定評があり、花の山旅シリーズの鈴鹿・伊吹の著者でもある。私も他のガイドブックの一部を担当してみて、この仕事は楽ではないことが分かった。自分の休日スケジュールを犠牲にして、一枚の写真を撮るために、何度も同じコースを登らなければならないこともある。分かりきったことでも全国版となれば確かな裏付けも取らねばならないし、出版社の指示が変わることもある。
このような割に合わない仕事を、黙々と何冊も続けている著者の姿勢には頭が下がる。本職と同じく、生まれながらの教育者なのだろう。
コースの設定はよく練られ、特に著者自身が撮影した写真が美しい。またモデルとして鈴鹿関連のホームページ仲間が登場しているのも楽しい。
2004年8月 山と渓谷社 ¥1400+税
鈴鹿の山で見られる花
監修 村長昭義 編集 鈴鹿の山 花散策会 発行 今村悦子
植物図鑑は幾らもあるが鈴鹿に特化した図鑑は貴重であり、また鈴鹿ファンにはより使いやすい。地元を中心とした登山者の手によって、このような図鑑が誕生したことは意義深い。ザックに入れても苦にならないハンディーなサイズに約500種が収録されている。しかし鈴鹿には2000種を越える植物があるそうで、この道も奥が深い。続編も計画されているようで楽しみである。写真もなるべくその種の特徴を表現するよう工夫されている。花オンチの一人として、製作に携わった方々の労に感謝したい。
初めて出会った科も分からない花を、どういう工夫ですばやく目的のページに導くかはすべての図鑑共通の課題である。また絶滅危惧何類と言う表記によって、保護意識の高まりがある一方、盗掘の誘引になりかねないジレンマもある。花の名前を覚えようという人に悪人はいないことを信じる。
2004年3月 東海出版 ¥2000
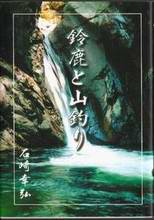 鈴鹿と山釣り 著者 石崎幸弘
鈴鹿と山釣り 著者 石崎幸弘
「鈴鹿と山釣り」という本が出たことは知っていた。既にすっかり釣り熱が醒めていたので、何となく買わずにいたらある人から頂戴した。著者の石崎氏は当サイトから相互リンクしている Introduction渓流 のブルーリバーさんである。
まえがきに「本書は釣りのガイド本でもなく技術書でもない」とある。そしてのっけから廃村茨川のことにかなりの頁が割かれている。首を傾げたくなる箇所も二、三あったが、私の知らないことも若干記述されていた。
以前から思っていたが、海釣りをする人種と山釣りを好む人種は歴然と違う。開けっ広げの大海原に向かう人と、独りで日の当たらぬ薄暗い谷間を徘徊する人が同じ気性であるはずがない。このあいだも山本素石のいたノータリンクラブ関係者から、本を出しましたとの連絡が来た。渓流人はもの想い、もの書く人が多い。山人舎の辻氏も然り。山奥へ入れば必ず目にする山村と民俗、植物、生物、地質などに次第に惹かれていく。そして最後はコンクリートで固められ、窒息して死にゆく川を目の当たりにし、河川行政にひと言言いたくなる。都会人の目に触れぬ山奥で、林道や堰堤工事はやり放題である。
本書には登山者にもおなじみの御池川、茶屋川、神崎川の自然が、豊かな感性で描写されている。そして自然と人間の関係を問いかける。釣りをしない人にも、一度目を通して頂きたい本である。
2003年6月 サンライズ出版 ¥1800+税
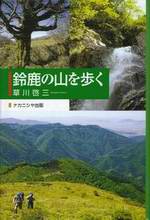 鈴鹿の山を歩く 著者 草川啓三
鈴鹿の山を歩く 著者 草川啓三
草川啓三氏の名は、誰もが持っている鈴鹿のエアリアマップでおなじみである。地図の調査執筆者であることは、誰よりもよく山を歩かねばならない。氏には三十年に亘る鈴鹿逍遥の蓄積がある。本書はそういう著者の作品ゆえ、得難い味わいがある。
本書はコースガイド、エッセイ、紀行文、写真の複合書である。著者がやりたいことをすべて盛り込んだのだろう。ガイドブックのように出版社の意向や注文に縛られることなく、自由闊達に山が語られている。特に「あるく・みる・きく」が面白かった。「やはり池と出合うのは天気の悪い日に限るものだと思った」・・・こういう感性が素晴らしい。
冒頭のフォト&エッセイもいい。好きな文章は「新緑の道」、好きな写真は「道の誘惑」にある杉峠道だ。著者には人生の大先輩というイメージを抱いていたが、プロフィールを見れば団塊の世代であり、自分と数年しか違わないことに驚いた。しかし鈴鹿道に関してはやはり大先達である。その達人にして帯のコピーには「鈴鹿の山との付き合い方が少々わかった」とある。少々である。山歩き道の修行も深淵の底は見えない。
2003年4月 ナカニシヤ出版 ¥2500+税