黄葉紅葉(こうようこうよう) 御池岳亀尾吟行−山頭火的自由律俳句の試み
御池杣人
黄葉紅葉 朝陽に陰影の妙 (コグルミ谷登山口)
黄葉紅葉 歩きはじめの 息はずむ
黄葉紅葉 天ケ平 秋をしている
黄葉紅葉 流るる水にも (真ノ谷)
黄葉紅葉 枝に根に助けられ よじのぼる (亀尾)
黄葉紅葉 ぶなの幹の 白さよ
黄葉紅葉 ぶなに抱かれており
黄葉紅葉 うんとこしょ どっこいしょ
黄葉紅葉 見下ろせば 亀尾も (東のボタンブチ)
黄葉紅葉 散りて奥ノ池の 残雪の
黄葉紅葉 美味と絶景の 昼下がり (昼食)
黄葉紅葉 友の笑顔もまぶしく
黄葉紅葉 広き尾根の 窯の跡にも (1241から真ノ谷)
黄葉紅葉 傾く陽に陰影の妙
(天ケ平)
黄葉紅葉 彩りの深みを下る
(コグルミ谷)
御池杣人の自由律俳句について 葉里麻呂の曾孫
曽祖父は2002年晩秋に御池杣人ら10名と御池岳を巡ったようで、先日遺品の整理中に杣人からの書簡を発見した。すでにあんぽんたんパロディーは大量に見つかっていたが、俳句は初めてであり貴重な資料となろう。私は自由律俳句は門外漢であるので、曽祖父がその書簡に鉛筆で走り書きしてあった感想を記しておこう。
黄葉紅葉と言う文字が乱舞する絢爛たる色彩感覚は氏の子育て本にあった子息の「ひゃくまんまいの葉」に通じる。言葉は饒舌ばかりが能ではない。ぎりぎりまで贅肉をそぎ取った句は写真を思わせる。如何に無駄のないフレームで、表現したい事に焦点を合わせられるかである。それに比べると短歌という形式は冗長にも思えるが、それはそれで優雅なリズムに堪えられない良さがある。
真ノ谷の句をみれば誰しもあの雪解けの清冽な流れを思い出すだろう。飲みたい水が音をたててゐた(山頭火)。
枝に根に助けられ・・・氏の口癖であった「御池岳に遊ばせてもらう」に通じる自然に対して謙虚な姿勢が見て取れる。
ブナの二句は抱きつきながら抱かれていると言う感覚、肌の白さ。意識せずとも本能的に母を感じているのではないだろうか。
うんとこしょどっこいしょ・・・ 急登も楽しめるのが山ヤ。苦しいけどメチャ楽しいと言う感覚がよく出ている。
亀尾もの「も」と言う一文字で眼前の光景の広大さを表現している。汗を拭きながら自分のたどって来た行程を振返る充実感。
美味と絶景の・・・出ました。絶景かな美味かなのフレーズ。味わう器官が違うだけでどちらもご馳走。
 友の笑顔・・・暖かさの感じられる句。単独行と異なる良さもあり。眩しい笑顔がもみぢに染まる。
友の笑顔・・・暖かさの感じられる句。単独行と異なる良さもあり。眩しい笑顔がもみぢに染まる。
傾く陽に・・・初句と対になって時間の経過を表現する。
深みを下る・・・紅葉も尾根と谷では味わいが微妙に違うことよ。
御池杣人は晩年放浪の旅に出た。山頭火の影響を受けたのだろうか。「風の中おのれを責めつつ」ちりりんちりりんと諸国を歩いたが、とある一軒の家で大量のアンパンの施しを受けイッキ喰いをしたため喉に詰まらせてあえない最後となった。よほど腹が減っていたのか、あるいは己を責めきれなかったのかは定かではない・・・南無阿弥陀仏。
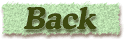
 友の笑顔・・・暖かさの感じられる句。単独行と異なる良さもあり。眩しい笑顔がもみぢに染まる。
友の笑顔・・・暖かさの感じられる句。単独行と異なる良さもあり。眩しい笑顔がもみぢに染まる。