読者投稿 とっちゃん(沢の短歌)
 水流に 打たれて嬉し 煩悩の この身を抜けて 沢を下りし
水流に 打たれて嬉し 煩悩の この身を抜けて 沢を下りし
淵に入り 淵にとけたる 哀しみよ 今は無心の 蒼となる吾
喉ごしの 心づくしの 素麺に 冷えし体も 心はあつき
凛として 立つ一条の 水流と 無心に遊ぶ 人の幼き
閉塞の 心を開く 大滝よ 飛沫を浴びて 清々(すがすが)し我
両の手で すくいし蒼は 透明の 水滴となり 淋しさ洗う
こんなにも 解き放たれて ここにあり 白き磐だな 蒼き流れよ
緊張の 時を越えたり その後(のち)の 心一つに なりて嬉しき
心決め 淵にその身を ゆだねれば 跳ねる水音 簾の飛沫
管理人 なかなか普段から悩み多きお方とお見受けします。下界で溜め込んだ懊悩を沢の流れに癒してもらうと言うテーマが見えますね。無心になって煌く水と戯れているうちに、悩みは水に溶け去り、明日からまた頑張れるという事でしょうか。 感傷的な言葉は啄木を彷彿とさせますが、読後は爽やかですね。ところでこんな歌があります。
年々に 思ひやれども 山水の 汲みて遊ばん 夏なかりけり
訳 毎年毎年、山へ行って清水を汲んで遊びたいと思いながら、そういう夏はやってこない
誰の歌だかご存知ですか。なんと明治天皇御製です。当時の天皇は今と違って本当の国家元首ですから、国務に忙殺されて好きな山遊びもできなかったのでしょう。その点とっちゃんは悩み多き人生といえども沢遊びに行けるだけ幸せではないでしょうか。
ところで皆が愛知川で煩悩を洗い流すと琵琶湖は煩悩で溢れてしまいますね。それはいったいどうなるのでしょう。魚が食べてくれるのかな。そうじゃないとその水を飲まされる京都、大阪府民はたまらんわね。
・・里山の小さき沢の流れの小道にて・・・
鷺草
涼風(すずかぜ)に 揺れる翼よ 白き花
真昼間の谷 長閑(のどか)な時空
とことこと 沢を流るる 水音に
和み(なごみ)の花の 真白き笑顔
桔梗
沢向こう 呼ばれるように 振り向けば
秋紫(あきむらさき)の 花の優しさ
 吾木香(われもこう)
吾木香(われもこう)
あなたはその地味な花姿と花色で
心の中でなんだかちょっと寂しそうに微笑んでいる
思いもかけず あなたに会えて そっと指で触れてみた
初秋(はつあき)の沢沿いのこの道にあなたがいてくれた喜びよ
知る人も無き吾木香
管理人 もう秋か・・・キキョウとワレモコウは旬の花ですね。女性らしい感受性が素晴らしいです。私には死んでも書けない詩を有難うございました。サギソウやキキョウは殆ど見られなくなり、外来種が幅をきかす里山ですが、いつまでもこの可憐な花が見られる日本であってほしいと思います。
都津茶女の歌に寄せる 御池杣人
凛として 立つ一条の 水流と 無心に遊ぶ 人の幼き
愛知川に戯れて遊んでもらっている姿が幾重にも浮かんでくる。自然は小さな人間の煩悩を洗い流してくれる大きな存在だ。しかし、煩悩に無自覚な愚かさのなせることについては洗い流してくれない。心して生きねば。
吾木香−この文と、それに添えた葉里麻呂の写真から漂ってくる叙情。我が敬愛する山本萠(女流書家−『御池岳残雪』あとがき、HP
「ふきのとう書房」参照)の文から引用してみる。
・
・・ふるさとの漁村を抑制の効いた色調で油彩に描く、一人の若者の澄みきった瞳に魅せられていた時期、他愛もなく
・
「何の花が好き?」
・
と問うと
・
「われもこうだよ」
・
と予測もしなかった応えが返ってきたことがあった。
・
私は、まだ見ぬまぼろしの花われもこうをまぶたの裏に描き出して、その名を一生忘れまいと、幼い決意をしたのだった。
・
辞書をひもとくと、「吾亦紅」という文字にはっとして、咄嗟に「吾亦恋」とノートに書きつけていた。
二十数年も前の実ることのなかった未熟な恋が、こうして今頃になって、貧弱な庭の一隅で夢の穂を細く伸ばしている。年を経ても、私は自分があの時分から少しも大人になっていないことを憶った。・・・山本萠『花に聴く』
都津茶女殿のさらなるご精進を祈る。いつか御池岳に遊んでもらいましょ。
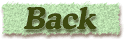
 水流に 打たれて嬉し 煩悩の この身を抜けて 沢を下りし
水流に 打たれて嬉し 煩悩の この身を抜けて 沢を下りし 吾木香(われもこう)
吾木香(われもこう)