読者投稿 龍ガ岳・・・「シロヤシオ幻想に寄せて」・・・ 都津茶女
夕闇が迫る頃には鹿眠る 老木(おいぎ)の花に夜露凌(しの)ぎて
 散り花のその花群れに包まれて 寄り添う鹿のまどろみの夢
散り花のその花群れに包まれて 寄り添う鹿のまどろみの夢
白龍の化身となりて天(あま)駆ける 星ふる闇に花舞いの妙
龍の山満月照らす静寂に 五葉躑躅の白さ清々
笹原に明けくる空は色染めて 白きヤシオに光りさす朝
この朝に咲きしばかりの乙女らは 小首かしげる初々しさよ
陽を透かし若葉の葉さき紅に染め はにかむように花笑う時
初夏の風 花簪(かんざし)に照れ笑い 笹の葉纏(まと)う孤塁(こるい)の山よ
竜神の宿れる山に咲く花も 慈雨(じう)の恵みに蕾を濡らす
花衣 纏し君は微笑みて 雨乞う人の安らぎとなる
いましがた雨水(うすい)含みし松肌に 触れれば老木(おいぎ)の年輪を知る
見上げれば浅き緑のその木陰 君の笑顔に切なさ匂う
山飾る花はなにをか語ろうか なにも語らずただ見ておりぬ
移り往く時を見ておりシロヤシオ 名のみ残れるこの池ノ平(ひら)
 羊雲 空から降りし笹の海 龍を抱(いだ)いた山堂々と
羊雲 空から降りし笹の海 龍を抱(いだ)いた山堂々と
笹を分け山に向かいて立つ人の 背中(せな)にあふるる愛惜の念
緑葉にうつむき笑う白き花 無垢なるおまえの心をうつす
老木に零(こぼ)るるごとく咲く花に 切なさせまる花盛りの白
今はただ命の限り咲く花よ 若葉萌え木に松肌の老い
散り花は天を仰ぎてなに祈る 一陣の風に儚(はかな)き命
華やぎた季節の後(のち)は静まりて ただ照りつける陽射し厳しき
・・・自然が与えてくれた心の共鳴は、その風景を見た者にもまだ見ぬ者にも、心の
響きを伝えてくれる。・・・
「傍らに心響ける人ありて 無類の友見る風景を見る」
「共鳴の心の波は広がりて 人それぞれのヤシオ幻想」
御池杣人氏評
この都津茶女の一連の歌を鑑賞するためには、まず葉里麻呂の山行記「シロヤシオの幻
想」(03.05.18)をお読みいただきたい。
昨年の、やまぼうし殿を世話役とする鈴鹿写真展にて、極めて印象的であった作品に葉
里麻呂の写真−シロヤシオがまるで羊の如く群れている龍ケ岳の写真−があった。思わず
僕はうなった。こんな姿を鈴鹿の山は見せるのかと。
今回の山行記も相変わらず快調だ。わけても冒頭の「笹深い斜面の中でその木の周囲だけ
ポッカリと空間が開き、強い鹿の臭気を放っていた。」がすばらしい。一回の山行き、そこ
には無数の凝縮した事実と出会う。出会いつつ、とりとめのないことも、心動かされるこ
とも、いっぱいある。山行記に何から始めるか。どんな文体で。
出だしの出色さは、当然ながら文全体を引き締める。結びも余韻を残しつつ、締まって
いる。葉里麻呂調の文が、途中とろいことも含みつつ(「男の幻想」なんてカッコよすぎ
る。まあ、僕もそうだが「男のひとりよがり」の方が的確だろう)形になりつつある。う
れしいことだ。
そうだとしても、この短い山行記を読み、たとえ情景を思い浮かべる作業をしたとして
も、都津茶女のこの一連の歌「シロヤシオの幻想に寄せて」(実に21首、結びに加えて
いる歌を入れれば何と23首)をどう評したらいいのだろう。葉里麻呂の文がこれほどの
世界へと誘因する力をもっているのか、はたまた都津茶女の繊細で豊かな感性と知性、想
像力と創造力を讃えるべきなのか(前者だと悔しいので、後者にしておこう。そう、後者
に決まっとる)。
都津茶女の歌は全体に5連から成っている。1連の4首−ここでは彼女は登山者が去っ
ていってさらなる静寂の世界、夕方から夜へと至る時の推移、「鹿のまどろみ」「星」、
「月」が音もなく老木を照らしている世界を描く。それは時に「星ふる闇に花舞いの妙」
の世界でもあったのだ。
2連では、明け方のひきしまった空気、そこへと朝の光、やがて白昼へと。静かに時は
推移していく。やはり登山者はいない。
「この朝に咲きしばかりの乙女らは 小首かしげる初々しさよ」−この歌こそ葉里麻呂言
うところの「男の幻想」、僕の言葉では「男のひとりよがり」そのものゆえ、中年のおじ
さんたる僕は泣きました。しかし、考えてみれば、これを歌ったのは都津茶女なんだから
、別に男と限定することもないかと思いなおしたところ。だけどやはりいいなあ。
第3連に至ると場面は大きく転換する。雨にうたれて揺れているシロヤシオ。都津茶女
の感性は縦横無尽だ。
「山飾る花はなにを語ろうか なにも語らずただ見ておりぬ」
お見事。つい先日、僕はある花と語りに御池岳へ。まさに花は「なにも語らず」僕は「
ただ見ておりぬ」だった。この間の僕の御池岳行き、特に単独行時は、ほとんど「ただ見
ておりぬ」ということをするためのもの。その時間を持ちたいがためのような気がする。
しかし、都津茶女の歌を今一度詠むと、「なにも語らずただ見ておりぬ」の続き具合いは
、どうやら花が「ただ見ておりぬ」と解釈すべきだろう。とすると、花は何を見ているの
だろうか。まさに花を見に来た人を「ただ見ておりぬ」のだろうか。そうならば、僕は花
に見られに御池岳を歩いているのかも。そうか、先日はあの花に見られに行ったのだ。も
ちろん、あの花は何も語ってくれなかったが。
第4連−都津茶女の位置はやや距離を置いた位置に移る。時は昼。お日様が照っている
。そこへ登山者。登山者は昨夜の自然の営みも、この地の雨も直接は知らない。だけど、
やはりこの登山者は今年も花に「見られに」来たのだ。
第5連は老いと青春の同居という哲学的命題へと思索する。僕たちもそのとおり。生き
ていくこととはあらたな何かを獲得しつつ同時に何かを喪失していくこと。僕たちははた
して齢を重ねながら「切なさ迫る花盛りの白」たりえているだろうか。
都津茶女の結びもいい。
「傍らに心響ける人ありて 無類の友見る風景を見る」
山行き、あるいは大きく人生の豊かさとは、まさにこれでないか。「傍ら」の物理的距
離など問題ではない。僕たちにとっての「傍ら」はそんな次元ではない。「心響ける人」
の存在の多様性こそ、僕たちの山行きの、あるいは煎じ詰めれば人生の彩りの豊かさでは
ないか。
「無類の友見る風景を見る」−花を見ることは実は花に見られること。「無類の友」に
見られ、「風景に見られ」に僕は山行きを続けよう。「心に響ける人」の存在の多様性を
信じて。
御池杣人
管理人
この一連の歌は四部に分かれていて順に夜、朝、対面、命が副題になっているようである。全体を貫くのは地球に生命が誕生して以来、倦む事を知らず営々と続く時のリズムと生命のサイクル。時は酷薄にも生命に老いを与える。しかし限りある故に命は儚くも美しい。と同時に命は逞しい。個は消滅しても種は連綿と受け継がれていくのである。母なる大地の上に人も鹿もシロヤシオも・・・
作者の感性あふれる一連の歌からそんなことを思った。それにしてもシロヤシオ一つでこれだけの歌を作ってしまうとは、都津茶女の才能恐るべし。第四首の「満月照らす〜白さ清々」の情景は実際見てみたいという気を起こさせる。純白の花ゆえに反射する月の光は妖しいほど美しかろう。ドビュッシーの曲が聞こえてきそうだ。
雪を纏ったかと見まごうシロヤシオもあれば、ちっとも花をつけないシロヤシオもあった。そのズボラなシロヤシオに、現場にいながら一首も詠めなかった自分を重ね、身につまされる管理人であった。投稿いただいた都津茶女に感謝。
そして御池杣人氏の評はどうだ。「ヒモ生活の片手間に教鞭をとっているのではないぞ」ちゅうことを世に知らしめる名解説ではないじゃろか。都津茶女の歌に理路整然たる詳細な分析を加えている。同時にそこには努力した人にはご褒美を・・という愛があふれている。自分の生徒でもない人に対する無償の愛。これぞ教育者魂ではないだろうか。
杣人氏はまた管理人の山行記にも言及頂いた。有難いことである。今回は一般路の調査だったため、地形ガイド的なものをやめて自由に書いてみた。トロさついでに書けば管理人が思い描いたシロヤシオの淑女とは、今は亡き夏目雅子であった。「男のひとりよがり」も過ぎましょうや?
「綾織の一枚の着物」
葉里さんの、「シロヤシオ幻想」は、今年になって無重力の世界にいるように心彷徨
う私に、再び短歌を歌わせてくれた。そのエッセイが、どんなに心嬉しいものであっ
たか。
素人の短歌は言葉使いもでたらめで、ただ感性のみの駄作である。その短歌とも言え
ないような短歌に御池杣人様の寄せていただいた論評を読み進むうちに、知らず知ら
ずに私の顔も心もほころんでいる。作者の思いに読み手の思いが新たに生まれてい
く、それはなんとも嬉しいことだ。
こんなふうに、次々に喜びが反響して、またまた喜びを生んでいくことの嬉しさ。花
も風景も山旅も、友との心の交わりという出会いによって頂点となる。こんな人と人
との心の綾織は、優しく体を包み着れば着るほど愛着の湧く一枚の着物のように大切
な宝物である。
竜ガ岳のシロヤシオ咲く風景は、私の見た風景であり、私の見なかった風景である。
《「傍ら」の物理的距離など問題ではない。僕たちにとっての「傍ら」はそんな次元
ではない。「心響ける人」の存在の多様性こそ、僕たちの山行きの、あるいは煎じ詰
めれば人生の彩りの豊かさではないか。》・・・御池杣人様、ただただ、嬉しきの
み。
山の友であり心の友・・葉里麻呂さん、御池杣人様に感謝を込めて・・・
都津茶女
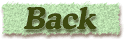
 散り花のその花群れに包まれて 寄り添う鹿のまどろみの夢
散り花のその花群れに包まれて 寄り添う鹿のまどろみの夢  羊雲 空から降りし笹の海 龍を抱(いだ)いた山堂々と
羊雲 空から降りし笹の海 龍を抱(いだ)いた山堂々と