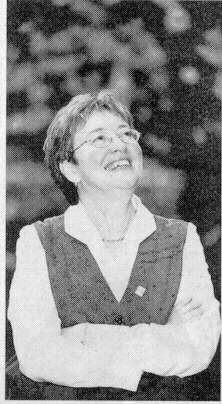(尚、講演会資料を希望される方、有料でコピー
配布しますのでご連絡ください。)
松葉は従来より大気中の汚染物質、重金属類などの測定分析の環境指標として活用されている。
本調査では、クロマツが大気中の存在するガス状、粒子状のダイオキシンを呼吸(炭酸同化作用)を通じ生物
組織内に長期にわたり蓄積することに着目している。摂南大学の宮田研究室が2週間に一度、松の針葉を採取
し分析した研究報告によると、大気中のダイオキシンはクロマツの新葉から急速に蓄積され、約4ヶ月以降で
濃度変化が少なくなり定常状態に達することが観察、確認されている。
さらに、一旦蓄積が安定すると、その後は大気中の平均濃度につれ松葉ダイオキシン濃度が上下することが
確認されている。したがって、4ヶ月以上経過し蓄積量が安定する6ヶ月以降の針葉を試料に用いれば、地域の
大気の平均濃度を推定することが可能となるものと考えられる。
<松葉調査の原理>
松葉調査の目的は、人々が生活する地域の平均的、長期的なダイオキシン類の汚染状況を性格に把握する
ことにより、廃棄物問題、ダイオキシンなどの有害化学物質問題の解決に向け人々の関心を喚起することにある。
そのために、日本のどの地域にも分布する常緑樹、クロマツの針葉を「環境指標」としてダイオキシン濃度を
測定分析することにより、地域の平均レベルの大気中ダイオキシン濃度を推定することを目的としている。
<松葉調査の目的>
TEL 0593-26-6414
Mail →
☆連絡先 YAMANBAの会☆
池田こみちさんの「松葉ではかろうダイオキシン」の
講演会に参加しました。
ダイオキシン汚染の現状では、焼却場/処分場から
の人体に影響を与える経路および大型化する焼却場
の課題/問題点を分かりやすくお話して頂きました。
松葉の調査では、社会的および技術的成果を踏
まえて全国的な松葉調査の必要性を説かれています。
四日市(桜、水沢、小山)でも、ガス化溶融炉が稼動
する前に、松葉によるダイオキシン調査をする必要性を
感じます。賛同される方は下記にご連絡ください。
<学習会>
*日時 平成14年4月14日(日) 14:00~16:00
*場所 レディヤン 春日井
*講師 環境総合研究所副所長 池田こみち氏
<2002年4月14日>
子供たちへの環境教育を熱心に進めているスウェーデンでは、幼稚園から「ゴミ分別」に
ついて学びます。日本と同じように、ここでも「循環」ということが大切なこととして、子供たち
に示されます。
循環とは「物が巡り回る」ことで、資源が何度も利用されることを意味しますから、大きな
意味では「リサイクル」と同じことです。ただし、スウェーデンでは「自然の力で分解されるも
の」と「人間がエネルギーを使ってリサイクルするもの」をはっきりと分けて考えています。
スウェーデンの幼稚園や小学校で「循環」を学ぶ実習のひとつとして、紙、野菜、アルミ、鉄
プラスチック、ガラスなど、さまざまな資源を土の中に埋め。数ヶ月後に掘出し、どのように
なるか比べる実験があります。結果、野菜は完全に分解し、紙はほとんどが分解します。
しかし、金属、プラスチック、ガラスは「自然の力で分解できないもの」として「出来るだけ利
用する量を増やさないほうがよい」「食品ゴミに混ぜていはいけない」ことなどを、子供たちに
学ばせます。
日本でよく使う「循環」と意味が違う。
去る3月30日に、京都の環境市民の主催する講演会
「スウェーデンの先進事例から学ぶ」に参加しました。
スウェーデンでは、学校とNGO、自治体、企業がビジョン
を共有し、連携した環境教育を進めています。「自然の循
環」の理解に力を入れ、持続可能な社会を築くための着
実な取り組みの紹介がありました。
<プログラム>
1.自治体・ローカルアジェンダ21が後押しする学校教育
2.社会に果たす企業の責任と教育の参加
3.自然循環を学ぶ授業
環境教育が道を拓く、
持続可能な社会
<2002年3月30日>
生命をはぐくむ水。淡水は地球の水の0.5%以下しかない。
有限かつ希少な水。にもかかわらず「工業化した農業や産業の
ために人は水を枯渇させ、奪い合い、汚染し、あらゆる生物
を死滅の危機に追いやっている。」と警告する。
10年程前に、北米自由貿易協定(NAFTA)構想が持ち上が
った時、多国籍企業など、より強い経済力を持つ者に地域資
源が奪われるとの危機感から、水の商品化に反対した。来年
京都で開かれる「世界水フォーラム」を前に来日し、全国5都市
を回った。
世界では10億人以上がきれいな水を使えない。汚い水のた
めに8秒に1人、子供が死ぬ。その一方で、ボトルに入った水の
市場は年20%の勢いで伸び、昨年は世界で840億リットルが本来
の循環から切り離して販売されたと指摘する。
「再生可能、持続可能な社会の一部として、自分と自然との
関係をとらえなおす。水はその重要な要素です。」世界の人が
水を共有財産と考え、私的な商品して売買されることから連携
して守ること、水源保全の国際的な法律の枠組みをつくること
の必要性を説く。
水資源の独占や貿易に反対するカナダ人 モード・バーロウさん
<2002年4月3日>