 海の星カトリック幼稚園運営規程
海の星カトリック幼稚園運営規程
1.施設の目的及び運営の方針
海の星カトリック幼稚園は、学校教育法第22条及び第23条に従って1号認定子どもを保育し、適切な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。
海の星カトリック幼稚園の教育理念・教育目標はカトリックの教え「愛すること」に基づき、思いやりの心、感謝する心、豊かな個性を持った明るく素直な子どもを育てる。
海の星カトリック幼稚園のモットーは
愛された子どもは、愛することができるおとなになる。
海の星カトリック幼稚園の教育理念の実践は
遊びと関わりの中で、思いやりの心、感謝する心、豊かな個性を育てる。
集団生活をとおして、自主自立の精神、基本的生活習慣の確立を助ける。
ひとりひとりと丁寧に接し、家庭との協力・連絡を密にする。
2.提供する特定教育・保育の内容
保育内容は、健康(体育、衛生、食育)、宗教(カトリック)、社会(関わり、地域)、自然、言語(日本語・英語)、音楽(歌唱、リズム)、絵画、制作などとする。
3.職員の職種、員数及び職務の内容
園長 1名 園務を処理し、所属職員を監督する。
教諭 必要名 学級担任は、園児の保育を行う。
年長組 担任1名、年中組 担任1名、年少組 担任1名・補助1名の 計4名。
その他必要に応じて、非常勤の補助職員。
主任は、全職員をまとめる。1名。
園医 1名 園児の健康診断に携わり、健康管理の助言を行う。
歯科医 1名 園児の歯科検診に携わり、歯科衛生管理の助言を行う。
薬剤師 1名 水質検査、照度検査などを行う。
事務職員 1名 園の経理、事務処理などを行う。
講師 必要名 英語教育や子育て支援事業、預かり保育などを担当する。
4.特定教育・保育の提供を行う日
土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、創立記念日、夏季休園日、冬季休園日、春季休園日を除く毎日。
ただし、これらの休日に行事を開催することよって、平日を代休とする場合がある。また、遠足などの翌日に休養のための休園日を設ける場合がある。年長児の宿泊保育の日は、年少児、年中児は保育の提供を行わない。その他、感染性の病気に多数の園児が罹患する恐れがあると園医が認めた場合は園長の判断で保育の提供を行わない場合がある。
5支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びその額
1)利用者負担(保育料)は、園児が居住する市町村が各々の保護者の納税額に応じて決定した額を幼稚園が受領する。
2)上乗せ徴収として、入園の際に施設整備費3年分を全保護者から受領する。その理由は従来入園金として受領していた園の運営に欠かせない費用で、施設の維持整備に必要であるためである。その額は36,000円とする。
また、年長児の保護者からは、卒園に関わる費用として、各月1,000円を受領する。その理由は卒園証書など卒園式で年長児が受け取る物と、卒園記念品として園に寄贈する物の代金に充てるためである。
その他、給食費は8月を除く11ヶ月間、毎月の平均額2,300円を受領する。
3)実費徴収として、遠足費用、制服や個人の楽器・保育用品代、防災用品代、プリメール管理料、卒園アルバム代、協力会会費などを当該の保護者から受領する。その理由は、これらの費用は、それぞれの全額が教育そのものの対価であるとは言い難く、また個人の利用頻度によって差があるためで、それぞれの実費を受領する。
4)幼稚園が一度受領した費用については、原則として返却しない。
第4条第2項に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員
平成28年度の利用定員は全体で60名とし、以下の区分ごとの数を目安とする。
年少3歳児 ゆり組 20名 (学則による定員は30名)
年中4歳児 ばら組 20名 (学則による定員は35名)
年長5歳児 すみれ組 20名 (学則による定員は35名)
7.特定教育・保育施設の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
1)利用の開始時間は 午前9時とする。特別な理由によってその時刻以前の利用が必要な場合は、子どもの安全を職員が見守ることができるよう、保護者は事前に届け出なければならない。
2)利用の終了時間は 年齢による体力などの違いを考慮し時差を設ける。また、水曜日は職員会議と行事準備のため半日保育とするため、以下の表のとおりとする。
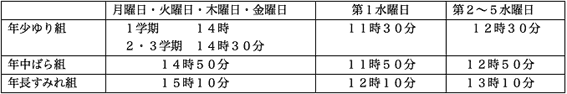
3)特定の行事がある場合は その終了時間に合わせて全員一斉に利用を終了する。
4)年少児は、慣れるまでの一定期間 終了時間を11時、11時30分にすることがあり、この期間は園長が決定する。
5)利用時刻以降 特別な理由によって園児の預かりが必要となる場合は、保護者が事前に届け出て子どもの安全を職員が見守る。なお、20分を超えて利用する場合、保護者は決められた延長保育料(500円)を支払わなければならない。
6)水曜日には預かり保育「コスモス」を実施し、保護者が事前の申し込みをすれば16時まで有料(700円)で利用することができる。なお、年少児は原則として2学期から利用できるものとする。また、園の行事などによって「コスモス」は実施できない日がある。
8.緊急時等における対応方法
1. 園長に即時報告
2. 同僚の職員に連絡
3. 必要に応じて直ちに最寄りの警察署、消防署に通報する。
園長は事態の正確な把握のもと、必要な判断を行い、教職員に対して指示を行う。
必要に応じて直ちに最寄りの警察署、消防書、医療機関、私学振興室、その他の機関に通報する。
また、保護者への説明を行い、園児の保護者への安全で円滑な受け渡しが行えるように指示する。
必要に応じて危機管理対策本部を設置し、必要な決定措置を迅速、正確に実施する。
9.非常災害対策
飲料水、非常食、防寒用ブランケット、タオルなどを備蓄し避難時持ち出しに備える。
災害の対策として、防災訓練を年2回(夏・冬)に行う。年1回は浜田小学校の屋上への避難訓練をする。
防災委員会(各クラス1名の保護者で構成)を開き、年1回防災講座を行って保護者に対して啓発活動または防災訓練を行う。
大規模な災害に備えて、園児の保護者同士で協力するため、「災害対策居住地域確認」を年1回行い、居住地域ごとに保護者・園児で集まって紹介・情報交換をする。
B.災害発生時
1)地震発生時は、次のように行動する。
〔一斉保育中または保育室内にいるときの地震〕
警報装置が作動した場合、速やかに机の下にもぐるよう園児に指示する。
余震が予測されるほどの大地震の場合は揺れがおさまるのを待って、防災頭巾を園児に配り、正門の内側、聖マリア像の前のスペースに避難・誘導して点呼する。けが人のいる場合は、手当てを行い、2次避難に備えて安全経路の確認を行ってから移動する。
〔自由遊びの時間または屋外にいるときの地震〕
警報装置の放送を聞いたものが直ちに放送などで全員に知らせ、その場で一旦しゃがむ姿勢を取らせる。揺れが収まったら、余震に備えてできるだけ園庭の中心部に集合させ、点呼して全園児の安全を確認する。
けが人のいる場合は、手当てを行い、2次避難のため安全経路の確認を行ってから移動する。
避難場所を保護者の迎えに備えて掲示しておく。
2)津波警報発令時や長期避難の必要な場合は、次のように行動する。
指定広域避難場所である浜田小学校までの安全経路を確認して、園児を2列に並ばせ、園長の指示で移動する。体育館前の東門から入り、東通用口から階段を使って4階または屋上まで、現場の指示誘導に従って避難する。津波到達まで時間に余裕があると報じられている場合は、飲料水を各自に持たせる。
3)大雨・洪水・暴風などの警報・「南海トラフ大地震注意情報」が発令された場合は次のように行動する。
〔始業前に発令された場合〕
午前7時前にいずれかの警報が四日市市に発令された場合は臨時休園の措置を取り、保護者に携帯メール連絡で知らせる。
〔保育時間中に発令された場合〕
すみやかに降園の準備をし保護者に携帯メール連絡で園児の迎えを依頼する。その際渋滞・事故をさけるため、車コースの園児の受け渡し場所をクラスごとに指定する。ヤマダ電機、グランドティアラ千寿などの協力を得る。大地震の注意情報が発令され、園での待機が危険であると園長が判断した場合は、指定広域避難場所である浜田小学校に避難して保護者にその旨連絡し、安全が確保されてから引き渡しの措置を取る。
10.虐待の防止のための措置に関する事項
職員は毎日の送り迎えの時に保護者とできるだけ会話を交わし、保護者の困りごとがないかに留意する。相談にはすぐに応じ、無理な時は相談日時の設定を提案する。
月ごとの身体測定の際、春の内科検診の際、プール遊びの時などに、園児の身体に傷などがないかを担任は確認する。
異常が見られる場合は、すぐに園長に報告し、園長は保護者との面談を行って事実の確認をして問題点・解決策を話し合うなどの措置を取る。
虐待が繰り返される事実が確認された場合は児童相談所に報告し、指示を受ける。
11.その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項
1)海の星カトリック幼稚園はその教育理念を実践するためにカトリックの宗教教育を行う。
2)園児の保護者は、本園の建学の精神、教育理念の実践のために行われる行事や教育活動に賛同し、できる限り協力しなければならない。
3)保護者は、園児の入園に際して、教育活動に必要な園児の情報を調査書などに記入、提出して、必要な面談に応じ、できる限り協力しなければならない
4)保育料を保護者から受領できない場合、また請求しても3か月以上保護者から利用料が受領できず、連絡が取れない場合は園児を退園させることがある。
5)保護者が園の規定やきまりを大きく逸脱する行動を繰り返し、他の園児や保護者に多大な悪影響を与えると園長が判断した場合は、退園させることがある。
6)保護者は園児の施設利用を中止する場合は、退園届を提出しなければならない。届が提出されないまま次の月に入った場合はその月の利用料を園は受領する。
7)保護者は転居や転職、労働形態の変更などの必要事項を速やかに園に届けなければならない。
8)本園は、宗教教育のためやその他の行事や活動のために、カトリック四日市教会の施設、敷地を借用することがある。
9)本園は、エスコラピオス修道会の司祭や教会関係者による支援を受けることができる。
10)保護者・園児のカトリック教会の儀式や行事への参加はいずれも自由にできるが、参加を強要されることはない。
12.個人情報及び特定個人情報の保護
附則
この運営規程は子ども子育て支援新制度への移行に伴い、平成27年4月1日から実施する。
この運営規程は5条4)項および12条を加えて、平成28年1月1日より実施する。
この運営規程は3条および5条2)項および9条B 3)項を変更して、平成30年 4月1日より実施する。

 今日、幼稚園では…
今日、幼稚園では…