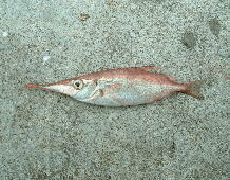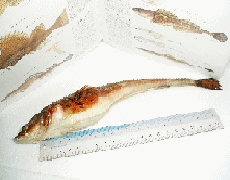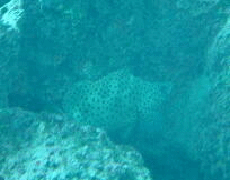現在17種類
|
和名 | サカタザメ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | エイ目 サカタザメ科 | ||
| 別名・地方名 | イタボトケ、イワイザメ、キャアメンチョ、コチケエメン、コト、サカフカ、スキ、スキクワザメ、テンガイ、トウバザメ | ||
| 分布 | 南日本、朝鮮半島、台湾、中国、ベトナム沿岸、アラビア海に分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸からやや沖合の水深200m位の以浅に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 千葉,神奈川、静岡・愛知・和歌山、高知、愛媛ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 豊浜漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身、煮付け、ヒレはムニエル、湯引き、練り物 | ||
| 体長は約70〜100cmぐらいになる。見た目がギターのように見えることから『ギターフィッシュ』と も呼ばれている。鮮度落ちが早いので刺身よりも湯引きにして酢味噌で食べる方がおすすめです。 |
|||
|
和名 | サギフエ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | トゲウオ目 サギフエ科 | ||
| 別名・地方名 | ダイコクサギフエ・ウグイス・チュウチュウ ツノハゲ |
||
| 分布 | 本州中部以南(琉球列島を除く)からインド、 西太平洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深は15〜150メートルに生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・愛知・三重・和歌山ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 紀伊長島漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | あまり食べたりはしない。 | ||
| 普段は斜めに倒立しているが、長距離を移動する時は水平に泳ぐ。 | |||
|
和名 | サクラダイ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ハタ科 | ||
| 別名・地方名 | カラサン・ウミキンギョ、オオキダイ、オキイトヨリ、オタマウヲ、オタマコロシ、オドリコダイ、オヒロベラ、コンペント | ||
| 分布 | 琉球列島を除く関東から南日本、台湾に分布する。 | ||
| 生息域 | 岩礁域、海底からやや離れた場所に群れで生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 千葉・神奈川・和歌山ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋港水族館 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身、煮付け | ||
| 雄の体色は赤色で白色斑が体側にある。背鰭第3棘はやや長く伸びる。 雌は橙色で、背鰭棘に黒色斑がある。雌雄ともに背鰭軟条のうち1本が長く伸長している。 尾鰭はよく湾入している。体長15cmmぐらいに成長する。 |
|||
|
和名 | サケ・・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | サケ目 サケ科 | ||
| 別名・地方名 | トキシラズ・アキアジ・アキサケ・シロサケ・シャケ | ||
| 分布 | 島根、利根川以北から北海道、日本海、ロシア、北アメリカ西部に分布。 | ||
| 生息域 | 川で生まれ海へ下り回遊し産卵期に生まれた川に戻って来る。生まれた川の匂いを覚えているようです。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道・青森・岩手・新潟ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 北海道羅臼漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 塩焼き・ムニエル・フライ・鍋物・バター焼き ちゃんちゃん焼き(北海道郷土料理)・ホイル焼き |
||
| 鮭と言ったら北海道りイメージが強い。鮭の卵を筋子、いくらと呼び美味い。 春に水揚げされるサケを『トキシラズ』と呼ばれ脂も乗り美味しい。 秋に水揚げされるサケを『アキサケ』と呼び卵を加工して、いくら・スジコとして食卓に並ぶ。 秋に獲れるサケの中に数万尾に1本の幻のサケ『ケイジ(鮭児)』が獲れる。 11月11日はサケの日です。鮭の漢字が魚へんに十一十一と書くからなんだって!
|
|||
|
和名 | サケビクニン・・・・・・・・・ | |
| 種別 | カサゴ目 クサウオ科 | ||
| 別名・地方名 | −−− | ||
| 分布 | 本州北部、日本海北部から北海道、オホーツク海、タータル海峡に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深100〜600メートルの深海に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 新潟・青森・北海道ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沼津港水族館 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 煮付け | ||
| 食用としては出回らない魚で、煮付けで食べられるが水っぽい魚で好んで食べる魚ではない。 クセのない魚なので食べやすいようですが・・・ |
|||
|
和名 | サザナミダイ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 フエフキダイ科 | ||
| 別名・地方名 | アマクチン | ||
| 分布 | 鹿児島県以南、西太平洋、インド洋、紅海に分布する | ||
| 生息域 | 水深50〜100メートルの沖合いの岩礁域にすみ、底生無脊稚動物や小魚を食べている。 | ||
| 日本の主な産地 | 鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄牧志公設市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・煮付け・焼き物・唐揚げ・ムニエル | ||
| シロダイに似るが、頬に多くの青色波状線があることで区別が出来る。 50〜80センチグラ手に成長し、シロダイ同様高級魚として取り扱われて味は良い。 |
|||
|
和名 | サッパ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | ニシン目 ニシン科 | ||
| 別名・地方名 | カツ・キイワシ・キンカワ・サベラ・チナシ ハダラ・ハベ・ハンダ・ヒラ・ママカリ・ワジ |
||
| 分布 | 北海道以南からフィリピンにかけて分布する。 | ||
| 生息域 | 内湾の浅い砂泥底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 千葉・神奈川・静岡・愛知・三重・和歌山・大阪 兵庫・岡山・広島・徳島・香川・愛媛・山口ほか |
||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 酢漬け・唐揚げ | ||
| コノシロに似るが、エラブタ後ろに黒い斑点がない。 酢漬けは瀬戸内海の名物で、あまりの美味しさに飯が足りなくなり、隣の家まで飯を借りに行くので「ママ カリ」と呼ぶようになった。 4〜9月に内湾で産卵する。 |
|||
|
和名 | サツマカサゴ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | カサゴ目 フサカサゴ科 | ||
| 別名・地方名 | −−− | ||
| 分布 | 南日本からインド洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 浅海の岩礁域に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 三重・和歌山・高知・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 各きょく条に猛毒がある。 | ||
| 食べ方 | 煮付け・唐揚げ・椀物 | ||
| この魚は取扱に注意して下さい。鰭先には毒があります。 市場にはあまり出回らない。 |
|||
|
和名 | サブロウ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | カサゴ目 トクビレ科 | ||
| 別名・地方名 | オクジ・ガンガラビ・センダイオクジ・トトキ | ||
| 分布 | 銚子以北の太平洋側に分布する。 | ||
| 生息域 | やや深海の砂泥底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 千葉・宮城・岩手・北海道ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 岩手県 山田漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・塩焼き | ||
| サブロウがいるからシロウもいるのかな?・・・実はいます。 よく似ていて、北日本の太平洋側に生息するのが『サブロウ』で富山以北の日本海側に生息するのが『シロ ウ』です。よく似ていて見分けが付け難いのですが、産地で判断できます。 近種にトクビレ(ハッカク)がいます。 |
|||
|
和名 | サメガレイ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | カレイ目 カレイ科 | ||
| 別名・地方名 | タカノハカレイ・トンビホチ・ホンダ・ホンダカレイ メガレイ |
||
| 分布 | 日本各地、朝鮮半島、東シナ海、カナダ太平洋側に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深150〜1,000m砂泥底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 岩手・青森・北海道ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・煮付け・塩焼き・お寿司・干物 | ||
| 見た目はよくないが、味は脂が乗っていて美味しい。市場に出回る量は少ない為なかなかお目にかからない が、食べる機会があったら是非食して頂きたい。綺麗な白身でエンガワは美味い! 体高は高く卵円形です。産卵期は10〜2月です。 |
|||
|
和名 | サヨリ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | ダツ目 サヨリ科 | ||
| 別名・地方名 | ハリウオ・カンヌキ・サイレンボウ・ショウブ スクビ・スズサヨリ・ハーイヨ・ヤマキリ・ヨド |
||
| 分布 | 樺太から日本各地、朝鮮半島、台湾に分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸域に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 日本各地 | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・塩焼き・お寿司・天ぷら | ||
| 白身で美味しい魚です。刺身や寿司ネタとしても人気が高い。 産卵期のサヨリは脂もあり美味い。サハリンから日本、台湾にかけて分布する。 サヨリは意外といろんな種が存在する。 旬は春です。 |
|||
|
和名 | ザラガレイ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | カレイ目 ダルマガレイ科 | ||
| 別名・地方名 | ミズガレ | ||
| 分布 | 南日本から太平洋、インド洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深200〜600mの海底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 愛知・和歌山・高知・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 豊浜漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 食用価値がなくあまり食べない。 | ||
| 下がくが上がくより長いのが特長です。 市場に出回ることは殆どなく珍しい魚です。 |
|||
|
和名 | サラサハギ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | フグ目 カワハギ科 | ||
| 別名・地方名 | ギュウギハゲ・ギュウギュウハゲ | ||
| 分布 | 関東以南から東シナ海に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深は200mまでの沿岸に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・愛知・和歌山・高知ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 豊浜漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 煮付け・唐揚げ・鍋物 | ||
| ウマズラハギに似るが、斑紋があることで区別できる。 通常市場で扱われることはないため市場に入荷する事は非常に珍しい。 |
|||
|
和名 | サラサハゼ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ハゼ科 | ||
| 別名・地方名 | −−− | ||
| 分布 | 和歌山県から高知、琉球列島、台湾、南シナから北西オーストラリアにかけての太平洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 珊瑚礁域の砂底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋港水族館 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | あまり食べない。 | ||
| 体長は10cmぐらいに成長する。 第1背鰭中央部の棘は長く三角形で、第1背鰭に明瞭な黒色斑がある。 尾鰭に前部上側に1黒色斑、後部に数個の青みがかった暗色斑が見られる。頬に青色斜走線がある。 |
|||
|
和名 | サラサハタ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ハタ科 | ||
| 別名・地方名 | クチグワーミーバイ | ||
| 分布 | 紀伊半島以南からインド、西太平洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸浅所の岩礁域、珊瑚礁に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄美ら海水族館 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | おいしくないのであまり食べない。 | ||
| 体型は頭部が急に盛り下がる。体や鰭に円形の黒斑がある。 やや深い岩礁や珊瑚礁にすむ。味はよくないが、観賞用としては人気がある。 |
|||
|
和名 | サワラ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 サバ科 | ||
| 別名・地方名 | カマチ・グッテリ・サーラ・サゴシ・トオサワラ ヤナギ・サゴチ |
||
| 分布 | 北海道南部以南から九州、温帯、亜熱帯域に分布する | ||
| 生息域 | 沿岸、沖合い表層を群れで生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 新潟・石川・福井・島根・福岡・長崎・静岡・愛知 三重・和歌山・高知・愛媛・鹿児島ほか |
||
| 撮影場所・仕入先 | 福岡魚市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・塩焼き・昆布〆・照り焼き・ムニエル 鍋物・フライ・タタキ |
||
| 魚偏に春と書いて鰆と書きます。旬は春ですが、秋から冬は脂が乗って美味い。 身は柔らかい。食べ方はいろんな料理が出来る為人気が高い。 尻尾に近い方のが美味しい。 栄養価も高く食べやすい事で人気もある。 |
|||
|
和名 | サンマ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | ダツ目 サンマ科 | ||
| 別名・地方名 | カド・サイラ・サイリ・サイリイ・サエラ・サザ サヨラ・セイラ・マルカド・バンジョウ |
||
| 分布 | 日本からアメリカ沿岸にいたる北太平洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸、沖合いの表層に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道・青森・岩手・宮城・千葉・和歌山ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・たたき・酢の物・塩焼き・蒲焼・寿司 | ||
| 秋の代表魚サンマは秋刀魚と漢字で書く。北海道から三陸、房総半島、紀州へと下り、日本海側へも北陸、 山陰へと下る。美味しいサンマの見分け方は、まず鮮度です。目は真っ黒か、魚に張りがあるか、エラは赤 いか、脂のあるサンマの見分け方は、皮肌が黄色っぽいか、尾鰭付近が黄色いと沢山脂が乗っている。 |
|||
 シの魚 イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 その他 魚の寄生虫
シの魚 イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 その他 魚の寄生虫