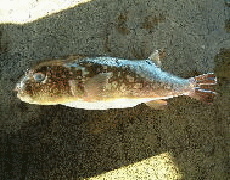現在27種類
|
和名 | コイ・・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | コイ目 コイ科 | ||
| 別名・地方名 | アカクチ・クイユ・コー・サクコイ・ナメ・ハヤリ ヒゴイ・ホウリュウモノ・マゴイ・ヤマト |
||
| 分布 | 野生種は、琵琶湖、関東平野、淀川水系、四万十川、岡山平野、ヨーロッパ、アジア大陸に分布する 移植により日本各地に生息する。 |
||
| 生息域 | 湖沼や河川に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 茨城・滋賀・高知・徳島・岡山ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 胆嚢で食中毒の報告がある。 | ||
| 食べ方 | アライ・コイコク・甘露煮 | ||
| 口にヒゲがあるのが特徴です。大きさは30〜60cmだが日本記録は115cmだとか・・・ 寿命は20年だが70年生きたという記録もある。 |
|||
|
和名 | コイチ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ニベ科 | ||
| 別名・地方名 | クチ・グチ | ||
| 分布 | 高知県以南から東シナ海、朝鮮半島に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深40〜150mの砂泥底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 高知・宮崎・鹿児島・熊本・長崎ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場・片名漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 煮付け・塩焼き・あんかけ・唐揚げ・刺身 | ||
| シログチ(イシモチ)、ニベに似る。 鮮度が良ければ刺身が美味く、塩焼きもおすすめします。 |
|||
|
和名 | コウライアカシタビラメ・・・・ | |
| 種別 | カレイ目 ウシノシタ科 | ||
| 別名・地方名 | シタビラメ | ||
| 分布 | 静岡県以南から南シナ海に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深25〜85m位に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・愛知・兵庫・高知・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | ムニエル・唐揚げ・煮付け | ||
| 裏側に黒っぽい模様があるのが特徴です。 体長は30cmぐらいになる。 |
|||
|
和名 | コウライトラギス・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 トラギス科 | ||
| 別名・地方名 | ハシアガリ | ||
| 分布 | 南日本、朝鮮半島、黄海に分布する。 | ||
| 生息域 | 砂礫底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 三重・和歌山・高知・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 引本港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | あまり食べない。 | ||
| 体側上部に暗色の鞍状斑がある。雄は胸鰭基部に大きな黒色斑があり、雌では黄色っぽい。 甲殻類や多毛類などの底生動物を食べている。体長は10〜12cm程度です。 雌から雄に性転換する魚です。産卵は夏です。 市場価値がないので、市場に出回ることは殆どない。 |
|||
|
和名 | コウライマナガツオ・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 マナガツオ科 | ||
| 別名・地方名 | マナガツオ | ||
| 分布 | 北海道から東シナ海、黄海に分布する。 | ||
| 生息域 | 大陸棚の砂泥底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 福岡・長崎・高知・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・煮付け・クリーム煮 | ||
| マナガツオと同種でマナガツオとして販売されている。 味も殆ど変わらない。白身で味は良い。 |
|||
 ←エラが白い? ←エラが白い? |
和名 | コオリカマス・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 コオリウオ科 | ||
| 別名・地方名 | アイスフィッシュ | ||
| 分布 | 南極半島、スコシア海域、ブーベ島、ケルゲレン諸島に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深100〜700mの海底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 日本には生息しない。冷凍輸入 | ||
| 撮影場所・仕入先 | 四日市市内 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・天婦羅・ムニエル・フライ | ||
| この魚の血液には酸素の運搬をするヘモグロビンがありません。そのため,血液が赤くなく、エラも白いの が特徴です。 アイスフィッシュとして冷凍で流通しています。南極海スコシア海域、南極海インド洋区の島付近に分布 する。ちなみに酸素は直接血漿に溶けこませるそうです。零下の水温でも血が凝結しないため生きられる。 体長は45cmぐらいになります。味は、刺身で食べると独特の味でやや水っぽい。 |
|||
|
和名 | コガネシマアジ・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 アジ科 | ||
| 別名・地方名 | アヤガーラ | ||
| 分布 | 南日本から琉球列島、インド洋、太平洋の熱帯、亜熱帯に分布する。 | ||
| 生息域 | 珊瑚礁に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄牧志公設市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・煮付け・塩焼き | ||
| 体長は1メートルを超えるものもいる。体高は高く側扁する。 若魚は金色で10本ほどの黄色い横帯を持つ若魚の内は大型魚に付随して生活することが多い。 |
|||
|
和名 | コクチフサカサゴ・・・・・・・ | |
| 種別 | カサゴ目 フサカサゴ科 | ||
| 別名・地方名 | アカオコゼ・アラカブ・ガガニ・ガシラ・ハツメ | ||
| 分布 | 本州中部以南から朝鮮半島に分布する。 | ||
| 生息域 | 浅海底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 和歌山・高知・鹿児島・長崎ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 唐揚げ・煮付け | ||
| 口がカサゴの中でも小さく体長も15cm前後。 市場には殆ど入荷することはない。 |
|||
|
和名 | コクハンアラ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ハタ科 | ||
| 別名・地方名 | −−− | ||
| 分布 | 八丈島、高知県から琉球列島、インド〜太平洋域に分布する。 | ||
| 生息域 | 遊泳性で、サンゴ礁域の外縁、岩礁域に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄泊漁港(泊いゆまち) | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒ですが、シガテラ毒を持つ場合がある為、注意が必要です。 | ||
| 食べ方 | 煮付け・焼き物・刺身 | ||
| 本州ではあまり見かけない魚で沖縄の魚屋さんでたまに見られる。 味はよく刺身がおいしい。体長は1m位になり、大きくなると体色が変わる。 シガテラ毒を持つ魚も報告されている為、注意が必要です。 |
|||
|
和名 | コシナガ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 サバ科 | ||
| 別名・地方名 | シロシビ・セイヨウシビ・トンガリ・ハシビ ビンツケ・メジモドキ・ヨコワモドキ・コシビ |
||
| 分布 | 南日本からオーストラリアにいたる西部太 平洋、東インド諸島、インド洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 表層を回遊するが、沿岸性が強く、大陸棚を離れずに一生を過ごすようです。 | ||
| 日本の主な産地 | 福岡・長崎・鹿児島・宮崎ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 煮付け・照り焼き・ソテー・カレー・加工品 | ||
| マグロの中では小型魚で、特殊な皮下血管が発達していて、周囲の温度より体温が高い。 強力な遊泳力を持つ |
|||
|
和名 | コショウダイ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 イサキ科 | ||
| 別名・地方名 | イロダイ・オゴンダイ・カクレダイ・コタイ コロエアイ・コロダイ・コンモリダイ・セコダイ チンダイ・マナラ・ブタノクチ |
||
| 分布 | 本州中部以南から南シナ海に分布する。 | ||
| 生息域 | 岩礁域に多く、大陸棚にも生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 愛知・三重・和歌山・徳島・高知・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 豊浜漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・塩焼き・唐揚げ | ||
| タイと名が付くが、以外にもイサキの仲間です。 夏が産卵期で、旬を迎え最も美味しい。味は良く美味しい魚ですが、入荷漁は少ないのが現状です。 |
|||
|
和名 | コスジイシモチ・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 テンジクダイ科 | ||
| 別名・地方名 | イシブンコウ・イシボンケイ・サンジオヨゴメ・シマアカジャコ・シマイセジ・シマシカロ・ブンコウ | ||
| 分布 | 東京湾から琉球列島、慶良間諸島、台湾、西太平洋に分布する。 | ||
| 生息域 | やや深い岩礁域に生息するが、浅い波止の生息も確認されています。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・三重・和歌山・高知、鹿児島、沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 紀伊長島漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 練り製品、唐揚げ | ||
| 体長は10cm位の小型魚です。 魚体の割に目と口が大きく、金赤色の7条の縦帯が特徴で尾の近くに黒点がある。 定置網や釣りなどで漁獲されるが市場価値は低く市場にはあまり出回らない。(食用にはなります) |
|||
|
和名 | ゴテンアナゴ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | ウナギ目 アナゴ科 | ||
| 別名・地方名 | ギン・ギンアナゴ・クロウナギ・ハカリメ・メバチ・ダルマ | ||
| 分布 | 日本各地からインド洋、ハワイに分布する。 | ||
| 生息域 | 泥沼底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 千葉。神奈川・静岡・愛知・和歌山・高知ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 片名漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 天ぷら・蒲焼・唐揚げ・煮付け・練り物 | ||
| 体長は60cm位になる。 マアナゴに混ざってくるが、味はマアナゴより劣る。 |
|||
|
和名 | コトヒキ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 シマイサキ科 | ||
| 別名・地方名 | ヤガタイサキ・クブ・クフワガナー・シマイサキ シャミセン・ジンナラ・スミシロ・スミヤキ タルコ・チョウダイ・フエフキ |
||
| 分布 | 本州中部以南からインド洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 浅海や河口域に生息し、幼魚は汽水域にも入る。 | ||
| 日本の主な産地 | 愛知・和歌山・高知・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 煮付け・唐揚げ | ||
| 体長は25cm位になる。あまり市場には出回らない。 黒い筋の模様は幼魚の時はくっきりしていて、大きくなると薄くなる。腹側は銀白色しています。 |
|||
|
和名 | コノシロ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | ニシン目 コノシロ科 | ||
| 別名・地方名 | アシチン・コハダ・ジャコ・シンコ・ゼニコ ツナシ・ツナセ・ナカズ・ベット・マベラ・ヨナ |
||
| 分布 | 本州中部以南からインド洋にかけて分布する。 | ||
| 生息域 | 内湾に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・愛知・三重・徳島・高知・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 淡路仮屋漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 酢漬け・唐揚げ | ||
| エラブタ後ろに黒い斑点がある。寿司ダネの光りものとして代表的な魚で人気がある。 やや小骨が気になる為、酢漬けでの調理法がおすすめです。 |
|||
|
和名 | コバンザメ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 コバンザメ科 | ||
| 別名・地方名 | コバンイタダキ・コバンウオ・コバンカジキ・ヤスナ ツチウオ・スナチドリ・フナイトル・フナスリ |
||
| 分布 | 太平洋東部、太平洋西部を除く全世界の暖か海、地中海に分布する。 | ||
| 生息域 | 大型魚やウミガメなどと吸着生活をする。 | ||
| 日本の主な産地 | 和歌山・高知・鹿児島・沖縄など | ||
| 撮影場所・仕入先 | 南知多ビーチランド | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 食べられなくはないが、食用としての利用価値はない | ||
| 大きな魚やウミガメなどに吸着して生活し、おこぼれの餌を食べている。 産卵期は5〜8月です。 |
|||
|
和名 | コバンヒメジ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ヒメジ科 | ||
| 別名・地方名 | ジンバー | ||
| 分布 | 南日本から沖縄、台湾、インド洋にかけて分布する。 | ||
| 生息域 | 浅い珊瑚礁に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄牧志公設市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 唐揚げ・煮付け・焼き物 | ||
| 本州ではあまり見かけないが、沖縄では一般的に見かけられる。 背びれ下の黄色っぽい模様と尾鰭近くの黒い斑点が特徴です。 |
|||
|
和名 | コブダイ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 べラ科 | ||
| 別名・地方名 | カンダイ・イザ・イソアマダイ・カンノダイ・テス デスコベ・アマ・ノマ・モブシ・ナベクサラシ |
||
| 分布 | 茨城以南・新潟以南から東シナ海に分布する。 | ||
| 生息域 | 黒潮の影響の少ない瀬戸内海や日本海に多く、沿岸の岩礁域に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・三重・広島・山口・石川・島根・長崎ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 福岡魚市場・名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・アライ・味噌漬け・唐揚げ | ||
| 写真上が成魚で、下が幼魚でコブがない。成長すると前頭部にこぶ状に突き出すことからコブダイと名付け られたようです。刺身で食べると歯ごたえがあり、身事態は特長のある味はない為、濃いめのタレや醤油で 食べる事をお奨めします。 |
|||
|
和名 | コボラ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | ボラ目 ボラ科 | ||
| 別名・地方名 | チクラ | ||
| 分布 | 日本海や東北地方、瀬戸内海にも稀確認されていますが太平洋側の千葉県以南から琉球列島からインド、太平洋、紅海に分布し琉球列島に多く分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸域の浅所および、汽水域から淡水域まで生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄サンマリーナビーチ | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身(洗い)・唐揚げ・フライ・塩焼き・煮付け | ||
| 胸鰭の基部に黄金色の横帯あり、頭部の断面は円筒形に近いことなどが特徴です。 縦列鱗数は30〜34枚で、体長は30cm位までで、ボラに比べると小型種です。 デトリタス(生物遺体や破片や微生物の死骸)、藻類、甲殻類や多毛類などを食べる。 |
|||
|
和名 | ゴマアイゴ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 アイゴ科 | ||
| 別名・地方名 | カーエー | ||
| 分布 | 琉球列島、西・中部太平洋、インド洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 河川汽水域や内湾に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄牧志公設市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 各鰭きょく条起部に毒があります。 | ||
| 食べ方 | 刺身・アライ・煮付け | ||
| アイゴは南の地方へ行くほど種類が増える。アイゴより形が丸く知識がないとうっかり触っ てしまい背鰭 の毒で大変なことになる。背鰭に毒を持つためよく注意して調理をしてほしい。 |
|||
|
和名 | コマイ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | タラ目 タラ科 | ||
| 別名・地方名 | オオマイ・カンカイ | ||
| 分布 | 日本海北部、北海道東部・北部に多く分布する。 | ||
| 生息域 | 水深150m以浅の底層に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 北海道花咲漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | ルイベ・干物・焼き物・煮付け・鍋物 | ||
| タラに似た魚で北方海域に多く生息する。産卵期は1〜3月の流氷がやってくる頃です。 流氷がくる頃最も浅い海域に来て、氷の下で産卵する。 |
|||
|
和名 | ゴマサバ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 サバ科 | ||
| 別名・地方名 | マルサバ・ウキサバ・グルクマア・ホシサバ・サバ ドンサバ・ナンキンサバ・ホシグロ・コモンサバ |
||
| 分布 | 日本近海から南西太平洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸表層を群れで回遊して生活する。 | ||
| 日本の主な産地 | 岩手・千葉・静岡・愛知・三重・和歌山・高知 福岡・長崎・島根・石川・新潟ほか |
||
| 撮影場所・仕入先 | 島勝漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 酢締め・塩焼き・竜田揚げ・煮付け | ||
| 別名マルサバとも呼び、マサバをヒラサバと呼んでいる。真鯖に似るが、腹側に黒い斑点でゴマ鯖と真鯖が 判別できる。真鯖に比べ身質が柔らかく味は劣る。しかし旬が異なるため、真鯖の旬がずれた時はゴマ鯖も お奨めできる(旬は夏)。体温は周囲の温度より高く、遊泳力は強い。 |
|||
|
和名 | ゴマフグ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | フグ目 フグ科 | ||
| 別名・地方名 | サフグ・サワフグ・フグト | ||
| 分布 | 北海道南部から本州各地、東シナ海に分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸海域に生息する。。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道・岩手・福島・千葉・静岡・愛知・三重・和歌山・高知・長崎・島根・福井ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | ふぐ毒のテトロドトキシンを持つ。精巣と筋肉は食べられるが、卵巣と肝臓は強毒、皮膚も毒を持つので素人での調理は避けて下さい。 | ||
| 食べ方 | 刺身・唐揚げ・鍋物 | ||
| 小黒点が密集する模様で、ゴマのように見えるからゴマフグと言われている。 このフグは皮にも毒があることで、調理する際素人がしないように! 市場には稀に入荷はするが、比較的本州では見かける種のフグです。 |
|||
|
和名 | コモンサカタザメ・・・・・・・ | |
| 種別 | エイ目 サカタザメ科 | ||
| 別名・地方名 | カアメ・カイメ・キャアメ・ケイメ | ||
| 分布 | 南日本から東シナ海、南シナ海に分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸の砂底に生息する。有明海に多い。 | ||
| 日本の主な産地 | 佐賀・長崎ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 福岡魚市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 湯引きで食べる・練り物・煮付け | ||
| サメと名が付くがエイの仲間である。 | |||
|
和名 | コモンフグ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | フグ目 フグ科 | ||
| 別名・地方名 | カンバ・ギシフグ・ギンフグ・コメフグ・ナツフグ ダイコンフグ・ヒガンフグ・フグト・フグトン ホシフグト・メアカフグ |
||
| 分布 | 北海道以南から朝鮮半島に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深100m以浅に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・愛知・三重・和歌山・高知・鹿児島・長崎 | ||
| 撮影場所・仕入先 | 紀伊長島漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い | ||
| 毒の有無 | 筋肉部に弱毒です。精巣、皮膚、腸は強毒です。 肝臓、卵巣は猛毒です。毒性が強い。 |
||
| 食べ方 | 一般に食べない。 | ||
| 筋肉部に弱毒、皮膚、精巣、内臓に毒がある。個人での調理はしないように・・・ 体長は25cmぐらいです。 |
|||
|
和名 | コロダイ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 イサキ科 | ||
| 別名・地方名 | イソコロ・エゴダイ・カイグレ・コロ・シブタ シャクアジ・ジューグワーグレー・マチマワリ |
||
| 分布 | 伊豆諸島から南シナ海、インド洋にかけて分布する | ||
| 生息域 | 岩礁域に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・愛知・三重・和歌山・高知・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | (写真上)引本港・(写真真ん中と下)紀伊長島漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・塩焼き・煮付け・唐揚げ | ||
| 写真の上が幼魚、写真の真ん中が若魚、写真の下が成魚です。 成長に伴い模様が変わります。 あまり市場に入荷することはないが、気を付けて見ているとお目にかかることがある。 コショウダイに似るが、頭部がやや小さい。背鰭がコショウダイが12本に対し、コロダイは9〜10本な ので区別が付く。稚魚の模様と若魚の模様は異なり、成魚になると斑点が細かくなる。 刺身や塩焼きが美味で食べる価値ありです。味は良いのでお奨め出来ます。食べる機会があれば是非食べて みて下さい。 |
|||
|
和名 | ゴンズイ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | ナマズ目 ゴンズイ科 | ||
| 別名・地方名 | ウグ・ウルベ・エドミズ・ギギ・ギギュウ・クグ クモ・グング・ゴンジイ・ズルベ・ユルベ・ユルメ |
||
| 分布 | 本州中部以南から朝鮮半島、インド洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸の岩礁域に生息する。幼魚は群れで泳ぎ、これをゴンズイダマと言う。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・愛知・三重・和歌山・長崎・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 尾鷲漁港(写真の上と真ん中) | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 背鰭、腹鰭に毒を持ちゴンズイが死んでも毒の効力はあります。 | ||
| 食べ方 | 唐揚げ・味噌汁・蒲焼(毒部の鰭は取る事) | ||
| 口ひげ(4対)を持ちナマズの仲間です。 背鰭、腹鰭に毒を持ち死んでも毒の効力はあります。(写真の真ん中の赤丸内にある白っぽい棘が毒針) 死んだ後鰭が立ったままの状態になりやすく棘に刺してしまうことがあります。 群れで泳ぐ為、ゴンズイ球と呼ばれよく泳いでいるが時にゴンズイに遭遇し刺されて死亡する例もある。 1尾だけに刺されるなら死にいたる事はないが、群れで刺されたら命にかかわることになる。この魚はあま り食べることはないが、唐揚げ、味噌汁にて食べることができる。 |
|||
 サの魚 イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 その他 魚の寄生虫
サの魚 イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 その他 魚の寄生虫