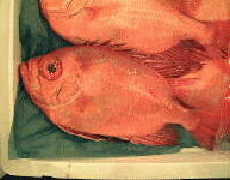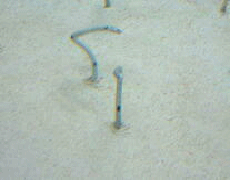現在09種類
|
和名 | チカ・・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | キュウリウオ目 キュウリウオ科 | ||
| 別名・地方名 | ツカ・ワカサギ | ||
| 分布 | 北海道沿岸から陸奥湾、三陸沿岸に分布する。 サハリン・カムチャッカにも分布する。 |
||
| 生息域 | 沿岸性の魚です。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道・青森・岩手ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 天ぷら・フライ・唐揚げ・塩焼き | ||
| ワカサギに似るが、チカは腹鰭の基点が背鰭の起点の直下のやや後ろにある。 ワカサギは腹鰭の基点が背鰭の起点の直下のやや前にある事で判別できる。 春が旬で、天ぷら、フライで食べると美味い。 |
|||
|
和名 | チカメキントキ・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 キントキダイ科 | ||
| 別名・地方名 | アカベエ・アカメ・イーキブヤー・カゲキヨ カネヒラ・キヌダイ・キンキン・キントキ タヒノオトト・メノシタ・メヒカリ |
||
| 分布 | 能登以南、関東以南から西日本、南日本に生息する | ||
| 生息域 | 水深100mの海底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 石川・福岡・静岡・三重・和歌山・高知・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・煮付け・焼き物 | ||
| キントキダイに似るが、キントキダイより赤色が濃い。鱗が取りにくい魚です。 身質は柔らかい。味はあまりよくない。 |
|||
|
和名 | チゴダラ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | タラ目 チゴダラ科 | ||
| 別名・地方名 | イタチ・ウミナマズ・オキナマズ・ヒゼンダイ・ドンコ | ||
| 分布 | 東京湾以南から東シナ海に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深200mの砂泥底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 神奈川・静岡・愛知・和歌山ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 豊浜漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 練り製品・吸い物・煮付け | ||
| 腹面が青紫色しているのが特徴です。冬場がおいしい。 水深は200メートル位の所に多く生息しているようですが、水深600メートル位の所にまで生息してい るようです。 |
|||
|
和名 | チゴダラ(エゾイソアイナメ)・・・・ | |
| 種別 | タラ目 チゴダラ科 | ||
| 別名・地方名 | クゾウ・クゾボ・シンキョボ・スケソウ・ドンコ ヌレゾウ・ノドクサリ・ヒゲタラ |
||
| 分布 | 函館以南の太平洋側に分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸の水深10m辺りに生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 青森・岩手・福島・茨城ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 岩手県大槌魚市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 煮付け・鍋物 | ||
| エゾイソアイナメはチゴダラと同種と判断された事から訂正しました。 まだはっきりしていない事もあり、チゴダラ(エゾイソアイナメ)と分けて表記しています。 エゾイソアイナメと呼ばれていた方は、水深約10メートル程の岩礁域の浅い所に生息している。 |
|||
|
和名 | チダイ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 タイ科 | ||
| 別名・地方名 | アブラツコ・エビスダイ・コダイ・チコダイ デココダイ・ハナダイ・ヒレチコ・ホンチコ マチコ・ヨリコ |
||
| 分布 | 北海道南部以南から九州にかけて分布する。 | ||
| 生息域 | 水深40〜60mの生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 千葉・静岡・愛知・三重・和歌山・長崎・福岡 島根・石川・高知・鹿児島ほか |
||
| 撮影場所・仕入先 | 島勝漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・塩焼き・煮付け・ムニエル・鍋物・椀物 | ||
| 体に青い斑点があることでマダイに似るが、尾鰭の後縁が黒くない。(マダイは黒い)鰓蓋後縁が赤いがマダ イは赤くない。産卵期は9〜11月です。 |
|||
|
和名 | チョウザメの一種・・・・・・・・ | |
| 種別 | チョウザメ目 チョウザメ科 | ||
| 別名・地方名 | −−− | ||
| 分布 | 東北地方、北海道から北太平洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 10〜11月に河口域、6〜8月に遡上する。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道・ロシアからの輸入 | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・フライ・ムニエル | ||
| チョウザメには沢山の種が存在します。ロシアチョウザメ、ホシチョウザメ、大チョウザメ、シベリアチョ ウザメ、サハリンチョウザメ等。卵はキャヴィアとして高級珍味の一つです。赤ラベルのキャヴィアはホシ チョウザメの卵でチョウザメの中では小型です。赤ラベルのキャヴィアは比較的安い。日本にも北海道の石 狩川等で産卵のため確認された記録があるが、自然繁殖するものは絶滅したと考えられる。稀に北海道沿岸 の定置網にかかる事がある身は白身ですがやや黄色っぽく歯ごたえがある。サメと聞くとクセの強い身と思 ったが意外とクセはない。しかし後味は若干気になるかなこの頃は養殖も盛んです。 |
|||
|
和名 | チョウセンバカマ(トゲナガイサキ)・ | |
| 種別 | スズキ目 チョウセンバカマ科 (スズキ目 トゲナガイサキ科) |
||
| 別名・地方名 | バンザイダイ | ||
| 分布 | 南日本、東シナ海に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深30〜50mの砂泥底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 愛知・和歌山・高知・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 塩焼き・煮付け・唐揚げ | ||
| あまり市場に出回ることはない。チョウセンバカマの新称は、トゲナガイサキです。 | |||
|
和名 | チョウチョウコショウダイ・・・ | |
| 種別 | スズキ目 イサキ科 | ||
| 別名・地方名 | ミーバイクレー | ||
| 分布 | 高知県、小笠原、琉球列島からインド・西太平洋域に分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸浅海の岩礁域や珊瑚礁域周辺の砂底に生息する。成魚は小さな群れをつくり、幼魚は内湾の浅所や藻場で生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 鹿児島、沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 宮津 魚っ知館 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身、塩焼き、煮付け | ||
| 幼魚、若魚、成魚と模様が変化する。幼魚は観賞用として人気もある。 味もよく沖縄では食用として流通している。 |
|||
|
和名 | チンアナゴ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | ウナギ目 アナゴ科 | ||
| 別名・地方名 | −−− | ||
| 分布 | 琉球列島、西太平洋、インド洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 珊瑚礁の砂底に群れで生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄美ら海水族館 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 観賞用で食べない。 | ||
| 砂の中に住む魚で40センチほどになる。大きな黒色斑が特徴です。 水族館ではよく見かけると思われます。 11月11日はチンアナゴの日なんだって!砂地から伸び出ている姿が数字の1のように見えるからで1が一番多く並
ぶ11月11日なのでしょうか?1月1日でも1月11日でも11月1日でもいいような・・・ チンアナゴのチンは犬のチンに似ているから名付けられたと言われています。
|
|||
 ツの魚 イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 その他 魚の寄生虫
ツの魚 イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 その他 魚の寄生虫