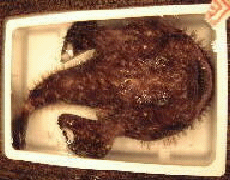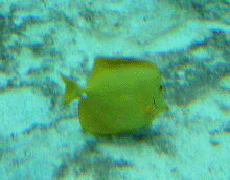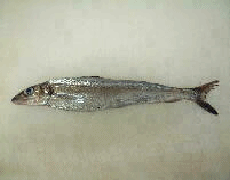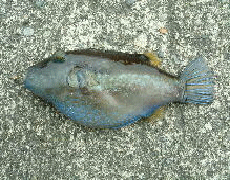現在38種類
|
和名 | キアマダイ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 アマダイ科 | ||
| 別名・地方名 | アマダイ・アマミー・キアマ・キンアマ・キンビタ キンクズナ・グシ・グジ・クツナ・ムラサキクズナ |
||
| 分布 | 本州中部以南から台湾にかけて分布する。 | ||
| 生息域 | やや深い砂泥底に穴を掘って隠れて生活する。 | ||
| 日本の主な産地 | 福岡・長崎・熊本・鹿児島・山口・島根・石川ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・西京漬け・ムニエル・椀物 | ||
| アマダイには大きく3つに分けられる。味として黄アマダイは、白・赤より味は劣る。 他種のアマダイとの区別は黄アマダイの目から口にかけて白いラインが入ることで区別できる。 見た目は赤と黄はよく似ているが、目の近くの模様で判別できる。 |
|||
|
和名 | キアンコウ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | アンコウ目 アンコウ科 | ||
| 別名・地方名 | アンコウ | ||
| 分布 | 北海道から東シナ海にかけて分布する。 | ||
| 生息域 | 水深25〜550mの砂泥底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道・新潟・石川・兵庫・島根ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 鍋物・唐揚げ | ||
| 旬は冬で鍋物として代表的な魚です。最大150cm程に成長し大きくなる。 アンコウは捨てる所がない位殆どが食べられます。 |
|||
|
和名 | キイロハギ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 二ザダイ科 | ||
| 別名・地方名 | クスク | ||
| 分布 | 高知県以南からインド洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 珊瑚礁に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄美ら海水族館 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 観賞用とししして一般には食べない。 | ||
| 食用としては流通はなく一般に観賞用です。黄色いから付いた名は単純すぎるような(笑) 体長20センチぐらい。素手で触ると棘でケガをするので気を付けて下さい。 |
|||
|
和名 | キグチ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ニベ科 | ||
| 別名・地方名 | キングチ・コイチ | ||
| 分布 | 本州中部以南から東シナ海に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深40〜160mの砂泥底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 長崎・鹿児島・沖縄 中国からの輸入が多い。 | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 塩焼き・煮付け・あんかけ・唐揚げ・天ぷら | ||
| 中国などからの輸入で入荷することがあるが、頻繁に入荷はしないため市場で見かけることはあまりない。 全体に黄色っぽく特に腹側が黄色い。 |
|||
|
和名 | キジハタ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ハタ科 | ||
| 別名・地方名 | アカミズ・アコ・アズキ・アズキマス・イネズ キジバタ・コウラギ・モズク・ヤハドリ・ヨネズ |
||
| 分布 | 本州中部以南に分布し、特に瀬戸内や山陰に多く 分布する。 |
||
| 生息域 | 沿岸の岩礁域に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 新潟・石川・福井・静岡・愛知・三重・和歌山 徳島・香川・愛媛・岡山・広島・山口・福岡ほか |
||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・煮付け・焼き物・鍋物 | ||
| 別名小豆のような斑点があることからアズキマスと呼ばれていて、関西や九州では人気が高い魚です。最大 で50cmぐらいまで成長し、旬は夏です。ハタの仲間では最高に美味い魚で高値で取引されている。 |
|||
|
和名 | ギス・・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | カライワシ目 ギス科 | ||
| 別名・地方名 | イダ・オオギス・オキギス・セギス・ダボ・ナヨ ダボギス・ニギス |
||
| 分布 | 北海道南部から沖縄にかけて分布する。 | ||
| 生息域 | 大陸棚から水深1,000mに生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道・岩手・福島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | すり身・練り物・塩焼き | ||
| 市場に入荷することは稀です。小骨が多いことで、水揚げの大半は練り製品への加工になってしまう為だろ う。綺麗な白身で脂があり味は良いが、小骨が気になる。 |
|||
 ←腹側です。 ←腹側です。 |
和名 | ギスカジカ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | カサゴ目 カジカ科 | ||
| 別名・地方名 | −−− | ||
| 分布 | 東北以北からベーリング海に分布する。 | ||
| 生息域 | 岩礁域に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 味噌汁・鍋物・唐揚げ・煮付け | ||
| 黒っぽい魚体に白っぽい柄の腹側が特徴です。産卵期は秋から冬です。 | |||
|
和名 | キダイ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 タイ科 | ||
| 別名・地方名 | レンコダイ・レンコ | ||
| 分布 | 南日本から東シナ海、南シナ海に分布する。 | ||
| 生息域 | 大陸棚の底層に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 石川・島根・山口・福岡・長崎・熊本・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 福岡魚市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・塩焼き・煮付け・椀物・鯛めし | ||
| 真鯛やチダイに似るが、ピンク色に黄色が混じることから黄鯛と呼ばれる。 お祝い用の姿物の鯛の塩焼きにもよく利用されている。産卵期は6〜7月と10〜11月の2回です。 黒鯛と同じく、性転換する魚で大きくなると80%位が雌になる。 |
|||
|
和名 | キタノホッケ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | カサゴ目 アイナメ科 | ||
| 別名・地方名 | シマホッケ・ホッケ・チシマホッケ | ||
| 分布 | 三陸、北海道、オホーツク海、ベーリング海に分布 | ||
| 生息域 | 寒冷な水域を好み海底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道・青森・岩手ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 塩焼き・煮付け・唐揚げ・干物 | ||
| 干物で出回っていることが多く、脂も乗って美味しい。キタノホッケよりホッケの方が味は良い。 アイナメの仲間だか、アイナメと違って尾がく びれているのが特徴です。 |
|||
|
和名 | キタマクラ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | フグ目 フグ科 | ||
| 別名・地方名 | イソネズミ・ウメフグ・キンチャクフグ・ギンフグ ギンバフグ・キンフグト・シュウレイ・ヨコフグ |
||
| 分布 | 千葉県以南から西太平洋、インド洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸の岩礁域に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・愛知・三重・和歌山・高知・愛媛・鹿児島 | ||
| 撮影場所・仕入先 | 和歌山県 宇久井港(写真上)、尾鷲漁港(写真下) | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い | ||
| 毒の有無 | 皮膚は強毒、肝臓と腸は弱毒、卵巣と肉は無毒とされているが、食用とはしない。 | ||
| 食べ方 | 食べない。 | ||
| キタマクラなんて、嫌な名前ですね・・・フグ毒テトロドトキシンを内臓や皮膚にもち、毒性が強いこと で、食べると死に至ることからこの名が付いたようです。 名前ほど毒性は強くはないが、この魚を見かけたら決して食べたりしないようにして下さい。当然市場に出 回ることはありませんし、漁港でも処分されています。 |
|||
|
和名 | キチジ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | カサゴ目 フサカサゴ科 | ||
| 別名・地方名 | キンキ・メンメ | ||
| 分布 | 本州中部以北から北海道、オホーツクにかけて分布 | ||
| 生息域 | 水深150〜500mに生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道・青森・岩手・宮城・福島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・煮付け・塩焼き | ||
| 脂が乗って最高に美味い。関東ではキンキと呼ばれ高級魚です。北海道ではメンメと呼ばれている。 鮮度が良いと刺身、他煮付け、焼き物と最高に美味いが高値である。 |
|||
|
和名 | キチヌ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 タイ科 | ||
| 別名・地方名 | キビレ・キチン・シオチヌ・シラチン・シロダイ チヌ・チン・チンゴ・ヒダイ・ホンチヌ・ヒレアカ |
||
| 分布 | 紀伊半島、四国、九州や台湾オーストラリアに分布 | ||
| 生息域 | 沿岸浅海の岩礁域周辺に生息する。河口にも入る。 | ||
| 日本の主な産地 | 愛知・三重・和歌山・大阪・兵庫・岡山・徳島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・塩焼き・煮付け | ||
| 別名キビレとも呼ばれている。黒鯛に似るが腹鰭や尾鰭の下部が黄色い。琉球列島からオーストラリアにか けて同種でオーストラリアキチヌがいる。 |
|||
|
和名 | キツネダイ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ベラ科 | ||
| 別名・地方名 | アカシキ・イノシシ・オテルベラ・オテルベロ キザミ・キツ・キツネ・キツネタルミ・サクラダイ |
||
| 分布 | 本州中部以南から朝鮮半島、西・中部太平洋、インド洋に分布する。 | ||
| 生息域 | やや深い岩礁域に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 福岡・長崎・熊本・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・煮付け | ||
| 背鰭の真ん中あたりに黒い模様がある。身はやや水っぽいがベラの仲間としては味は悪くない。 | |||
|
和名 | キツネメバル・・・・・・・・・ | |
| 種別 | カサゴ目 フサカサゴ科 | ||
| 別名・地方名 | キツコオホゴ・ソイ・ツヅノメ・バドウ | ||
| 分布 | 北海道南部以南から太平洋側は千葉県、日本海側は山口県に分布する。 | ||
| 生息域 | 浅海の底近くに生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道・岩手・福島・秋田・新潟・石川ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 金沢漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 煮付け・唐揚げ | ||
| 近種にタヌキメバルがいるが、タヌキメバルより体高の幅がある。ソイと呼ばれることが多い為、市場や店 頭ではソイやメバルとして販売されている。産卵期は春です。 |
|||
|
和名 | キヌバリ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ハゼ科 | ||
| 別名・地方名 | エンボウ・キヌバル・キュウゼン・ゴンジ チョウセンマンマ・ツボトキ・ホトケノイオ |
||
| 分布 | 北海道南部から九州、朝鮮半島に分布する。 | ||
| 生息域 | 内湾に生息し、1〜2月に幼魚が磯で群れるが成魚は群れをなさない。 | ||
| 日本の主な産地 | 福岡・長崎・鹿児島・宮崎・高知・和歌山ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 紀伊勝浦漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | あまり食べる事はしない | ||
| 防波堤で釣れる。(写真は紀伊勝浦漁港で釣りました) 市場や魚屋ではあまり見かけない。6〜7本の黄色く縁取られた黒褐色横帯が特徴です。 |
|||
|
和名 | キハダ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 サバ科 | ||
| 別名・地方名 | キワダ・キメジ・イトシビ・ウキンシビ コイト・シビ・ビンキリ・ホンバツ・マシビ |
||
| 分布 | 世界中の温暖・熱帯域の海に分布する。 日本では太平洋側に生息し、日本海側には殆ど生息しない。 |
||
| 生息域 | 表層回遊性 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・和歌山・宮崎・鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 紀伊勝浦漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・煮付け・寿司・鉄火丼・フライ・煮付け | ||
| 名のごとくやや黄色い肌をしていることで、キハダやキワダと呼ばれ、他のマグロに比べると脂はあまり乗 っていない。サッパリした身質です。大型になると黄色い鰭が長くなる。 体長は3mにもなる。旬は夏です。 |
|||
|
和名 | キビナゴ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | ニシン目 ウルメイワシ科 | ||
| 別名・地方名 | カナギ・ギッポ・キミイワシ・キミナゴ・コオナゴ ジャムキビナゴ・シュレン・スルル・ハマゴ・ヤス |
||
| 分布 | 関東以南から九州、フィリピン、オーストラリアに分布する。 | ||
| 生息域 | 外洋に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 愛知・三重・和歌山・高知・宮崎・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身(酢味噌で)・唐揚げ・煮付け | ||
| 九州では人気が高く、酢味噌で食べると美味しい。 産卵期は春から夏です。 |
|||
|
和名 | キビレアカレンコ・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 タイ科 | ||
| 別名・地方名 | レンコダイ・フカヤーマジク | ||
| 分布 | 奄美諸島以南の琉球列島だけに分布することから、沖縄では見かけられるが本土ではあまり見かけない | ||
| 生息域 | 水深50〜100メートルに生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄牧志公設市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 煮付け・塩焼き・刺身 | ||
| 沖縄では、フカヤーマジクと呼ぶ。 | |||
|
和名 | キビレハタ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ハタ科 | ||
| 別名・地方名 | ‐‐‐ | ||
| 分布 | 琉球列島。インド・太平洋域。珊瑚礁域に分布する。 | ||
| 生息域 | サンゴ礁域や岩礁域に浅所生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄牧志公設市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。(南方の魚はシガテラ毒に注意) | ||
| 食べ方 | 煮付け・唐揚げ・刺身・焼き物 | ||
| 名前の通りに尾びれ、胸ひれ、尻びれが黄色い。 沖縄の魚屋さんでは、普通にみられるが本土ではあまりみかけない。 体長は35cmぐらいまで成長する。 |
|||
|
和名 | キビレミシマ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ミシマオコゼ科 | ||
| 別名・地方名 | ‐‐‐ | ||
| 分布 | 琉球列島を除く中部日本以南から南シナ海に分布 | ||
| 生息域 | 沿岸の浅所から水深120mまでの砂底、砂泥底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 石川・兵庫・島根ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 煮付け・唐揚げ・鍋物 | ||
| ミシマオコゼに似るが、尾鰭が黄色味に帯びるのが特徴です。 鰓孔の上部に巨大な棘があるので注意する必要がある。 |
|||
|
和名 | ギマ・・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | フグ目 ギマ科 | ||
| 別名・地方名 | キツバ・ギッペ・コンノウ・サンボンギリ・ハゲ ツノキ・ツノギ・ツノハゲ |
||
| 分布 | 本州中部以南からインド、西太平洋域に分布する。 | ||
| 生息域 | 湾内の河口付近に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 愛知・三重ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 豊浜漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 煮付け・唐揚げ | ||
| カワハギに似た魚で、カワハギと同様に皮を剥ぎ取ってから料理する。 煮付けると美味しい魚です。東海地方では人気の魚で知る人ぞ知る魚です。 捕獲された後に大量の粘液を出し、ヌルヌルになるのが難点である。産卵期は6〜7月です。 |
|||
|
和名 | キュウセン・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ベラ科 | ||
| 別名・地方名 | アオベラ・アカギザメ・アカベラ・ギザミ・クサビ シマメグリ・ジョロウイオ・スナベラ・ベリベラ ベラ・ホトケノイオ・モズク |
||
| 分布 | 函館以南から東シナ海に分布するが、特に瀬戸内 海に多い。 |
||
| 生息域 | 内湾の砂底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 千葉・静岡・三重・和歌山・徳島・大阪・広島 香川・愛媛・山口・岡山・大分・長崎ほか |
||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 焼き物・煮付け・唐揚げ・南蛮漬け | ||
| 写真の上が雄で、下が雌です。 べらの仲間では意外に食されていて、関西、瀬戸内海近辺では珍重されている。冬の水温の低い時期に瀬戸 内海のべラは、外洋魚より成長が遅い為、身の締りがよく美味い。冬が美味いが冬眠する為夏しか釣れない |
|||
|
和名 | キュウリウオ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | キュウリウオ目 キュウリウオ科 | ||
| 別名・地方名 | キュウリ | ||
| 分布 | 北海道、サハリン、アラスカに分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 北海道花咲漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 焼き物・唐揚げ | ||
| 胡瓜のような香がすることからこの名が付いた。シシャモに似るが色は薄い 5〜6月の夜間に河をのぼってれき底に産卵する。旬は春です。 |
|||
|
和名 | キリンミノ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | カサゴ目 フサカサゴ科 | ||
| 別名・地方名 | ‐‐‐ | ||
| 分布 | 紀伊半島から南太平洋、アフリカ東岸に分する。 | ||
| 生息域 | 浅海の岩礁や珊瑚礁に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 和歌山・高知・鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄美ら海水族館 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | この魚は、背鰭棘に猛毒を持つ。 | ||
| 食べ方 | 味噌汁 | ||
| ミノカサゴの中では、最も毒が強力なので、素手で触らないように気を付けて下さい。 | |||
|
和名 | ギンアナゴ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | ウナギ目 アナゴ科 | ||
| 別名・地方名 | アナゴ・イモガラウナギ・キツネ・ギンバモ・シロアナゴ・シロドグラ・ドグラ・ハリギス・メジロ | ||
| 分布 | 北海道以南の太平洋岸、青森県以南の日本海岸から山口県、東シナ海、台湾や中国にも分布する。 | ||
| 生息域 | 水深数10〜500mを超える深海まで生息し、水深100m前後の海底から底曳網で多く生息し小型は浅海にも生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 愛知・愛媛・ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 片名漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 天ぷら・煮物、干物・練り物 | ||
| 体長は40cm前後になり肉食魚で旬は7月〜9月頃です。 マアナゴに比べると脂がのっていなく劣るが天ぷらで食べるとおいしい。 |
|||
|
和名 | ギンガハゼ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ハゼ科 | ||
| 別名・地方名 | ‐‐‐ | ||
| 分布 | 石垣島、西表島からフィリピン、北オーストラリア東岸に分する。 | ||
| 生息域 | 内湾的なサンゴ礁域浅所に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋港水族館 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 食べない(鑑賞用) | ||
| 体長は4〜6cm位の小型の魚です。 顔面や背鰭の先端部、腹鰭、臀鰭が黒色っぽく、頭部、体背面、背鰭基底部、腹鰭に多数の輝青色点が散在 している。 |
|||
|
和名 | ギンガメアジ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 アジ科 | ||
| 別名・地方名 | アカミークチミチヤー・エバ・カマジ・メッキ クチミチャー・コゼン・ナガエバ・ヒラアジ |
||
| 分布 | 南日本からインド洋にかけて分布する。 | ||
| 生息域 | 若魚は汽水域、時には川を遡る。 成魚は内湾のや珊瑚礁などの沿岸域に生息する。 |
||
| 日本の主な産地 | 静岡・愛知・三重・和歌山・高知・鹿児島・沖縄 | ||
| 撮影場所・仕入先 | 紀伊長島漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒ですが、南方の魚や大型魚はシガテラ毒を持つ場合があります。 | ||
| 食べ方 | 刺身・塩焼き・煮付け | ||
| 産卵期は4〜5月です。体長は50cm位になる。 | |||
|
和名 | ギンサケ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | サケ目 サケ科 | ||
| 別名・地方名 | アマメ・ギンマス・コクレ・ボタンコマス・マス | ||
| 分布 | カリフォルニア等北太平洋に分布し、稀ではあるが北海道北部の河川に遡上例がある。 | ||
| 生息域 | 孵化後1年位は淡水生活のち海洋生活をして河川に戻ってくる。 | ||
| 日本の主な産地 | 養殖が主で海外からの輸入が多い。北海道ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 塩焼き・ムニエル・フライ・鍋物・刺身 | ||
| 養殖が盛んで、国内でも養殖されている。 海外での養殖が多くスーパーや魚屋でも一般的に販売されている。 |
|||
|
和名 | ギンザメ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | ギンザメ目 ギンザメ科 | ||
| 別名・地方名 | ウサギ・ウサギガメ・ギンブカ・フカ | ||
| 分布 | 北海道以南の太平洋側から東シナ海に分布する。 | ||
| 生息域 | 水深100〜500mの深海底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 千葉・和歌山・福岡・長崎・鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 福岡魚市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 練り製品 | ||
| 体色は銀白色で、1m位にまで成長する。殆どが地元漁港で練り製品用として加工され市場にはあまり出回 っていない。深海に生息し卵生です。 |
|||
|
和名 | ギンダラ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | カサゴ目 ギンダラ科 | ||
| 別名・地方名 | ‐‐‐ | ||
| 分布 | 北海道からベーリング海・カリフォルニアまで分布する。 | ||
| 生息域 | 水深300〜600mの泥底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 北海道ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 塩焼き・鍋物・煮付け・照焼き・噌漬け・フライ 刺身・練り物 |
||
| 三陸では秋から春にかけて漁獲される。北海道では、ナミアラ・ホクヨウムツと呼ばれ、三陸ではキツネと 呼ばれている。肉は脂肪分が多く、肝臓の脂肪にはビタミンA・B群が多く含まれる。 |
|||
|
和名 | キンチャクダイ・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 キンチャクダイ科 | ||
| 別名・地方名 | カガミウオ・キンチャク・シマウオ・シマセウオ | ||
| 分布 | 相模湾以南から朝鮮半島、台湾、中国に分布する。 | ||
| 生息域 | 本州太平洋側はやや深い岩礁域、天草諸島では水深10位の浅所に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・三重・和歌山・鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 紀伊長島漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 観賞用で一般的には食べない。 | ||
| チョウチョウ科に似るがキンチャクダイ科の魚で、熱帯域に生息する魚だが、例外的に温帯域に適応でき る。 |
|||
|
和名 | キントキダイ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 キントキダイ科 | ||
| 別名・地方名 | アカメ・ウマヌスト・カゲキヨ・キントウジ キンメ・セマツダイ・タンヤマエグレ・ヘイテ |
||
| 分布 | 南日本、西太平洋、インド洋、紅海に分布する。 | ||
| 生息域 | 日本近海では東シナ海の大陸棚縁辺域、北緯30度以南は水深80〜120mの水温17〜22度に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・三重・和歌山・ | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・煮付け | ||
| 鱗が引き難い魚なので、そのまま切身にして煮付けや、開きにして一汐干しにて食べる。 鮮度が良いと刺身でも良い。キンメダイにも似るが味は劣る。 |
|||
|
和名 | ギンブナ・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | コイ目 コイ科 | ||
| 別名・地方名 | マブナ | ||
| 分布 | 日本各地に分布する。 | ||
| 生息域 | 浅い池や流れの緩やかな川の水草の繁茂する砂泥底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 日本各地 | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 甘露煮・味噌詰めして蒸す。 | ||
| 鯉に似るが口にヒゲがない。 銀鮒は雄が極端に少なく、雌が多く、川によっては雌ばかりの所もある。 |
|||
|
和名 | ギンポ・・・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ニシキギンポ科 | ||
| 別名・地方名 | |||
| 分布 | 本州内湾の河口付近に生息する。 | ||
| 生息域 | 北海道南部から高知、長崎に分布する。 | ||
| 日本の主な産地 | 水深20m位の潮間帯やタイドプールの石の隙間に生息する。 | ||
| 撮影場所・仕入先 | 東京築地市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 天ぷら | ||
| 天婦羅が大変美味しく、料亭の天婦羅の具には欠かせない魚の一つだった。 この頃はあまりお目にかかることも少なくなっている。見た目の割に味が良い。 |
|||
|
和名 | キンメダイ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | キンメダイ目 キンメダイ科 | ||
| 別名・地方名 | アカギ・アカギギ・カタジラア・キンメ・マキン マキンメ・ギンメダイ・ギメンダイ |
||
| 分布 | 本州以南の太平洋沿岸(世界の温帯、熱帯域)に分布 | ||
| 生息域 | 水深100〜800mに生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 茨城・千葉・神奈川・静岡・高知ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 名古屋市場 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 刺身・煮付け(うす味がおすすめ) | ||
| 目が大きく金色をしていることでこの名が付いたようです。この魚は鯛と名が付くか鯛の仲間ではない。 鯛という名が付く魚が多いが、鯛以外でタイと 付くものは、一般的に魚を指しているものです。 水銀問題がありましたが、タマネギをつま代わりに一緒に食べるとよいと言われています。 |
|||
|
和名 | ギンメダイ・・・・・・・・・・ | |
| 種別 | ギンメダイ目 ギンメダイ科 | ||
| 別名・地方名 | アオ・アオダイショウ・アゴナシ・オチョコアゴナシ・ギンメ・シウジウダイ・デンデン・マイマイ・メダイ | ||
| 分布 | 本州中部(相模湾以南)の太平洋岸から東シナ海に分布する。 | ||
| 生息域 | 深海性で水深150〜500mに生息し、300m位の場所に多く生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 静岡・愛知・高知ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 片名漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 練り製品・煮付け | ||
| ギンメダイの仲間は、下顎に2本のひげ(写真下)があるのが特徴です。 煮付けで食べてみたらあまりおいしいとは言えないので、小骨も気になる事から練り製品にするのでは? 鱗は硬めです。銀色をしているから銀目鯛と名付けられたようです。体長は30cm位になる。 |
|||
|
和名 | キンメダマシ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | キンメダイ目 キンメダイ科 | ||
| 別名・地方名 | アカシロ、シカロ、グイグイジャコ、ヒカラボ | ||
| 分布 | 八丈島、神奈川県以南の太平洋岸から長崎、琉球列島、西太平洋、西インド洋に分布する。 | ||
| 生息域 | やや深い岩礁や砂底に生息する。 | ||
| 日本の主な産地 | 長崎・鹿児島・沖縄ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 沖縄美ら海水族館 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 練り製品、煮付け | ||
| 底曳網で漁獲されるが市場にはほとんど出回らない。 体長20〜30cm位になる。 キンメダイに比べると味は劣る。 |
|||
|
和名 | キンメモドキ・・・・・・・・・ | |
| 種別 | スズキ目 ハタンポ科 | ||
| 別名・地方名 | アカシロ、シカロ、グイグイジャコ、ヒカラボ | ||
| 分布 | 房総半島以南、朝鮮半島、西部太平洋に分布する。 | ||
| 生息域 | 沿岸の岩礁域やサンゴ礁域に生息する。 夜行性で、昼間はサンゴの隙間や岩孔などに群れで潜むが、夜間はその中より出て活動する。 |
||
| 日本の主な産地 | 千葉・静岡・三重・和歌山・高知・鹿児島ほか | ||
| 撮影場所・仕入先 | 紀伊長島漁港 | ||
| 珍魚度 | 一般的 ★ ★ ★ ★ ★ 珍しい | ||
| 味の評価 | 不味い ★ ★ ★ ★ ★ 美味い | ||
| 毒の有無 | 無毒です。 | ||
| 食べ方 | 唐揚げ | ||
| 半透明で骨が見える魚です。大きな群れをつくって泳ぐ習性があります。 あまり食べる魚ではない為、市場には出回っていませんので魚屋さんでは、あまり見かけない魚です。 |
|||
 クの魚 イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 その他 魚の寄生虫
クの魚 イカ類 タコ類 エビ類 カニ類 貝類 海藻類 その他 魚の寄生虫